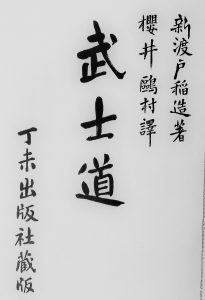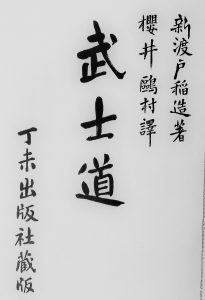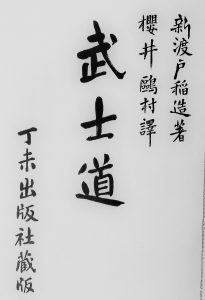


武士道を考えるー1

開運村村長・花見 正樹
武士道という言葉が歴史上に現れるのはいつからかは知りません。いま、私が用いている「武士道」という言葉は、幕末も終焉を迎えて武士そのものが消滅した明治33年(1900)に英文で発表された新渡稲造博士の著書「武士道」の日本語版からの引用です。
それ以前の実際の武士道なるものは、全国に三百藩以上あった各地各藩の藩主の訓示に依るか、歴史上に名を連ねる著名な武士・武将達の重んじた家訓、心構えや礼節などを元に想像する他はありません。そうなると肝心の「武士道」は人によって違って千差万別、基準が定まらないことになります。
「武士道」といっても戦国時代と江戸時代では全く違います。隣国との死活を賭けた戦いに明け暮れた戦国時代までの武士は、孫子の兵法を基本とした欺瞞と略奪と殺戮が主で、その代表的兵法が甲斐の戦国大名・武田信玄軍でその軍旗に記された「風林火山」は、孫子が遺した兵法の軍隊の動かし方の基本をそのまま用いています。風林火山とは、「疾(はや)きこと風の如く、徐(しず)かなること林の如く、侵掠(しんりゃく)すること火の如く、動かざること山の如し)」で、この中の「侵略(しんりゃく)すること火のごとし」には現地調達、戦利品の略奪が許されていて、当時の戦いが「武士道」にはあるまじき欺瞞・略奪・殺戮・侵略戦争だったことが分かります。
その後、徳川家康の天下統一後は、殺し合いのない武士の時代になり、武芸に優れた豪傑よりも、単純に国(藩)を治める為に都合のいい武士が必要になります。これが、今の世の官僚、公務員、政治家の前身ですが、江戸時代と現代の大きな違いは「武士道」の欠落です。昔なら切腹ものの公私混同の大金の使い込みも、頭を下げ続けるだけでうやむやにされ無罪放免ですから呆れます。これをしない、これを許さないのが武士道という道徳観念で、これが現代ではどこに消えたのか探しても見つかりません。
時代錯誤かも知れませんが、日本人はもう一度、武士道の長所欠点を総括してみる必要があるような気がします。
それと、幕末の人物像なども東西に拘らず冷静に「武士道」的観点から、その人間性をみてみたいのです。
ならば、ここは新渡戸式「武士道」を標準に考えるのが一番手っ取り早い方法であるのは間違いありません。
それでも、自分が小説に書く人物の日記や遺された資料などから、「武士道」の著書の説く内容を100点満点として合わせ考えると「武士道度80点」とか「武士道35点で武士としては失格とか、歴史好き仲間大勢で武士道から見た客観的評価をすれば、武士・武将の武士道的評価がはっきりするかも知れません。
ともあれ、まず最初に武士道とは何であるかを新渡戸式評価法で確認してみたいと思います。
写真の書籍は、えむ出版刊の新渡戸稲造「武士道」の復刻版ですが、その内容を優しくかみ砕いて連載してみます。
この項の最初に触れた通り、「武士道」は、新渡戸稲造が外国の人に日本人の道徳、死生観など、個別には、仁、義、礼、誠、孝、勇気、名誉、忠義、切腹、刀、女性の在り方、信仰、教育などを知ってもらうために書いたものです。
原文は英語で書かれていますが、西洋の哲学や欧米各国の格言などもかなり使っています。
序文は、新渡戸稲造がこの本を書くことになった経緯の説明です。
米国にいた新渡戸稲造がある日、親しいベルギー人の法学者と雑談をしていたときに、相手の法学者から「日本では宗教や道徳教育はあるのですか?」、「ない」と答えると、「では、どうやって子供に道徳観念を教えるのですか?」と言われたのです。
これに応えられず、数日間、熟考して出した結論が、「日本の道徳観念は封建制度と武士道が根幹を成しているのではないか?」、です。
新渡戸稲造は、そこから考えて武士の道徳習慣を体系化し、本格的に取り組んで本にしたのが英文の「武士道」で、この本は、日本をはじめ各国語に訳され、世界的名著として知られることになりました。
当時、世界一治安のいい国は日本でしたから、日本人の民度の高さは、この「武士道」教育によるとも考えられたのです。
これは、聞いた話しの請け売りですが、日露戦争当時のアメリカ大統領のS・ルーズベルトは、この「武士道」を読んで深い感銘を受け、激しい戦闘で双方が疲弊しつつあった日本とロシアの戦争終結への講和に名乗り出たといいます。
ともあれ、この「武士道」とは現代でも亡霊のように時折甦って来ますから気になるのです。
では、次回をお楽しみに・・・