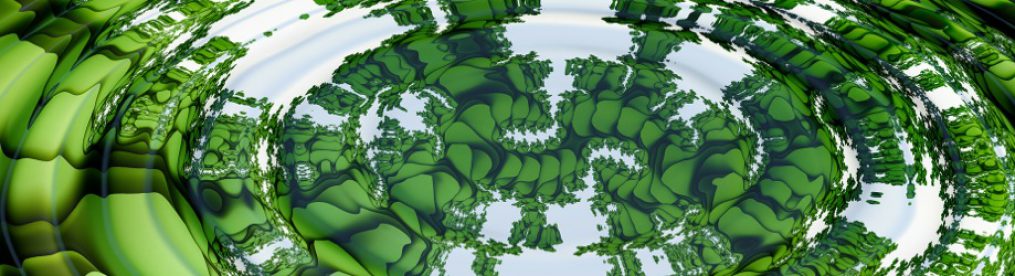源頼朝にみる武士道
花見 正樹
源頼朝(みなもとのよりとも)は、久安3年4月8日(1147)に、清和天皇の流れを汲む河内源氏の頭領・源義朝(よしとも)の三男として生まれます。幼名・鬼武丸から鬼武者、頼朝と名は変わりますが、通称は三郎です。
父・義朝は清和天皇を祖とし、河内源氏の流れを汲む武士です。保元元年(1156)の保元の乱では、平清盛らと共に後白河天皇に従って戦って勝利しますが、平治元年(1159)の平治の乱では、後白河上皇の近臣であった藤原信頼の反乱軍に加わって、三条殿焼き討ちを決行しますが、官軍となった平清盛軍に敗れて謀殺され、長兄も次兄も処罰され、三男の頼朝も死罪でしたが、清盛の継母である池禅尼(いけのぜんに)の嘆願もあって死罪を免れます。
永暦元年(1160)3月に、14歳の頼朝は、伊豆の蛭ヶ小島(ひるがこじま)に流刑になります。
比較的自由な琉人生活の中で、源氏方に従ったために所領を失った武士らが従者となって頼朝のもとに集って来ます。
頼朝は、安達盛長、佐々木定綱四兄弟らと、地方武士として日々鍛錬を怠らず過ごし、やがて、監視役になるべき平家方の武將で伊豆の豪族・北条時政の長女・政子と親しくなります。
これを知った政子の父・時政は、政子を地侍の山木兼隆に嫁がせるが、政子はその婚礼の場から抜け出して頼朝のもとに走ります。
諦めた時政は、政子を頼朝の妻と認め、頼朝と政子の間に大姫が生まれます。
ただ、最近では、この山木兼隆の話は創作とされています。
治承4年(1180)4月、後白河法皇の第三皇子である以仁王(もちひとおう)が平氏追討を命ずる令旨を諸国の源氏系武士に発しま 頼朝にも、叔父の源行家経由で令旨が届きますが、政時の助言で「機至らず」と静観して動かずにいます。
政時の推測通り、戦いに利なく、以仁王は源頼政らと共に宇治の戦いで敗死します。
だが、勝ち誇った平氏は、令旨を受けた諸国の源氏系武士の追討を厳命、頼朝にも危機が迫ります。やむなく、挙兵し、伊豆国目代の山木兼隆の韮山目代屋敷を襲撃して兼隆を討ち、気勢を上げますが、相模国土肥郷へ向かった頼朝軍300騎は、そこで待ち伏せた平氏方の熊谷直実、伊東祐親ら三千余騎に包み込まれて敗北し、頼朝は土肥実平ら僅かな従者と共に箱根山中へ逃れます。
治承4年(1180)8月末、安房国平北郡に上陸した頼朝は、房総の豪族・上総広常、千葉常胤らの加勢を得て、9月に安房国から上総国、下総国と出て、千葉一族と合流し、さらに上総広常の大軍と合流、頼朝軍は進軍し、さらに武蔵国の豪族・葛西清重、足立遠元らの軍勢を加えて、かつて敵対していた畠山重忠や河越重頼らの軍も従属させてかつて父の義朝の支配地だった鎌倉へ入ります。
その後、着々と鎌倉を整備して新たな政治の拠点とし、平氏との決戦に備えます。
その秋、平維盛(たいらのこれもり)率いる平氏の追討軍が駿河国まで来ると、鎌倉勢も武田信義と北条時政ら頼朝軍2万で進軍し、富士川を挟んで対峙しますが、夜半、水鳥の飛び立つ音に驚き浮き足立った平維盛軍は慌て乱れて潰走し、頼朝軍は戦わずして勝利します。
その勢いで頼朝は上洛を目指しますが、味方の総意が得られず、やむなく黄瀬川まで兵を引きます。
この日、頼朝の異母弟である源義経主従が、頼朝軍に合流します。
これを機に、鎌倉に戻って、新たな政務を侍所を中心に行うことになります。
治承4年(1180)末にはまだ、平氏と源氏の優劣の差は全く見えていず、国内のあちこちで小競り合いが始まっていた。
四国伊予、近江、甲斐、信濃、美濃、尾張の源氏系武士、肥後の菊池隆直軍が挙兵して頼朝軍に投じ、平氏も福原を去って京都に都を戻して反撃に出ました。平氏は南都の寺社勢力を制圧し、近江源氏を倒しますが、平清盛が熱病で世を去ります。
その後、一進一退の攻防が続きますが、その均衡を破ったのが義経軍でした。
寿永2年(1183)春に挙兵した木曽の義仲が、平氏との戦いに連戦連勝し、ついに平氏を追い落として都を制圧します。
しかし、平氏に替わって都に入った義仲軍は、統率も乱れて乱暴狼藉や略奪で都人の反感を買います。後白河法皇もさすがに木曽軍に見切りをつけ、義仲に西国の平氏追討を命じ、代わって頼朝に上洛を要請します。
しかし、頼朝は上洛を断ります。頼朝は奥州の藤原秀衡らに鎌倉を攻められるのを恐れたのと、京にはもはや、数万騎の頼朝軍を賄うだけの余力がないことも知っていたのです。
その後、木曽軍が平氏追討で破れ、京に戻って、頼朝追討の命を望み、一度は断られますが、実力で後白河法皇を拘束して頼朝追討の宣旨を出させ、強制的に征東大将軍に任ぜさせて、源範頼と義経率いる頼朝軍と戦って自滅し、義仲は粟津の戦いで討たれます。
義仲を討った範頼と義経の軍は、平氏を追討すべく京を発ち、摂津国一ノ谷の戦いで平氏を破ります。
文治元年(1185)1月、鎌倉の範頼から、軍内部の不和や食料不足、帰還を望む武士達の窮状を訴える書状が届きます。
頼朝は、九州に逃れた安徳天皇や建礼門院の無事を願い、これ以上は軍を動かさず、九州の武士達から反感を買わぬようにと
気遣った返書が範頼に届きます。さらに、九州の武士には、範頼に従って協力を望む書状を届けています。
その範頼への書状をみた義経は、後白河法皇に親書で西国出陣を奏上して、その許可を得て讃岐国屋島に出陣し、ここでの戦いで平氏を海上へと追いやり、さらに、九州の武士から兵糧と多くの船を得た範頼が義経と力を合せ、豊後国へと渡ってから、3月24日の壇ノ浦の戦いへと進み、ここで平氏を滅亡させますが、同時に、幼い安徳天皇の命をも海の藻屑にして、頼朝の意に反した結果になっています。
文治元年(1185)4月、平氏追討で義経の補佐をした梶原景時から、義経を弾劾する書状が頼朝に届きますが、頼朝は無視します。
さらに、頼朝は幕府の内挙を得ずに朝廷から任官を受けた関東武士らの任官を認めず東国への帰還を禁じますが、同じく任官を受けた義経だけには咎めを与えませんでした。
その上、範頼の指揮権への越権行為、義経が配下の武士達に勝手な処罰など専横を訴える武士の報告、それらが入り、頼朝も仕方なく義経を代官から外し、武士達に義経の命には従ってはならなという命が出されました。
義経は、壇ノ浦の戦いで捕らえた平宗盛父子を伴って相模国まで意気揚々と凱旋し、腰越から鎌倉に入ろうとします。
しかし、頼朝は宗盛父子のみを鎌倉に入れ、義経の鎌倉入りを許しませんでした。鎌倉では主要な御家人数人が義経に謀反の疑いありと報告していて、その理由を聞くまでは義経を鎌倉にはいれられない、という雰囲気だったのです。
もちろん、その時の義経にはそんな気など全くありませんでした。
腰越に留まる義経からは、鎌倉入りの許しを請う書状(腰越状)が頼朝に届きます。だが、頼朝は、それを無視して、面会を終えた平宗盛親子を伴って京に戻るように義経に命じます。
頼朝としては、義経を京に戻すことで、鎌倉武士内部の軋轢を消し、義経の身の安全を図りたかったのです。
何故なら、義経を弾劾する数々の訴状をあわせると、いくら頼朝が頭領でも、義経を死罪から守ることは出来なかったのです。
しかし、これを機に義経は頼朝を深く恨んで、「鎌倉に怨みを成す関東武士は、義経につくべき」と言います。
この時、はじめて義経に、鎌倉に反旗を翻す謀反への感受が感情が湧いた、と私は思います。
後世に至り、判官贔屓の日本人気質からは、義経が善玉で頼朝が悪玉となっています。
しかし、頼朝の平家打倒の旗印には全国の反平家勢力が結集し、義経の打倒鎌倉には誰も応じなかった事実は無視できません。
頼朝には頼朝なりの賞と罰の論理があり、仁において武士道が存在するのは確かです。
それを理解できた時、義経だけでなく孤独だった頼朝にも情を寄せることが出来るのかも知れません。