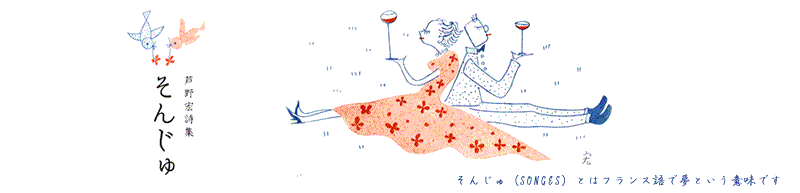しあわせ
幸福を売る男
芦野 宏
プロローグ
昭和三十一年パリ、夢の劇場出演
初めて訪れた晩秋のパリは、灰色の曇り日が続いていた。
その日も鉛色の重たい空気がよどんでいた。
朝からソワソワしてちっとも食欲がない。
なにもしないで寝ていようと思って目を閉じるけれど、少しも眠くない。
劇場は夜九暗からなのに、午後三時からオーケストラの音合わせがある。とにかく横になっ㌔いようと思って寝ている。
ギャルソンにポタージュと肉を運ばせて寝
ながら食べる。やはり食べなければならないから……。
昼ごろから一時間ばかりうつらうつら眠り、少し早めに支度して出かける。
オランピアの前に釆たら、私の名前が大きく出ていた。
横文字なのでピンとこないけれど、たしかにジョルジュ・ユルメールの上にでかでかと出ていた。
ロベール・リバの名前はその上に書かれていた。
昼間見る劇場はうす汚くて目立たなかったが、もう日暮れも近いせいか大看板の電飾はキラキラ輝いていた。
マドレーヌ広場に近いこの「オランピア劇場」は、シャンソン歌手の憧れの舞台であり、エディット・ピアフもイヴ・モンタンも、そしてジルベール・ペコーもこの舞台から全世界にメッセージを送ったのである。
日本でいえば歌舞伎座のような格をもつ劇場である。
初めて訪れたパリで、なぜ私がここで歌うことになるのだろう。
信じられないことだが、事実なのである。
だから恐ろしかった。
楽屋はこぢんまりした個室で、小さな鍵を渡されて待っていたが、不安な気持ちはつのるばかりである。
いつもの白い上着は持ってきていないので、黒いタキシードに西陣織の光るネクタイとカマーバンドを着けて舞台に出ることにした。
だれかが 「ムッシュー」と言って迎えにきたので、おもむろに出ていった。
少しもあがっていないふりをしてゆっくり歩いていったが、のどがカラカラに渇き、息苦しくて歌えないような気分になった。
こんなとき日本でなら必ずマネージャーか付き人がいて、「水」を一口用意してくれるのだ。
まだ間に合う。私は迎えの男性に「水、水がほしい」とフランス語で頼んだ。
びっくりしたような表情で、彼は私をトイレに案内したのである。
私はあわてて彼に言った。
「ソワフ」、のどが渇いているのだ、と。
にっこり笑った彼は、ブランデーの瓶を一本持ってすぐに現れた。
アルコールは一滴も駄目で、とくに歌う前はもってのほかである私は、諦めることにした。
もう舞台の袖では私の出番がきていたからである。
司会者が東洋の果てから釆たシャントウール・ド・シャルム (魅惑の歌手)、「イロシ・アシノ」と紹介している。
もうなにがなんでも歌わなければならない。
ああイントロが始まっている。
つづく・・・