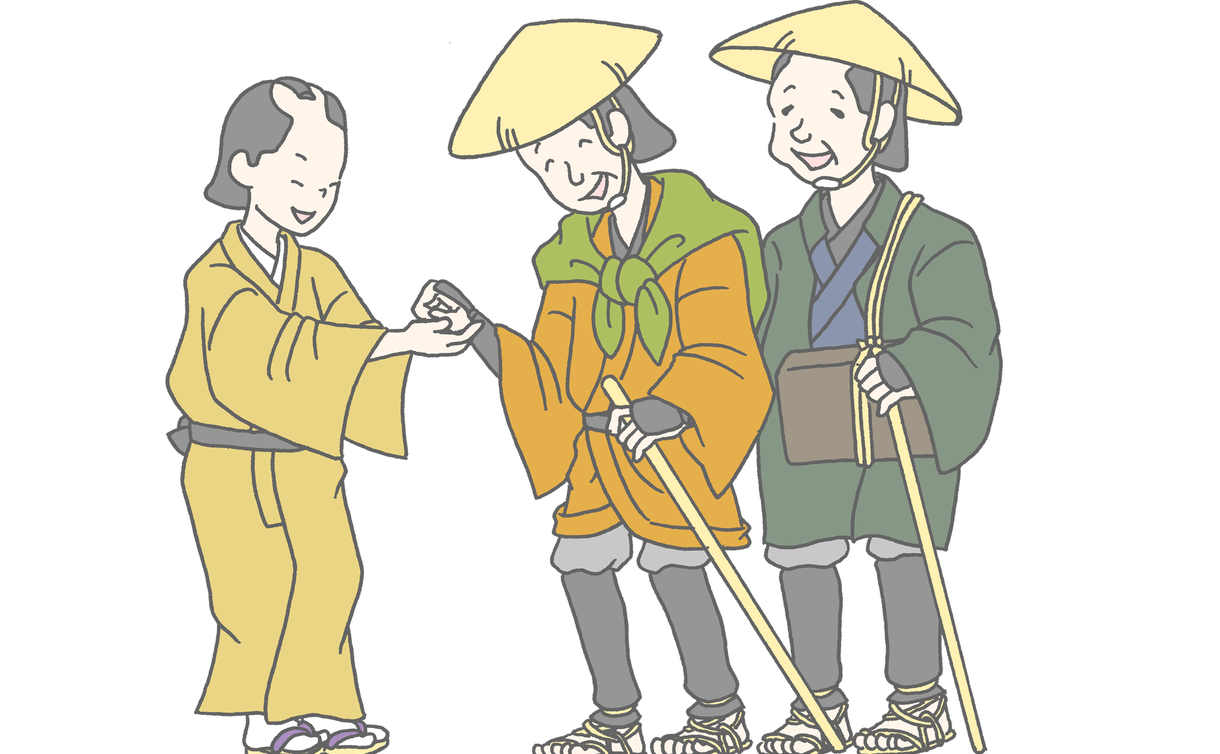第四章 餓狼の群れ
1、担庵の死
安政二年(一八五五)一月一六日、国防に奔走した代官・江川担庵が逝った。本所南割下水の江戸下屋敷で、家族、手代、幕府の要人、友人らに看取られての大往生だった。
この悲報を歳三は、江川家に暫しの定宿と知らせてあった上州前橋の旅籠「柏屋」で知った。
ある小雪散る夕暮れ前、藍色の二重の着流しで天蓋(てんがい)を被り、袈裟掛けに明暗の文字入れの箱を下げた虚無僧が宿の前の軒下で尺八を吹いた。その音色は雪の中にもの悲しく響いてゆく。
宿の番頭が外に出て「手の内ご無用に」と、丁重に断りながらも数枚の銭を渡そうとした。
「それには及ばぬ」
虚無僧が深編み笠をとって頭を下げて言った。
「こちらに小間物商・弥太郎というご仁はおるかな?」
「はい、いらっしゃいます」
「相部屋でいい。そこに泊るぞ」
これが岡野壮四郎だった。
案内した女中があわてて衣服の濡れを拭きとろうとすると、手拭いを奪って自分で拭いた。
「歳さん、暫くだな」
ニ階の奥の間に入った荘四郎は、濡れた衣服のまま座って火鉢に手をあぶった。
「なかなか澄んだいい音を出すな。本物の普化宗かと思ったぜ」
「本物さ。歳さんは尺八もやるのか?」
「盲目の長兄が、道楽で三味線でも尺八でも何でもやるもんで耳達者になっちまったんだ」
「そうだったな。為次郎さんは元気かね?」
「兄貴は今じゃ石翠とか名のって弟子まで集め、芸事三昧の暮らしらしい」
「そいつはいいや」
歳三はすでに湯を浴びて、手酌で独り酒を飲んでいたところだった。
「歳さんは、明るいうちから飲んでたのか?」
「雪だし、柏木さまからの早文で岡野さまが来るって知らせがあったからな」
「それで、真っ昼間から酒か?」
「朝からだよ」
「いい身分だな。拙僧も付き合うぞ」
「おっと、普化宗なら宿での酒はいけねえはずだぜ?」
一月寺など名のある虚無僧寺では、托鉢僧の規範を条文にしているのを歳三は知っていた。
たしか、公儀の御法度を守る、諸国の国法を守る、朝夕の読経を勤める、争いをしない、宿では酒を飲まない、博打はしない、騒ぎを起こさない、こんな禁律だったような気がする。
荘四郎が笑った。
「なあに、俄か僧だから戒律なんぞ何も知らん」
「代官の手代なら、勝手に僧に化けてもいいんのかい?」
「青梅の鈴法寺から、ちゃんと托鉢自由の認可を出させたさ」
女中に手拭いを返しながら、熱燗の酒と肴をかなり余分に頼み、荘四郎は改めて座り直した。
「殿の直筆だぞ」
首に掛けた布袋から取り出した油紙包み入りの封書を、歳三に手渡した壮四郎が目を伏せた。
包みを解き紙面を見ると、乱れてはいたが確かに見慣れた担庵の米庵流の書があった。
「これからも国のために頼む」
これだけの乱れ書きの短文だが、宛名は石田村歳三殿とあり、末尾の字は確かに英龍と読めた。
死を覚悟した担庵は、枕元に息子の英敏と執事の柏木惣蔵、手代の根本慎蔵の三人を呼んで、江川家に縁のある一人一人に一言づつ、最期の力を振り絞って遺言を書き残したのだ。
しかも、丹庵は苦しい息の下で、「石田の小倅を手代に取り立ててやってくれ」と、言い遺した、と荘四郎は言った。「いずれ武士に」、と言った歳三の子供心を丹庵は覚えていたのだ。
その気配りに感謝し、ありし日の担庵のおだやかな笑顔を思い出しつつ歳三は、久しぶりに会った壮四郎と各地の情勢を語り合い、今後の国情を憂いて長き夜を飲み明かすことにした。
国防のために寝食を忘れて東奔西走して命を縮めた坦庵は、老中筆頭・阿部正弘から勘定奉行栄転の内示を受けながら、それを冥土の土産に逝ってしまった。行年五十五歳、惜しまれての早すぎる死だった。
逝去寸前、隠居して僧籍にある親しい遠山金四郎景元が病身をおして駆けつけて担庵に顔を寄せて手を握り、「わしもすぐ後を追う。安心して先に行け」と、囁いたという。
担庵や渡邊崋山と盟友でもあった川路聖謨(としあきら)は、公用の下田行きを前に江川家を訪れた。聖謨は担庵の顔に被せた白布を少し上げ、おだやかな死に顔を眺めてか手を合わせて拝み、布を掛けてから手を顔に当てて号泣し、その涙を拭こうともせずに立ち上り、供を揃えて外国使節の待つ下田へと旅立って行った。
在りし日の江川担庵は、渡辺崋山や川路聖謨らと共に、蘭学者の集りである尚歯会に参加していて、鎖国攘夷主義の急先鋒の鳥井耀蔵らと対峙して暗闘していた時代もあった。仲間の渡辺崋山が天保十二(一八四二)年の蛮社の獄で捕らえられて獄死したが、江川、渡辺、川路ら尚歯会では、当時の西洋事情や海外の優れた技術などを研究して、いずれ日本も外国と対等に戦える力をつけた上で、海外との交易を開くのが得策との観点からさまざまな研究を始めていた、と、歳三は聞いたことがある。
2、夢の実現
荘四郎が言った。
「殿の死をもっとも悼んで悲しんだのは、意外だが、筆頭老中の阿部正弘さまだったよ」
「タンナンさんと安倍さまは、同じ開明派だったからかな?」
「阿部さまは、頼りにした殿の死を知った瞬間、筆頭老中の座を降りる決意を固めた、と仰っられた」
「タンナンさんは、それほどまでに幕府に影響力を持っていたのかね?」
「阿部さまが登用した人材は、我が殿・江川英龍をはじめ、勝麟太郎、大久保忠寛、永井尚志、高島秋帆、遠山景元、川路聖謨さまなど優れた人物ばかりだった。それだけに一人欠け二人欠けと少しづつ身内が抜けていくのが、たまらなく辛かったんだろうな」
阿部正弘は江川担庵と組んで、海防の強化にも努めた上に、講武所の開設や長崎海軍伝習所の創設、西洋の大砲製造技術の採用、大型戦艦の建造なども積極的に考えて軍備の改革にも取り組んでいた。
その阿部正弘の開国に積極的な姿勢は、かたくなな勤皇攘夷派とも相容れず、ごく自然に有力外様大名の知恵や力を頼りにするようになり、いつしか親藩と外様の差別がなくなり、ペリー艦隊来訪以来の国難への対応策も国中から求めることになった。これによって、今まで表に出ていなかった幕府の脆弱さが明らかにされてしまったのだ。
「時代の流れは、明らかに開国へと向かっているんだ。今更、鎖国だ攘夷だなどと叫んでも無意味なのに、朝廷が異国嫌いであることを利用しての反幕府勢力の動きが激しくなってるんだ」
「こうなると、国中が開国か攘夷かに割れてくる。これも時の流れで仕方ないことだがな」
壮四郎も歳三も、日本が国を開き、海外に活路を求めて雄飛すべき、という点では意見が一致している。ただ、旧態依然とした形式だけで戦いを忘れた武家社会の集合体である幕府では、武力も外交力もはるかに上の諸外国と、対等には戦えない。この点では莊四郎も歳三も懐疑的ではだからといって、いつまでも曖昧な解答でぐずぐずと外国との交渉を引き延ばすことも出来ない。交渉でも戦いでも相手の手強さが歴然としているだけに、今のままでは勝てないという幕府内での少数意見にも反論はできない。
「薩摩、長州など雄藩の意見も必要と考えた阿部正弘様の考えは正しかった。だが・・・」
荘四郎は、残念そうに続けた。
「殿は公武合体を願ったが、それが実を結ばず、結果的には有力な外様大名の政治権力欲につながり、意見が割れての権力闘争になる。いずれは国内が二つに割れ、関ヶ原の二の舞になる。それこそ乱世の到来だ。これが亡き殿、江川担庵の出した結論だ」
「乱世が来るのか? それで江川家は、軍備を急いだのか?」
「そうだ!」
荘四郎が、きっぱりと言った。
無言で頷いた歳三が、障子を少し開けて外を見た。
まだ雪が舞っていた。
壮四郎が続けた。
「今のまま外国が一気に攻めて来たら、戦って勝てると思うか?」
「斬り合いなら負けんが、異人は遠くから連発銃で撃ちまくってくるらしいからな」
「火縄銃だと敵の顔が見える距離まで待たんと倒せんが、最新式銃は人の姿が豆粒でも的確に撃たれるぞ」
「隠れて待ち伏せしたら?」
「心配するな。韮山で作っている小銃の性能も悪くはないぞ。ただ、量産が出来んのだ」
「大砲は?」
「異国の大砲は二十町(約二・二キロ)先の頑丈な家でも吹っ飛ばす。それでガンガン撃たれたら、堅固な城だって持たんよ」
「そんなの、韮山で作れるだろ?」
「簡単に言うな。韮山の反射炉も金属溶解量には限度があってな。今、作ってるのは八十ポンド青銅製カノン砲ってやつで口径二百五十ミリ、砲身の長さが二間七寸(約三・八メートル)がせいぜいだ。これを鉄製で大型化して大量の火薬を詰めた砲弾で破壊力を強め、長距離の敵陣を木っ端みじんに吹っ飛ばすには、まだまだ製鉄や火薬の製造技術、射程や発射速度、砲弾炸裂による破壊力なども大切だし、これを的確に目標物に命中させる精度の高い砲術を身に着けた砲兵の養成も必要になる。強大な異国の軍隊と戦って勝つにはまだまだ道は遠いさ」
「ならば、どうすれば強くなる?」
「いま、国内で反射炉を持って大砲造りで進んでいるのは佐賀の鍋島様だ。そこで生前の殿は鍋島様と会って技術交流を図った」
「鍋島は応じたのか?」
「佐賀藩の自治領に武雄という地があり、そこの領主の鍋島茂義(しげよし)公が高島秋帆に師事して軍事研究に没頭、オランダから軍人を招いて教練をしたり、自ら家臣と共に高島秋帆に弟子入りして西洋式砲術を学んで免許皆伝を受けていた。高島門下で後輩にあたる殿は、武雄の地を訪れて、鍋島家の軍事教練や大砲鋳造を見学して交流を深め、以後、佐賀と韮山が砲術の最先端を同門で競うことになったのだ」
「よき競争相手だね?」
「剣術や相撲だって、強い相手と数多く試合を重ねてこそ強くなるんだ」
「すると、いつかは佐賀藩製と韮山製の大砲が戦場でまみえることになるのかな?」
「それは分からん。佐賀は自藩が技術を独占、韮山は今までに各藩から派遣された千人近い門人に門戸を開いて技術を共有している」
「タンナンさんは、太っ腹だからな」
「いや。これは日本国を強くするために阿部さまが考えた幕府の方針で、それに殿が賛同して始めたことなのだ」
「あくまでも、外国に備えるためだな?]
「当然だ。だが、殿は、各地での外国艦隊の戦果を分析して、彼我の差を冷静に判断された」
「どのように?」
「いま、外国の攻撃あらば我が国は壊滅、敵国支配下の属国になる。それを防ぐには?」
「なにか妙案が?」
「まず国内で戦乱を起こし、充分に実戦で経験を積み、武器や戦略も近代化させてから人心を一元化させ強力な国家を築き外敵に備える」
「国内で戦えば勝ち組と負け組が出る。負けると分かって戦う藩はあるまい」
「人は切られて血を見てから痛みを感じるものだ。戦う前は勝ち戦さしか考えんよ」
「江川家は何をする?」
「相撲でいえば裏方、呼び出しと行司の役割かな」
「おれは?」
ふと、荘四郎の目が鋭く光った。
「これから暫くの間、歳さんの身柄は江川家が預かる」
「どうする気だ?」
「わしと同道してまずは韮山。ただし、今回の行動は喜六殿以外の誰にも内密になる」
荘四郎が真剣な表情で歳三を見た。
「国内の戦さでも銃撃戦が主体になるが、それでも人間同士がぶつかれば斬り合いになる。そこに剣客の活躍の場があるのだ」
「なるほど」
世が荒れて、幼少期から武士になる夢を抱いて育った、歳三の夢の実現が急接近している。
ペリー艦隊来航以降、日本中が騒然として浮足だっている。
老中筆頭・阿部正弘の打った幕閣外からの積極的な意見の公募、この賭けも危険すぎた。
この機に乗じて、外様や反幕府勢力の大名が結集して自藩の立場を主張し始めたから収拾がつかなくなっている。これによって、生前の担庵が危惧し、予言したように国内が二分三分して、幕府内でも人心の亀裂が始まった。その対立の構図が、尊皇攘夷、開国左幕、この二つの図式になって渦を巻き、尊皇開国という最善の選択はかき消されている。
その理由は単純で、公卿が操る朝廷側と武家政治を存続させたい幕府、この二大勢力の思惑の違いだった。朝廷主軸の政権復古を目ざす公卿達が、開国による異人の政治的介入を嫌ったのが攘夷だった。
その点、幕府は政権の維持が保証され、国益が損なわれなければ開国に妥協の余地もあると考えた。
朝廷側に立つ集団は尊皇攘夷、幕府側はひとまず開国にと、事態は荒れ模様のまま進行していた。
雲の上の存在である朝廷が、大の異人嫌いで幕府に攘夷を命じているという、これでは朝廷があまりにも狭量過ぎるように思えて仕方がない。国主である朝廷が何故に国益に反する攘夷に拘るのか?
歳三は、子供の時から親類の貿易商宅や漢方医・本田覚庵を通じて世界の中の小さな日本の立場を知っているだけに、武士になる夢以上に海外雄飛は望むところだった。
担庵という大船が沈んだ今、歳三は、体ひとつで大海原に放りだされて波間に漂うような不安で落ち着かない気分を感じていた。もの心ついた子供の頃から担庵の影響を受けて育った歳三にとって、この後の展開が全く見えていない。
姉ノブが嫁いだ日野の佐藤彦五郎は、わずか十一歳の時に代官・江川担庵の後見で日野宿問屋・寄場名主十一代の座を継いでいる。それ以来、担庵の指導で多摩の治安や行政に携わり、小野路の小島鹿之助と共に担庵の目指す多摩農兵隊の実現にも尽くして来た。その一環として天然理心流の道場も開き、多摩の農民の次男以下に戦うための剣技を習得させてきた。さらに、多摩の政りごとに関する限りにおいては、担庵と佐藤彦五郎は、表裏一体の仲にあり、いわば多摩は担庵の隠し里の役割を果たしていた。
担庵は何事も自分が育てた日野宿の大名主・佐藤彦五郎に相談しながら多摩の発展に尽くして来たのを、歳三は、幼い時から担庵と彦五郎、兄の喜六の薫陶を受けて育ってきた歳三はよくその事情を知っていた。その担庵がもういない。義兄の彦五郎にとっても、父とも仰ぐ担庵の死は大きな衝撃となっているに違いない。
その担庵は、積極的な開国論者だった。
生前、蘭学者の渡邊崋山、高野長英らと西洋事情研究のための尚歯会(しょうしかい)に参加し、日本は世界に羽ばたくべし、を積極的に進めたが、天敵ともいえる鳥居耀蔵の厳しい弾圧で崋山ら仲間が処罰され、開国への弾みは停滞したが、その遺志は江川家の番頭・手代、江川家支配下の各地名主や、歳三らにまで継がれていた。いわば、相模、武蔵、下野、甲州など関東一円に渉って、幕府の名を隠れ蓑にして代官・江川家の行政が行き渡っていた。当然ながら幕府直轄地の多摩も代官・江川家の支配地であり、いざとなれば多摩の名主は江川家の指示で動くのは疑う余地もない。
しかも担庵は、諸外国への備えと称して幕府の許可を得て公然と農兵を組織し、江川塾を通じて親藩も外様も分け隔てなく、日本という統一国家を目指した人材の育成に乗り出した。これによって、全国津々浦々の大小諸藩が挙って英才の育成を江川塾に託した。江川塾に集まった大勢の門人は佐久間象山を始め、薩摩、長州から東北各藩に至るまで日本中の才ある人物の溜まり場でもあった。その誰もが、江川担庵の教えを真摯に学んだ。
担庵はかつて高島秋帆から学んだ火砲術を研究・技術開発し、それを高度化させて外国と戦える兵器と軍隊の整備を目指していた。そのためには近代戦に対応する兵法は勿論、大砲や西洋式銃砲の製造や取扱方法、強力な火薬の開発、救急介護から非常食など近代戦争に必要なあらゆる知識や技術を、誰にでも惜し気なく教えた。このことは、歳三も行く先々で聞く江川塾の噂で知っていた。
「今だから言うが・・・」
荘四郎が酒腕を手にしたまま、歳三の目を覗きこむようにして続けた。
「歳さんを人材探索に使え、と命じられたのも有事に備えてのことだ」
「それが内戦か?」
「初戦は、あちこちの斬り合いから始まる。だからこそ歳さんの出番になる」
「おれは捨て駒か?」
「一兵卒の歩だって、敵陣に入れば金駒となって相手の王を倒す活躍が出来るのだ」
「それもそうだな」
「しかも、歳さんは、武士として登場するのだぞ」
一瞬、歳三は酒椀を手にしたまま荘四郎の顔を見つめた。
3、敵か友か?
暮れなずむ宵が雪明かりで淡い白さを障子に映していた。
師とも仰ぐ担庵の死によって、歳三の役割も変わるのか?
「これも伏せねばならんことだが・・・」
「なんだ?」
「亡き殿の命で、歳さんには秘密裏に海外事情、軍学、砲術など兵法の全てを身につけて頂く」
「誰に教わる?」
「若殿・英敏様、柏木総藏、斎藤新太郎ほか拙者を含めた手代一同だ」
「新太郎って、練兵館の弥九郎さまの後継ぎか?」
「そうだ。新太郎の父上とは面識があったな?」
「弥九郎様とは、本田家で何度も会っている」
「その時、弥九郎様になにか言われなかったか?」
「いずれ、息子の新太郎と共に江川家で働かんか、と」
「その時、おぬしがぬかした台詞を覚えておるか?」
「もう忘れた」
「おれは江川家じゃなく国のために働く、とガキの歳三が言ったそうだぞ」
「生意気だったんだな」
「今でも充分に生意気だ」
「でも今じゃ、そんなこと恥ずかしくて口には出せん」
「いや。今こそ言ってもらわねば困る」
「国のために働く気持ちは、今でも同じだ」
「その意気、それでこそ歳さんだ」
「おだてには乗らん」
「ともあれ、歳さんには組織を動かす近代兵学を短時間で身につけてもらう」
「なぜだ?」
「国のための兵学研修さ。江川塾では伊豆長岡の弥太郎として下働きをしながら学ぶんだ」
「下働きか?」
「講義や研修、砲術の実習など、いつでも勝手に出入り出来るように計らうから、江川塾の全てが学べるぞ」
「知ってるやつに出会ったら」
「この世の中には、自分とそっくりなのが三人いるからと言え。あくまでシラを切れば、誰だって半信半疑ながら、それを信じるさ」
「まさか?」
「現に、わしは身内の伊豆の庄屋まで騙したことがあるぞ」
「おれが江川家に入るのに、なぜ嘘をつかねばならんのだ?」
「理由は簡単だ。いずれ、江川家と歳さんは無縁でなければならなくなるからだ」
「江川家の都合で、おれと関わりたくないのだな?」
「そうだ。だが、歳さんも得る物が多いから悪くはない取り引きだぞ」
「取り引きか?」
「そうだ。武士として活躍の場を与えられたら、どうする?」
「夢のようだな? でも、なにか条件があるんだろ?」
「いや、江川家の修行が終ったら試衛道場に行くだけだ。そこからは自由に羽ばたけばいい」
「それだけで武士になれるのか?」
「その通りだ。歳さんと試衛道場の若師範は兄弟分だったな?」
「そうらしいな」
「だったら一心同体だ。共に武士として活躍することになる」
「いつ?」
「そう焦るな。まずは江川塾で近代兵法や練兵術、砲術、武器弾薬や組織を動かす力を学び、来たるべき時に備えるのだ」
「なぜ、そこまで肩入れしてくれる?」
「江川塾が育てるのは歳さんだけではない。戦いってやつは、敵味方の力が均衡を保つほど面白くなるからな」
「そうか。おれの敵役も江川家が育ててるってことだな?」
「その通りだ」
「ようやく謎が解けて来たぞ。相手はどこの誰か知らんが、敵味方に別れさせて戦わせ、強く逞しい国造りを考えるってことだな?」
「江川家は、そのための武器弾薬、兵法、戦後の処理や行政、外国との対応なども考えて、近代国家の創建に関わるのだ」
「なるほど・・・」
そこで歳三が、ふと疑問を口にした。
「おれの韮山入りが極秘なら、おれは一体、どこにいることになる?」
「大伝馬町のいとう呉服店に話をつけてある。歳さんは番頭見習いで逆戻りした、という段取りだ」
「そんな昔のことまで調べたのか?」
「呉服屋で住み込みで働いていることにしておけば、歳さんの隠密行動は隠せるからな」
「なぜ、呉服屋に?」
「あるじの伝兵衛さんから歳さんのことを聞いたよ」
「悪い評判だな?」
「いや。番頭の磯吉が己を恥じて詫び歳さんの無実が晴れたそうだ。そこで、改めて歳さんを婿に迎えたいと」
「婿にか? とんでもないことだ」
「千代という娘が、歳さんを追いだしたのが誤解と知って、泣き喚いて病に伏して大変だったそうだぞ」
「もう、どうでもいいことだ」
「わしも、歳三は国のために働いてもらうから諦めてくれ、と言ってきた」
「それでいいさ」
そうは言ったが歳三は、千代との別れの辛さ、千代の憂いを湛えた悲しげな顔を忘れてはいなかった。
歳三が江川家の手代見習いとして、江川家邸に顔を出したのは安政二年(一八五五)の春、梅の香る季節だった。
代官への届け出は、江戸大伝馬町の呉服店・伊藤伝兵衛方に再奉公として兄の喜六から村名主経由で岡野荘四郎に提出されている。
その朝辰の刻、歳三は大伝馬町には立ち寄らず、本所南割下水の江川家江戸下屋敷に岡野荘四郎を訪ね、荘四郎の案内で屋敷内に入った。この歳三の行動を知る者は、兄の喜六と佐藤彦五郎・のぶ夫婦、それに江川家の後継者・英敏と手代の主だった者だけだった。
江川家では、以前から父を手伝っていた三男の英敏が後を継ぎ、父を喪った悲しみを抑えて多忙な公務に励み東翻西走、その行動力も能力も父親以上だとの評判で江川家は盤石だった。それもこれも一騎当千・千軍万馬の手代陣があってのことだ、と壮四郎は言った。
荘四郎から「いつもの小間物商姿で」と言われている歳三は、商材入りの風呂敷包に油合羽
「そなたが弥太郎どのか? 江川英敏でござる」
これが、江川英敏の第一声だった、
歳三を迎えに出た岡野荘四郎に連れられて門を潜り、玄関脇の客間で会った瞬間、英敏が先に口を開き、歳三の挨拶が後になった。
「長岡村の弥太郎です。以後、お見知りおきを願います」
歳三より四歳若いと聞いていた英敏は、顔色が蒼く年齢より遥かに老けて見えた。英敏は柔和な顔に似合わぬ鋭い眼光で歳三を見たが、その眼はすぐに穏やかに戻り、周囲に聞こえぬ小声で悪戯っぽく囁いた。
「歳三さん。以前から父に聞いており、待ってましたぞ」
英敏は、すぐ側近らしい若者を呼んだ。
「小五郎さん、すぐ屋敷内にいる番頭さん達を二の客間に集めてください」
集まった代官手代は、多摩にも通うだけに殆どが歳三とは顔見知りで、初対面は数人だけだが、ここでは全員が初対面となっている。
江川英敏が、歳三を紹介した。全員が自分より年長だからか誰に対しても呼び捨てにはしないらしい。
「岡野さんの手の者として働いている小間物屋・長岡村の弥太郎どのです。今日一日ここで過ごし、明日、韮山に向かいます」
形式的ではあるが、荘四郎が重ねて弥太郎を紹介した。
「亡き大殿の慧眼で見出された弥太郎殿は、私の良き協力者として諸国探索に力を発揮して頂いております。また、これからも江川家をよく知って頂いた上で、さらに力を借りることになります。なお、弥太郎どのと私は五分と五分の付き合いです」
英敏が続けて手代衆を紹介した。みな芝居だと分かっていても顔には出さない。お互いに目と目で挨拶を済ませている。
顔見知りの柏木総藏、石井修三、望月大象、岩嶋源三郎、長沢与四郎、根本慎蔵、大山菊五郎、ここからが初対面で、増山健次郎、石川政之進、中浜万次郎、桂小五郎、と続いた。増山健次郎とは、小間物と文書や活動資金のやり取りで縁があり、石川政之進の名は荘四郎から聞いている。
歳三の子供の頃から兄の喜六とも義兄の彦五郎とも親しい筆頭手代の柏木総蔵が、涼しい顔で言った。
「弥太さんとやら、岡野から聞いたが武士になりたいそうだな?」
そんなことは、歳三の子供の頃の口癖だったから百も承知で芝居を打っている。
「こちらの桂小五郎さんは、練兵館の塾長でしてな、大殿が存命中には、斉藤弥九郎の後継者として大殿の付き人となり、伊豆下田にも行きペリー艦隊を実地に見聞し、大殿から直接に西洋兵学や銃砲術、砲台の築造術などを学び、大殿亡き後も、若殿の補佐を勤めている。この桂小五郎さんも出自は武士ではない」
何を言い出すのか、歳三は十一歳ほど年長の割りには老成した柏木総藏の顔を見つめた。
「桂さんは。医者の家に生まれ、武家に養子入りして松陰塾に学び、柳生新陰流と神道無念流を極めた剣術家だが、それ以上に進取の気性に優れた長州藩随一の逸材なのだ。いずれはこの国を背負って立つ男だから、弥太郎さんもとくと見知っておいてくれ」
小五郎にも言った。
「この弥太郎さんは、人の目利きに鋭い大殿が惚れて岡野に付けた男だ。多くは語る機会もなかろうが、暫し仲良くしておくれ」
長身の歳三より更に背が高い小五郎が、余裕のある目で歳三を見て軽く会釈した。
この男が味方なら心強いが敵に回すと手強い相手になる、これが歳三の直感だった。
その瞬間、歳三と小五郎の視線が激しく絡み合って火花を散らしたが、すぐに二人共穏やかな表情に戻っていた。
4、農兵隊構想
江川家手代・岡野壮四郎の協力者・長岡村の弥太郎と名乗った歳三は、江川英敏の付き人でもある練兵館塾頭の桂小五郎の案内で江川家屋敷を隈なく案内されることになった。
「柏木さまから、おぬしとは五分の付き合いで、何でも隠さず見せて説明してやってくれとの指示があった」
「柏木総蔵さまが?」
「おぬしはよっぽど重要な役目を担っているのじゃな?」
歳三には、江川家から自分が何を期待されているのか、それさえ理解できていない。
広い屋敷内のあちこちに人が立ち働いていて、敷地内に建つ数棟の長屋からからも活気に満ちた人の気配があり、外庭にも大工や鳶の衆が大勢立ち働いていて何やら騒がしい。
「何が起こるんです?」
「亡き殿の長年の功績に対して幕閣から、この五月に新たな土地を賜ることになった。その移動のための準備だ」
「どちらへ?」
「昔は銭の鋳造場だった芝の新銭座、新見藩関家の江戸屋敷跡など今年は約六千坪、来年になると東側千坪余にある御書院番桑山鎮之亟屋敷と丹後に領地のある旗本・藤掛出羽守の添屋敷が立ち退いて、そこがまた江川家に下賜されるそうだ」
「そんな広大な土地を何に使う?」
「江川家お屋敷、柏木さまら与力同心の住居、各藩から預かる塾生の寄宿舎、教室長屋、大砲や小銃など銃砲習練場、広場は練兵場になる」
「練兵? どこの軍隊の?」
「多摩の農兵隊だよ。多分、中心になるのは佐藤彦五郎さんだ?」
「まさか? そんな本格的な軍隊なんて」
「農兵を募るには幕府の許可がいる。江川家は韮山と多摩、二か所の農兵訓練を申請して幕府の許可を得ている」
「桂さんも農兵に興味をお持ちで?」
「わが藩も密かに農兵の創設を指示したよ。こっちは無許可だがな」
「藩? どこの藩です?」
「萩藩だ。拙者は長州だよ」
「長州?」
「何で驚く? 江川家執事の我が師・斉藤弥九郎先生は長州藩の剣術指南役だぞ」
「そうでしたか? 農兵の仕組みは誰が考えたんですか?」
「農兵の組織は、亡き殿と弥九郎さまが考え、柏木さまが”隊伍仕法”という仕様に練り上げたものだ」
「桂さんは、何でも知ってるんだな?」
「いずれにせよ新銭座の屋敷と調練場が完成すれば、小規模ながら江川家は軍隊をもち実戦形式で模擬戦を行い、幹部武将の育成が出来る」
「長州藩もそれを?」
「そうだ。練兵館の剣術仲間の高杉という男に創らせる。もう指示も出した。この男なら藩主の許可を得て無敵の農兵隊を創設してくれる」
「桂さんは、何でおれのような者に、そんな大切なことまで話すんで?」
「若殿・英敏さまにも頼まれたからさ」
「何て?」
「知ってることは何でも話してやってくれ、とな。おぬしは亡き殿との関係で岡野さんを手伝ってるんだな?」
「その通りだ」
「ならば、われわれは仲間だ。だったら本当のことを言え。おぬしは多摩者だな?」
「おれは豆州長岡村の弥太郎。これで何か不都合でも?」
「岡野さんは多摩から上州にかけて活動する江川家手代、多摩訛りのおぬしが出自を明かせない理由は?」
桂小五郎がしばし瞑目して目を見開いた時は、すでに謎が解けてスッキリした表情に戻っていた。
「なるほど、わかったぞ!」
「なにが?」
「おぬしが江川家に出入りしたことは一切、日誌に残っても人の記憶に残ってもいかんのだ」
「どういうことだ?」
「おぬしには近代兵法や軍事情報の全てを学んで貰いたいが未来永劫、江川家とは無縁であらねばならんのだ」
「どうして?」
「それは、江川家の都合だろう。多分、おぬしには危険で命がけの大きな歴史的使命が課せられるはずだ」
「今のところ、そのような兆しも気配も全くないのだが?」
「では聞くが、おぬしは韮山が終ったら、つぎは試衛道場へ行くのだな?」
「どうして、それを?」
「多摩の農兵構想は、天然理心流を除いては進まないからだ」
「そこへ行けば、拙者とも会うことになる」
「なぜ?」
「表向きは別々だが、練兵館と試衛道場は江川代官絡みで考えれば兄弟道場だからな」
「稽古も激しいし」
「おや、弥太郎さんはどちらも詳しいんだな?」
「いや。耳学問ですよ」
「どちらにしても、試衛道場で会えば弥太郎さんの正体は知れますからな」
ふと、教場がある長屋の前で小五郎が歩みを止めた。
「どうやら、亡くなった殿の真意が読めてきたぞ」
「どのように?」
「拙者には長州で農兵を作らせ、ご自分は韮山の拠点を守る農兵を鍛え、弥太郎さんには多摩の農兵を任せる」
「まさか?」
「もしかすると、我々は国を強くするための噛ませ犬かも知れんぞ?」
「どういう意味だ?」
「今まで、拙者は師の弥九郎さまや新太郎さまに替わって、江川の殿の側近として房州から相模や伊豆の湾岸防備を見廻り、お台場に大砲を備えて異国の侵略に備え、大量の武器弾薬を作るために骨身を惜しまず働いてきた。殿はそれに備えると見せかけて公然と幕府の許しを得て武士以外の若者に江川塾で作った武器を使っての戦闘訓練を始めようとされている。妙だと思わんか?」
「どこがおかしい?」
「異国が攻めてくるのは海からだ。全国の沿岸各藩が大砲を備えた海防拠点を築いて武士が戦うことになる。なぜ農兵が要る?」
「敵が上陸した時の防衛策として農兵を考えたのじゃないのか?」
「異国の襲来を武力で防ぐ海防策は、海に面した諸国各藩の当面の急務だが、そのために全国各地各藩から選ばれた武士がこの江川塾に集まって砲術や兵法を競い合って学ぶ。その全員が帰藩してそれぞれの藩内で藩士を集めて軍事訓練を行う。それは海防のためだ。小銃で武装した農兵の軍隊が必要なのは、国内の争いに備えてのことじゃないのか?」
「おれには分からん」
「ま。備えあれば憂いなし、というからな」
会話はそこまでだった。
桂小五郎は、壮四郎が歳三に語った通りのことを見抜いている。歳三は、桂に親しみと同時に何か知らぬそら恐ろしさも感じていた
(この男には、世の中の動きが見通せるのかも知れない)
その思いは、桂に案内されて江川屋敷の内外を見まわすと土塁や塀の厚さなどからみても納得がいく。江川屋敷はすでに臨戦態勢なのだ。
江川邸敷地内には何棟もの長屋があって銃砲製作、火薬製造、砲術学習、硬パンと呼ばれる戦場用非常食の製造などが行われていて、服装もお国訛りも異なる大勢の若い武士が教場で学び、屋外で銃砲の訓練に余念がない。それらの講師を務めているのが先刻、歳三と顔合わせをした中浜万次郎や長沢与四郎、根本慎蔵などの手代らで、どの教場も活気に満ちた若い熱気と情熱に溢れていた。
5、韮山の反射炉