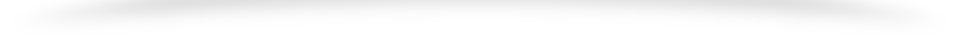1、八寸の勘助
文蔵が疑わしそうな目でお勝を見た。
「それが、どう裏から手がまわったのか長牢のあっしと、後々に捕まった舎弟分の下柘植の浅太の二人だけ、代官様がどういうわけか逃がしてくれやした。だが、お説の通り死罪ということで墓まであって、いまさらどこにも顔を出すことも出来ねえ。しかも、こんど捕まれば、否応なしに獄門でやすからね」
「変だね? わざと逃がしといて、また捕まえて死罪かえ? その板割の浅太って男はどうしたんだね?」
「おや? お勝さんとやら、あっしは板割なんて言ってませんぜ? 板割の浅太郎をご存知ですな?」
「知るもんかね。だから言っただろ。耳年増だって」
「ごく最近になって分かったんだが、あっしと一緒に追放された浅太は、以前、死んだ親分から、足を洗え、と言われて信州佐久の寺宗金台寺の列外(れつがい)和尚への紹介状を貰い、そこに逃げ込んで頭を丸めて寺男に化けた、と聞きやした」
「その浅太も死んだことになってるんだね?」
「浅太もすでに死罪になっていて、下総の寺宗・助崎山乗願寺に立派な墓もあり、あっしと同じくこの世にはいないことになってるんだが、もしも、それがバレてもすでに僧籍に入ったことでお構いなしだそうで……どうも、腑に落ちねえ話なんでね」
「なにが変なの?」
「田部井村の宇右衞門という人は、親分を匿った罪で死罪になったが、聞いた話だと、親分が役人に逮捕される何日か前に、納屋を改造した隠れ家で中風で寝込んでた親分を、信州から坊主が訪ねたそうでやんす」
「坊主がねえ?」
「それまでは、療養中の親分を代官所に密告したのは、看病疲れのお町姐さんか、親分に愛想を尽かした本妻のお鶴さん、美人で若いお町に親分を寝盗られたお徳姐さんじゃねえかって言われてたんだが……」
「ちょっと、文蔵さん。こればかりは聞き捨てならないねえ。その寝盗られたお徳が、親分を役人に売ったっていうのかえ?」
「いや。そうじゃねえんで。その後、どうもこの坊主が怪しいってことになって調べたら、なんとその坊主ってえのが……」
「浅太だったんだね?」
「その通りだ。変だと思わねえですか? でも、関係ねえ人には……」
「いいから、その続きは?」
「いろいろ調べると、怪しいことばかりで」
「どんなことだね?」
「お千賀という娘が納屋にお茶を運んだら、坊主姿の浅太が、足腰も不自由で臥せっていた親分の枕元で泣いて詫びてて、それを看護に付き添ってたお町姐さん……この人が親分の面倒を見てたんですが……」
「お町か? なにも面倒なんか見てないのに……ま、なにを詫びてたんだね?」
「昔、あっしら一家が二日二晩の賭場を開いた時に、誰にも知られてねえはずなのに木っ端役人に襲われて大立ち回りになり、賭場開きと関所破りの罪などで幹部らを含めて十人以上も捕まった、と、ご承知ください。どうにか逃げ延びた親分以下二十人ほどが、仕方なく赤城の山の紫藤洞ってえ岩穴に籠もったんだが、あの捕り物だって誰かが密告しなければ絶対にあり得ないはずでしたからねえ」
「それが浅太だったっていうんだね?」
「いえ、そうじゃねえ。あっしは浅の伯父を疑ったんだ。ちょうど間が悪く、客の接待を任されてた浅の野郎は腹痛だとかで家で臥せってたし、二足の草鞋を履いてて十手持ちだった浅太の伯父の八寸の勘助どんも、いつもなら見回りに来るのに一度も見えなかったんだ……それをあっしは浅のいる前で問いただしたんだ。なぜ、伯父貴は顔を出さねえんだ? てね」
「それは、たしかに怪しいねえ」
「親分は、あの賭場を代官所に知らせたのは、別にいる。浅の伯父の勘助が密告なんて考えたくもねえって言うし、日光の円蔵も、例え二足の草鞋を履こうともあの真っ正直な勘助が恩義のある親分を裏切るなんて、天地神明に誓ってあるはずがねえって言い張って、あっしの意見に耳を貸さなかった」
「じゃあ、あんただけが勘助が怪しいって、言い張ったんだね?」
「あの時、親分と円蔵とあっしのやりとりを黙って聞いてた浅の野郎が、ここで何を言ったって始まらねえ、伯父貴のところに行って直談判して疑いを晴らして来る。こっちが腹を見せれ、ば真っすぐな勘助伯父のことだから必ず真相を打ち明けてくれるはずだ、と言いやがった」
「それで?」
「そこで、円蔵が浅に言ったんだ。もしも、勘助が万が一にも親分を裏切ってたたとしても身内のおめえには首は切れねえだろう。だからって、この文蔵はもっと始末が悪い。はなっから密告は勘助だって決めつけてるからすぐ争いになる。ここはオレが行ってようく話し合ってくる……こう言ったんだ」
「それで?」
「ところが浅が、自分の身内の始末は自分で付けるって言い張って突っ張るから、さすがの円蔵も根負けして、万が一にも勘助が裏切ったら黙って帰って来い。オレか文蔵が、改めてお命頂戴に行くから、と念を押したんだ」
「その時、親分は止めなかったのかい?」
「親分は、ようく話を聞いて来い。万が一にも間違いがあっちゃあならねえからな……こう親分が諭して浅の舎弟分を五、六人、助っ人として付けて山から降ろしたんだが……」
「結局、浅太が勘助を?」
「浅の追求に答えて勘助が言うには、関東取締出役の中山誠一郎に呼び出され、甥が身内がいるからといって関所破りの大罪を犯した悪人を庇うと女房子供も死罪だぞ、と脅されて仕方なく開帳中の賭場の在り処を吐いちまった……大恩ある忠治親分を裏切る気はねえから、すぐ子分を山に走らせて知らせにやったのに、見張りの下っ端が刃物で脅してうちの子分を追い返した。すぐ賭場を畳んで逃げれば騒ぎはなかったんだ。悪いのはそっちだぞって開き直ったそうだ」
「それで?」
「その上に、おまえの親分には世話になったが、もう年貢の納め時でお縄は避けられねえ。おめえも早く足を洗って仲間から抜けろ、と説教され、我慢がならずに口答えしたら、勘助に思いっきり頬を張られ、思わず揉みあいになった。それを離れて見ていた浅の舎弟分らが、浅が殺されると勘違いして、寄ってたかって勘助を惨殺し、泣き叫ぶ幼い太郎吉や義理伯母のお玉さんまでも手にかけ、一家を皆殺しにして山に戻ってきやがった」
「でも、幼い甥っ子は背負ってきたはずだろ?」
「世間の噂では、勘助殺しを命じたのは親分で、浅の野郎は、幼子の太郎吉を背負って戻った来て、親分に盃を返してどっかに姿を隠したことになってるが、実際には勘助の首だけ持ち帰り、加担した舎弟分と一緒に親分から金一両づつの骨折れ賃を貰ってるんだ」
腕組みをして聞いていた政太夫が、納得したように頷いた。
「なるほど、あの悪名高い国定村の忠治郎一味の末路に相応しい話だ……その浅太という男が世にいう板割りの浅太郎ってことか、げに浅ましき話よのう」
「なにも、そこだけ芝居がかって節を付けることないだろ?」
「それにしても芝居なら……涙ながらに討ち取った勘助の首を親分に差し出した浅太郎……浅太郎が連れて来た幼い太郎吉を背にした忠治が刀を抜いて……赤城の山も今宵限り……折しも赤城山の端からまん丸な月が出て……いい場面だがなあ」
「講釈師は黙ってな。あんたなんか、どうせ見たようなウソを語るんだから……」
「それは違う。説経節はな。ウソのような話を本気で語るのだ」
どうやら政太夫は、文蔵の話に興味を持った様子だった。
2、お徳という女
また政太夫が口をはさむ。
「文蔵さんとやら……詰まるところ忠治一家を役人に売ったのは、その勘助だったってことだな?」
「ところが勘助に、親分以下幹部が賭場に集まる時刻を知らせたのは浅だった……」
「その浅太って男がそう言ったのかね?」
「浅は、伯父の勘助に挨拶に来るようにと思って主だった者の集まる時刻を知らせたんだ」
「なるほど?」
「これにはまだ続きがありやして、八州回りの中山誠一郎に脅されて賭場の在り処を喋ってしまった勘助は、すぐに目明かし見習いの若い衆に文を持たせて賭場への捕り物を浅に知らせようとしたが、たまたま浅が腹痛で休んでいて会えなかった上に、挙動を怪しんだ見張り役の山王の民五郎が、その若い衆を殴り倒して追い返したから、手紙は浅にも親分にも届かなかったんだ」
「ならば、伯父の勘助は義理を守ったことになる」
「ともあれ、賭場での大捕り物になって大勢の死者やケガ人を出し、赤城の山に逃げた忠治一家、凶状持ちで手配されての悲惨な羽目になったんだ。それもこれも自分のせいでそうなった……多分、浅は、坊主になって親分にそれを詫びに行った、こう考えでやすが、あっしらにはまだ落とし前がついていやせん」
「それにしても、浅だって、何で何年も過ぎてから詫びる気になったんだろうね?」
お勝の疑問に文蔵が応じた。
「それは浅が、どこかの寺にいて渡世人からの噂か何かで病に倒れた親分のことを聞いて、生きてる間に詫びておく気になった……とも解釈できるが、その坊主姿の浅が見舞いに来てから、わずか五日もしねえうちに捕り手がその田部井村の納屋を襲って、親分やお町姐さん、隠れ家を貸した大家の宇右衞門宅をしょっ引いたんだ。妙な話だとは思いやせんか?」
「だからって、その浅太が密告したとは限らないだろ?」
「あっしは浅の仕業と睨んでるんですがねえ。それにしても浅の野郎め、てめえだって何人もの命を奪った凶状持ちのくせに、あろうことかぬくぬくと寺守として生きてるなんて……」
「でも、お前さんだって、昔の舎弟分が無事でよかったと思ってるんだろ?」
「とんでもねえ。あいつは親分を売った男だ。絶対に生かしてはおけねえ」
「どうしても、親分の捕縛は浅太の手引きだって言うのかえ?」
「それ以外に思い当たる節はありやせんからね。浅は、これだけ仲間をコケにしておいて自分だけいい思いしようとは、とても許す訳にはいかねえんだ」
「その浅太のことは探してみたの?」
「親分の仇をと思って佐久まで行ったが、どこで知ったかあっしが行く寸前に雲隠れして行方知れず。もっと早く田部井村のお千賀からこの話を聞いてれば、とっくに浅を叩き切ってたんだが」
「お前さんは、その浅太って男をまだ執念深くどこまでも追うつもりかえ?」
お勝の問いに文蔵の目が光った。
「痩せても枯れても三ツ木の文蔵、そう簡単に目指した獲物は逃がしはしねえ。実のところは浅の野郎が、この界隈に逃げ込んでるのは佐久の貧乏寺の坊主を締め上げて吐かせてるんでね。多分、死んだ親分よりも先に浅と顔なじみだったというお徳姐さんが、浅の居場所を知ってるか、あるいは匿ってるんじゃあねえかって、あっしは睨んでるんですがねえ」
「ほう、そのお徳って女だって捕まったんだろ?」
「親分を匿った罪で、お町姐さんや、本妻のお鶴さん同様に唐丸籠に詰められて、罪滅ぼしに小銭を蒔きながら江戸に送られて調べられた後、監視付きの押し込めになったが、いつの間にか姿を晦まして……芸者上がりのお徳姐さんのことだから、唄でも三味でも教えて暮らせるぐらいの腕はある。だから、どこへ行ったって暮らしに困るわけでもねえ。だから、忠治一家の生き残りは、誰もが、このお徳姐さんを慕っていた。だから、浅太が陰で面倒を見てもらっていたって変じゃねえって理屈ですぜ……」
「それは妙な言いがかりだねえ」
「どこが妙なんです?」
「だって考えてもごらん。聞いた話だけど、そのお徳という女が親分に世話になる前に、浅太も文蔵も、とっくに死罪になってるんだよ。生きてたとしても接点はないじゃないか」
「そう来ると思いやした。お勝さんとやら、あんたはとんだ思い違いをされてますぜ。一家の者でお徳姐さんを知らねえヤツはいねえはず……そりゃあ、確かに親分が正式にお徳さんを囲う前に浅太もあっしも縛につきやしたが、その前からあっしらは顔なじみですぜ」
「どういうわけで?」
「親分が囲う五、六年も前から、各地の親分や堅気の衆など客の接待に親分がきまって座敷に呼んだのが赤堀のお徳さん……上州芸者の看板みてえな鉄火場女だったが、あの頃は水もしたたるいい女だった。それに惚れて、渡世の男なら一度や二度は座敷に呼んで酒を注がせて、端唄の一つも聞きたいものですぜ。しかもお徳、いやお徳姐さんは大金を積んでも誰にも肌を許さねえ」
「ほう、文蔵さんも金を積んだかね?」
「あっしもだが、浅の野郎ときたら目が血走って見てられねえ。親分に気つかれたら大ごとだから、気を使ったもんですぜ。それにしてもお徳姐さんが謡うご禁制の女浄瑠璃は天下一品、浅なんぞ一言一句そらんじていやがった……あんたには関係ねえ話だが、女としての色気じゃあ、お町さんには敵わねえが、お徳姐さんってえお人は、昔から気っぷがよくて男好きのするいい女だ……これは親分だけが知らねえだけで、子分の間じゃあ誰一人として惚れねえヤツはいなかった。と、すれば浅太と親しくっても可笑しくはねえ」
「そうかしらねえ? お町には色気で負けてたってえのが……いえ、あたしには縁のない話だがね」
「ましてや浅は気立ての優しいいい男だ。親分よりず-っと前からお徳姐さんと深い仲だったって聞いても驚きやしませんぜ」
「文蔵さん。あんた、お徳さんと浅太の仲を妬いてるのかえ?」
「バカにしねえでくだせえ。それほどではありやせん」
「だとしたら、忘れてやった方が本人のためじゃないのかね?」
文蔵の口許が歪んだ。
「お勝さん。あんまり上州者を甘く見ねえでくだせえよ」
「どういう意味だね? お前さん、あたしまで脅すのかい?」
「いや、あんたじゃねえ。お徳姐さんだ。いずれは浅をとっ捕まえて真相を吐かせ、親分に内緒でお徳姐さんと出来てたら……」
「どうするんだね?」
「親分に成り代わって、二人を叩っ切るのが渡世の道だと承知しておりやす」
「文蔵さん。返り討ちってこともあるからね」
「分かりましてござんす。また、あっしの詰まらぬ話を長々とお聞き頂きやして、これで思い残すことはありやせん」
お勝が名残惜しそうに文蔵を見た。
「いいかい? 亀屋だよ」
「曇ったら道が暗い。お勝、提灯を貸してやれ」
政太夫の好意を文蔵が断った。
「今夜は月が出てましたし、あっしは夜目お効きやすので心配はご無用に」
「文蔵さん、ここまでだ。また表がうるさくなった。体を大事にするんだよ」
「重ね重ねご親切に有り難うござんす。お勝さんも政太夫さんもお達者で、ごめんなすって」
「文蔵もね……」
おもわず呼び捨てにしたお勝を一瞥して、素早く押し入れから天井に潜り込んだ文蔵の足音は、鼠が這うように遠のいて消えた。
ほぼ同時に、表戸が蹴倒され、先刻訪れた捕り手が再び土間になだれ込んだが、二人が落ち着いているのに拍子抜けしたらしい。
「また来たのかい? さっきは家じゅう泥だらけにしやがって」
「やいお勝。あちこち探したが奴の姿はどこにもねえ。押入れに匿ってるんじゃねえのか?」
「だったら押入れから床下まで全部調べておくれ。あ、土足はダメだよ」
政太夫も怒った。
「おまえさん達のおかげで一物が萎えて折角の好機を逃してしまった。残念でならん」
「やかましい! 祭文唸りの愚痴なんか聞いてられるか」
「祭文じゃない、説教節だ」
下っ端役人だが、ここでは頭らしい男がしぶしぶ草鞋を脱いで部屋に上がり、あちこち調べた末、ようやく天井裏に気づいた。
「長屋の両端に逃げ道があるらしい。すぐ追いかけるんだ。お勝、下手な芝居を打ちやがって」
政太夫がぽつりと言った。
「あんたら、善太郎さんには会えるのかい?」
「善太郎? まさか三橋の大親分のことじゃねえだろうな?」
「その善太郎さんに伝えておくれ。あの旅人はこの宿場では悪事は働かねえから構わんでくれ、と説教節が言ったってな」
「何を言いやがる。兄弟分を五人も痛められて黙ってられるか?」
「そいつは親分に聞いてくれ。あんな男を相手にしたらあと十人は傷つくぞ。じゃ、善太郎さんへの伝言を頼みましたぞ」
「なんだ偉そうに。とにかくあいつを捕まえろ」
慌てて捕り手が走り出たが、この時はもう文蔵は遠く離れた月夜の田んぼ道、この男を捕えるのは容易ではなさそうだ。