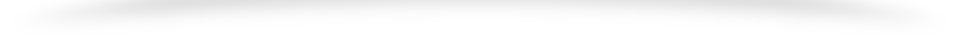1、懺悔
ここでお勝の出番になる。
「ここで政太夫が一息入れる間に、ここ浄光寺ご住職代理の堂守さんから、このお寺を開かれた一遍上人のお話などお聞かせ頂きます」
「坊主の説法を聞きに来たんじゃねえぞ!」
「お勝の浄瑠璃を聞かせろ!」
「お聞かせしたいは山々なれど、お上のご意向で女浄瑠璃はご法度なれば、ご法が変わったその時に、またの機会を楽しみに……」
「勿体ぶるな。二上がりときたら浄瑠璃じゃあねえのか?」
ここで列成が現れて頭を下げる。
「私は寺守の列成(れつじょう)と申します。理由は言えませんが出家する前には大きな罪を犯した者でございます。一遍ご上人の臨終のお言葉には、「わが屍は野に捨て、獣に施すべし」とありますが、わたくしも死後、土に帰して虫を育て草花となるもよしと思う者でございます。この清浄光寺は一般に、踊り念仏で知られる一遍上人の建てたものとされますが、実際には一遍上人は、鎌倉幕府が弱体化し社会不安が広がっていた当時の庶民を救済し、法然さんや親鸞さんが広めた念仏に踊りを加えた新たな宗教を興して各地を転々としていたのです。そのために、寄進する信者にはこと欠かなくても、落ちついて自分のお寺を開くまでには時間的にも余裕がなかったのです。
この清浄光寺は、時宗を開いた一遍上人から数えて四代目の呑海(どんかい)上人が建てたもので、ご承知の通りに遊行寺の名で親しまれているものです。日本一とも言われる黒門を入ってからの石段は、仏様が衆生救済の四十八願に因んだとされる四十八段に築かれてありますので、暇な人は数えてみてください」
「引っ込め、ゴマ擦り坊主。政太夫の語りを聞きに来ただぞ!」
「まあまあ、そう焦らずに……さて、この踊り念仏ですが、これも一遍ご上人が創始者となっていますが、これは間違いです。一遍ご上人がお生まれになる三百年も前の時代に生きた空也上人(九〇三-九七二)が醍醐天皇の御代に世に現したものなのです。一遍上人は、延応元年(一二三九)に松山で河野水軍の家系にお生まれになりましたが、十歳で出家して西山派の浄土宗に入りますが、お父上の死によって一度は環俗します。しかし、兄弟や一族で相続で揉めたことでつくずくと俗世に嫌気がしたとかで再度の出家、文永十一年(一二七四)からは妻子を連れ、念仏を唱えて諸国を行脚しましたが、多くの人と縁を結ぶための布教のために踊り念仏を取り入れたのは、それから五年後の弘安二年(一二七九)からでございます。
一遍ご上人の周囲には多くの人々が集まり、尼僧や僧侶たちが足を踏みならして踊ると群衆はそれを真似て踊り、その機会を利用して僧侶たちが念仏札を配ったのです。この踊り念仏が、盆踊りや歌舞伎に発展し、鎌倉幕府の圧政に抵抗して生まれたという説教節とも結びついて、説話を通じて庶民に仏教の教典や教義を説くようになったと言われます。一遍ご上人のご一行は、踊り念仏や辻説法の舞台を組み立てるための材料や道具を持参して、あちこちで踊り念仏を披露したあとは取り壊して再び次の地を目指したものです。しかし、常に死や滅びを意識していた一遍ご上人は、白装束まで用意してひたすら念仏往生を祈り続けて、さすらいの旅に何かを求め続けたのではないでしょうか?」
「なんだゴマ擦り坊主。ご上人を批判してるのかい?」
「いえ、わたしも一人の求道者として一遍ご上人が求めた自分との戦いの旅に生き、一遍ご上人がめぐり合った、魂の蘇生を自覚させるための説経節との出会いを大切にしたいと願うものです。それでは説経節・政太夫の第二段……ゆるりとお楽しみください」
ここで政太夫が登場した。
政太夫がコホンと一度咳をして、気持ちを落ちつかせてから語り出す。
「天保七年(一八三六)の夏、前年からの飢饉が続き、六十余州の百姓が一揆を起こして世の中が騒然となっていた……。その夏、忠治の兄弟分・信州茅場の兆平が、これも信州の博徒である中野の原七に殺された。その知らせの急飛脚を受けた忠治親分は血相変えて怒り狂い、迷わず即座に言い切った。『飲み分けの兄弟といえば実の身内も同然、この仇を討たねば渡世の義理がすたるわい』、直ちに子分を集めての旅支度、信州目指して旅立った。兄弟分の仕返しにと急いだ忠治一家の総勢十数名の面々は、白昼堂々、槍や弓矢に鉄砲と、御禁制の長刀なども携えて、関所も押し破っての旅立ちは、忠治二十七歳、意気盛んな頃だった」
ベベベーンと三味の音が冴えた秋の夜気を裂いて唸る。
「だが時すでに遅かった。皮肉にも忠治一家が到着した時は、中野の原七は賭博の罪で逮捕され、原七一家は壊滅状態、忠治一家に歯向かう者はただの一人もいなかった。この時の、二度目の関所破りが命取り、忠治は天下の大罪人となりにける……」
「赤城山なら名月だ。名月はどうなった!」
夜が深くなると気の短い客には我慢がならないらしい。
「それからの忠治一家と八州回りとの攻防は一進一退で続いたが、天保一三年(一八四二)の秋深く、忠治一家の縄張りの新田郡世良田で開帳中の賭場を襲われ、多くの子分が捕縛されたが、忠治と主立った子飼いの手下は赤城の山に逃げ込んだ……。その時の世良田の賭場には、子分の板割の浅太と、浅太の伯父の勘助がの姿がなかったことから、忠治は勘助の密告を疑った。
『浅、おめえがあの日、腹が痛えと寝込んでたなあ仕方ねえ。だがな、十手を預かる身とはいえ、おめえの伯父の勘助は忠治一家とは縁の切れねえ深え仲だ。忠治一家が賭場を開くとなりゃあ、一度は顔を見せて小銭を張るのが渡世の義理じゃねえのかい。それにしても、誰が役人に刺したのかは知らねえが、賭場が盛り上がったところに手が入った。ここの賭場を知ってるとなれば勘助をおいてはいねえはず。ここは一番、浅、てめえに任せるから、きっと首尾よく始末をつけて来い』、大恩ある親分から謎をかけられた浅太。しばしの思案の末に頭を下げた。『伯父貴は、一度疑われたら言い開きなどしねえのは親分も先刻ご承知の通りだ。だが、あっしも仁義の道は曲げたくねえ。伯父貴を討ったら、必ずに首を洗って持ち帰りやす。だが、その後は山を降りて弔ってやり堅気に戻ろうと思いやす……』、忠治が淋しい顔で浅太を見つめた。忠治としたら、ガキの頃から育てた浅太にまで去られては、という思いがあるから迷うのだ」
ここで「水を一口!」と客に断った政大夫がお勝が差し出す瓢箪から酒を喉を鳴らして流し込み、唇を手で拭って続けた。
「忠治が言った。『なにも勘助を討って来いとは言ってねえ。ただ気になることは白黒つけずにいられねえのがオレの性分、お前にだって分かっていよう。勘助が何か理由があって賭場に顔を出せなかった。手入れとは関係ねえ。こう言い開きしたらそれでいいんだ』、それに応えて浅太郎、『それでも万が一、伯父貴が、世良田での開帳を知らせたのはオレだ、と開き直った場合は、きっと伯父貴の首はあっしが取ってめ選りましょう。その時は?』 重ねての浅太の申し入れにさすがの忠治も根負けし、『その時は仕方がねえ。盃を返して魚売りでも百姓にでも勝手になっちまえ』と、言いながらも未練たらしく言葉を続けた。『だがな、よくよく考えてみると、あの勘助が、間違ってもワシらを裏切るなどあり得ない。やっぱり、浅、ここは気持ちを抑えて、もう少しだけ様子をみようじゃあねえか』『いや、これだけやられて、一家が散り散りになろうってえ緊急の時に、親分とオレとが落とし穴を見逃せば、いずれもっと大きな捕り物で忠治一家は潰される。ここは一番、鬼になっても密告したヤツを見つけるのが先決でがしょう。明日の夜明けに山を降りて伯父貴に会って白黒きっぱりとつけて参りやす』
ならばと忠治は、浅太の舎弟分を四、五人連れてけ、と、ぶっきらぼいうに言い放つ」
ここで一息入れて……
「翌朝、舎弟分を連れて山を降り、麓に住む勘助を訪ねた浅太。舎弟分を外に待たせ、勘助と話し合いを始めたが、忠治に命じられたた浅太
郎が夫を殺しに来た、こう思い込んだ伯母のお玉が、『浅は、伯父伯母を裏卯切るのか!』と叫び、亭主の脇差しを抜き放ち、不意を狙って切りつけた。
まさか伯母がと油断したから浅太は、背後からの白刃を避け損じて左腕に浅手を負った。カッとなって逆上した浅太は、怒りの表情を露にして抜き打ちにお玉の胸を刺して即死させ、返す刀で勘助の肩口を割ったのだ。
さらに、抵抗する伯父の胸を迷いながらもズブリと一刀。悲鳴も上げずに勘助は一瞬もがいただけで即死した。
思わぬお玉の攻撃で逆上して我を忘れた浅太が、あろうことか、母に縋って泣き叫ぶ幼い太郎吉の首を締めて窒息死させ、ふと気づいてから暫くは呆然自失で立ち尽くす。ふと我に返って勘助の首を切り落とすと、舎弟分に命じて裏庭に穴を堀らせ、首のない勘助と目を剥いたお玉、恐怖の表情で息を引き取った太郎吉のの死体を埋め、勘助の首だけを油紙にくるみ、風呂敷で包んで背中に背負い、人目を盗むように宮城村からの赤城の岩屋への登り道を急いだ。
山奥の隠れ家にたどり着いた浅太は、油紙に包んだ勘助の首を差し出して、密告を認めた伯父貴に激しい口調で説教までされ、あまつさえ伯母には腕を切られたので止むなく二人を手にしたと、涙ながらの報告に、さすがの忠治も驚いた。『ところで、勘助夫婦には、太郎吉という幼な子がいたはずだ。そいつはどうした?』、浅太も親分は騙せない。『泣き叫ぶ太郎吉を見てるうちに、両親がいねえ幼な子の哀れさを考えて、無我夢中でつい手を掛けてしまいやした。親分にお願いですが、どうか、あの可愛い太郎吉の首を締めたこの汚れた手を、一思いにスパッと斬り落としてはくれませんか』『なんだと、あの幼い太郎吉をか……お玉だけでも余分なのに、いくらなんでもそいつは許せねえ。浅、おめえの望み通りにその手をすっぱりと斬ってやる。表へ出ろ!』、境川の安五郎が必死で押し止めようとしたが、脇差しの柄を握った親分の勢いに押されて、それ以上は何もできない。灯に浮かぶ浅太郎は顔面蒼白、生気がない。
屋外に出ると、中秋の名月が恐ろしいほどの輝きで皓々と周囲を照らし、風は木々の梢を揺する。忠治は白刃を月の光にかざして深々と嘆息した。『おれは今まで多くの悪事を働いた。だが、赤子と女だけは殺しちゃいねえ。この刀でその手を斬ればこの愛刀が汚れるだけじゃ済まねえで、おれの身体にまで太郎吉の泣く声がまとわり付いて来る。ま、ここは冷静に考え直して、仕出かしたことは仕方がねえ。いつか、おめえとは縁を切らねえと、おれまで奇怪しくなってくるからな』 刀を収めた忠治が、矢立と巻紙を取り出して文を書く。
『浅、よっく聞け……信州の佐久に金台寺という時宗の荒れ寺があって、住職に列外(れつがい)という和尚がいる。そこに紹介状を書いておいてやる。昼日中だと街道筋でたちまちとっ捕まって獄門だから、夜中のうちに山を降り、まっすぐ急いで金大寺に行け。そして、終生、勘助お玉夫婦と太郎吉への供養をしながら人のために役立つ生きかたをしてみろ。どっちにしても、おめえは渡世人には向いてねえ。これからは、もう二度と博徒には戻るんじゃあねえ。この勘助の首は、すぐに八寸に持ちかえって死体と一緒に埋めて来い。あとはワシらが懇ろに弔ってやろうじゃねえか……』 この忠治の言葉に浅太が泣いた」
政太夫が声音を変えてしっとりと。
「涙ながらの浅太郎、『これで、哀れだった伯父伯母と太郎吉の霊も浮かばれやす……親分のお気遣い、重ね重ねに有り難うさんでござんす。あっしをここまで育てていただいたこれまでの御恩は一生忘れはしやせん。これから夜道を走って伯父貴の仮の墓を作って参りやす』、勘助の首を抱えて小屋を出かかった浅太を忠治が呼び止めた。『夜が明けてからだって遅くねえんだぜ』、それに応えて浅太郎、『勘助伯父の首が一緒になれば、伯母や太郎吉も成仏できると思いやす。こうと決まれば早いほどいい。幸いに今宵は満月、獣避け用の松明さえあれば今から八寸までひとっ走り、なんの心配もありやしやせん。では……』 再び油紙に勘助の首を包み直した浅太。風呂敷に包んで背中に背負うと、隠れ家を出て一目散、山路を辿って八寸への道を急いだ。折しも秋風強き中天には青みがかった円月が冴え渡り、松明を手に赤城からの夜道を急ぐ浅太を照らし出す」
ここで一息ついた政太夫。またもやお勝の差し出す瓢箪酒を一気に飲み干すと、お勝の三味線が鋭い音色で鳴り響き、群衆は、しわぶき一つなく、政太夫を見つめている。
2、お徳とお町
政太夫とお勝の三味線が怪しく絡み、政太夫の地声が響く。
「さてと話は飛びにけり……その後、幾度か赤城の山も探索され、麓へ降りての賭場も襲われ、日光の円蔵ら多くの子分が捕縛されては仕方ない。ついに忠治も逃げ場を失い、命の綱の縄張りさえも子分の境川の安五郎に譲って身を隠す。
さて、ここからは忠治の末路……人は最期が決めどころ。それが惨めか美しいかで生きた値打ちが決まるもの……全盛期には一声かければ千人近い助っ人が集結するといわれた上州の侠客・国定村の忠治郎……気力も失せたか、嘉永三年(一八五〇)の初秋のある夜に……田部井村にある妾のお町宅で突然の発作、脳溢血かで半身不随、口もきけず身体は動かず、ついに病に倒れ臥す。
急の知らせで駆けつけた、子分の境川の安五郎とてどうにもできずに、頼りになるのは五目牛に住むお徳姐さん……使いを出して事情を話させ、親分を運び込むから面倒をと頼んだところ、『お町と同じ布団で寝ていての中風発作だよ、それをあたしにとは虫がよすぎる。ここは、あたしの出番じゃないよ……』と、冷たく言って戸をぴしゃり」
「ひでえ女じゃねえか!」
「人でなし。その女、お徳とやらを殺しちまえ!」
三味の手を休めたお勝が凄い形相で、一息つく政太夫を睨む。こんな話は語り合ったこともない。この語りもお勝にとって初めて聞く台詞(せりふ)なのだ。一体全体、この男はそうしてここまで詳しいのか? この男は油断ならない。
それを知ってか知らぬでか、政太夫の声が朗々と続く。
「使いが去ると、お徳が呟いた。『妾宅で病気療養とは世間への聞こえも悪く、お尋ね者ゆえ自宅にも返れず。隠居したとて渡世の頭、と、なれば親しい仲の村名主・宇右衛門以外にはあり得ない。ここならお町宅からも近いから』 お徳は、お町は必ず、忠治の身柄を宇右衛門宅に運び込む……そう読んだ。こうなるとお徳の動きは速かった。お徳は素早く身の回りの物を風呂敷で包むと、肩から斜めにしっかり結び、身支度も早々に、草鞋の緒を締め提灯片手に外に出た。懐中には肌身放さず身に付ける忠治がくれた鐔なし短刀、いざとなったら役人とでも刺し違えて死ぬ覚悟……目指すは伊勢崎田部井村の西野目宇右衛門屋敷。同じ村内のお町宅からの移動だが、あれこれ決めかねる時間があるから二里も離れた五目牛からでも同じ刻限になるだろう。急いで行けば充分間に合う。お徳の勘は的中し、ほぼ同時に到着したから、いきなり病人を運び込まれた上に二人の女が鉢合わせ、あわてふためいたのは宇右衛門だった」
思わずお勝は三味の手を休めて「その通り!」と呟いた。
「当座のお礼にと、お徳は用意した二両を宇右衛門に手渡して離れの納屋をば借り受けて、お町にも手伝わせて塵掃き水拭きで洗い清めた。余分な荷物は二階に片付けて、さっさと仮の住まいに変える。その行動力こそ忠治が惚れた姐御肌、かつては忠治を探索に来た二足の草鞋の十手持ちの頬を張ったこともある。その時の言い分は、『渡世人が役人の真似をして恥ずかしくないのかえ』 そんなお徳がお町に言った。『あんたも忠治の女なら、生涯、この人に操をたてて、今後一切、男を断ちます、と言えるかい?』 思わず知らずにその場の勢いで、『ハイ』と言ったお町、初婚が破れてから忠治の愛人になっていた。だが、その返事の余韻も消えぬ間の忠治の死、この喪が明けぬ間にお徳との約束は守れなかった。お町はさっさと新田の郷士の妾となり、その後も再婚を繰り返して男なしでは居られない奔放な人生を辿るのも、所詮は定めと言うしかない。それにしても浅ましや、忠治の本妻・お鶴さえ、忠治の死後には羽が生えたか軽くなり、再婚の道を選びしは、請われて断りきれぬのか、女の血が騒ぐのか、それは誰にも分からない」
お勝は思わず頭の中で混乱で爪弾く三味の音を止めた。
(この政太夫がここまで忠治の女の葛藤を?)
「嘉永三年(一八五〇)の秋深く、関八州取締り役の捕吏に、さしもの忠治も病床を襲われ捕縛され、江戸送りとなりにけり……やがて、年の瀬も迫った十二月のある日……かつて自分が関所破りで罪になった大戸の関所脇の広場に築かれた竹矢来の中で、一世を風靡した国定村の忠治は二千人に近い群衆に見守られ、定法通りに罪木柱にくくり付けられたが、目隠しを断った。左右の執行人が繰り出した見せ槍の、刃先が眼前で交差するのを顔色一つ変えずに目を見開いて口一文字、恐れる気配も見せずに死を待った。槍の刃先に左右の腋下から肩先へ貫かれること二十数回、これでさしもの忠治も息絶えた……」
ここでお勝は涙を流しながら気を取り直して、政太夫に合わせて力強く三味を鳴らした。
その激しく優雅な三味の音は、忠治に届けと夜空に鳴り響いてこだました。
「たしかに忠治は人を殺した。イカサマ博打で人も騙し、関所も破った……だが、その人生は、兄弟分や身内を守るため、仇討ちや抗争に明け暮れ、天保の飢饉には多くの村人を救ったのだ。いまはすべては幻で享年四十一歳、夢のような一生だった。さて、国定村無宿の忠治郎、その人生は終わりしが……」
しばしの間があり、観客が固唾を呑んで見つめると、三味の音色が変わって政太夫の語りが続く。
「忠治のために人の道を貫き通した女が一人……亭主と死別してからの芸者暮らしで忠治と逢って、それ以降の半生を、忠治以外の男を知らずに生きて行く……忠治死してはや五年、その女の名はお徳……四十そこそこ女の盛り、いまだに忠治を心に抱き、いまもいずこかに生きている。いま忠治のなきがらは、お徳の家の裏に広がる竹藪に、お徳が建てた墓の下、おだやかな眠りについている。いずこの地からか知らねども、姿の見えないお徳から、今でも寺への付け届け、その依頼からその墓に、線香と花の絶え間なし……」
語調が変わってしんみりと。
「忠治と知り合う前につくったお徳の蓄え、その後の稼ぎも情けなや、すべてが忠治のために消えてゆく。手入れの日時が一刻も早く知れるように、一日でも忠治への捕り物が遅れるようにと、十手持ちへの付け届け、博打で負けた子分に小遣い、親分衆との盆暮の付き合いなど、忠治と過ごした四年間に尽くすは博徒の妻のつね。泣き言ひとつ言わずに努めたことは誰もが認めるところなり。忠治死してこの五年、罪人隠しの罪で捕らわれ、押し籠めの裁きなのに姿を消した、お徳の姿は今いずこ……墓石守る寺のほか、いまだに子分の遺族には、盆暮に欠かさず『忠治・代』、その名もしらぬ人からの米代、餅代が届いている。誰知らぬと思う送り主、勢いのある右肩上がりの筆跡は、お徳の見事な筆づかい、子分で知らない者はない……」
ベベベ-ンと三味が鳴ってすすり泣きが聞こえる。その一人は三味線引きのお勝だったが、三味の音にまぎれて誰にも気づかれない。
ここでまた政太夫が語り出す。
「愛する人の代わりになって自分は名乗らず墓石にも『忠治・代』としたお徳、役所の咎めが薄れたら、忠治の両親が眠る国定村の養寿寺に移したい、と、寺にはお徳の書面があって、余生を忠治のために捧げようというお徳の覚悟が偲ばれる……」
三味線が鳴って政太夫が朗々の声を高める。
「忠治の情愛のほとんどを若いお町に奪われて、ただ尽くすだけのお徳だが、草葉の陰に眠る忠治をば、独り占めして揺るぎない」
お勝のすすり泣きが徐々に観衆に気づかれ多少は不審がられるが、殆どの人は感情移入は誰にでもあることと納得して見守っていた。
「そして、お徳もまた、旧家に嫁ぎ苦労の末に、夫に先立たれ、花柳界に身を投げたた薄幸の日々から、忠治に救われ愛された数年間の人生こそが、生きる歓びを知った日々、その追憶をそのままに、おのれは生きて死びとを愛し、思い出の中に生きている。いつかは入る同じ墓……愛する人と眠る日は二人で一人の『同行一人』、いついつまでも忠治と共に……説経節の政太夫、二あがりお勝の力を借りて、お徳も忠治も、いずれ劣らぬ三国一の幸せ者と、遊行寺の庭にと響かせけるは義侠に死せし国定忠治、それを愛した女のお徳……赤城の山に咲いて散ったる物語。今日、お集まりの皆々様に、口から出任せ説経節。お勝の三味線共々に、どうぞ宜しくごひいきに……」
涙が止まらないお勝が、あわてて政太夫に合わせて三味線を鳴らすが拍手と歓声で何も聞こえない。喧騒の中で語りが終わった。
だが、人々がざわめきを残して散り始めた時に事件が起こった。
3、内藤政右衛門
「浅太っ……覚悟は出来てるな!」
突然、躍り出た文蔵が刃物を振るって、先刻、一遍上人の小話をした列成という寺男に切りかかり、寺男もまた近くにあった箒を持って応戦する。それを見た三橋一家の三下が、政大夫の語りの余韻から解き放たれて騒ぎ出す。
「あいつは、さっき、兄貴達を殴った野郎だぜ!」
「でも手出しはするな。三橋の大親分からの厳命だぞ」
「親分に知れなきゃいいだろ? あの生意気な説教坊主も袋叩きにしちゃえ!」
二人の争いに三橋一家や宿場役人まで加わったから堪らない。ご禁制の刃物が寺社内で振り回されては騒ぎは大きくなるだけだ。
「浅太。逃げるのか!」
追う方も逃げる側も、人込みに邪魔されてままならない。肩口に浅手を負った列成が、お勝に駆け寄って叫ぶ。
「お徳姐さん! 文蔵兄いが狂いやがった。危ねえから逃げてくだせえ!」
野次馬も一緒になって騒ぎ出す。
「浅太、文蔵、お徳ってなれば、まるで忠治語りじゃねえか」
「どうせ余興の芝居だろ?」
「なんだか分からんが、おらも思いっきり暴れてみるぞ」
「仏様は壊すなよ。罰が当たるからな」
寺の境内も本堂内も、たちまち取っ組み合いの修羅場となる。
すでに、文蔵も浅太も乱闘の輪に巻き込まれて虫の息だった。
その時、政太夫の本堂を揺るがす大音声が響いた。
「静まれ、静まれ、静まれい。ここをどこだと心得る。おそれ多くも一遍ご上人のおわす清浄光寺なるぞ! わしを誰と心得る」
この大声で気勢を削がれたのか、騒ぎは瞬時にして静まった。
「誰って、ただの説経節の政太夫じゃねえか」
「説経節とは仮の姿、その前歴は、関八州を一手に預かる関東取締出役(しゅつやく)・内藤政右衛門昌和なるぞ!」
「だから何だ? どうせ嘘だろ、政大夫?」
「その通り、大嘘だ」
「なんだ、これも演目か。人を食ったオヤジだな」
それでも、騒ぎはすっかり収まって群衆は大いに満足した表情で引き上げてゆく。
「皆の衆、本日の説経節・政太夫の演目はこれにて終わり! お賽銭を忘れなさるな」
「さっき十文払ったぞ!」
「あれは入場料、これはお布施ですぞ」
お勝が用意した笊(ざる)を持って歩くと、たちまちビタ銭で底が見えなくなり銀粒も見え隠れしている。
政太夫が支度をしてるところに、集金を終えたお勝が近づいた。
「やっぱり、あんたは、お武家さんだったんだね?」
「冗談だよ。ワシはただの説経節・政太夫さ」
「でも……」
群衆に殴られて傷だらけで気絶している文蔵を抱えた列成こと浅太が近寄り、嬉しそうに頭を下げた。
「内藤さま。今日はお見事でした……」
「語りがか?」
「いえ、お裁きがです。文蔵兄いに殴られはしましたが、仲直り出来そうです」
政大夫が気絶している文蔵を見た。
「文蔵もこれで気が済んだろう。起きるまでそこに寝かせておけ」
「なんだね、浅太。この人は本当に内藤さまなのかえ?」
「姐さん。一緒に住んでて名前も知らねえんですかい?」
「知らないねえ。この人だって、あたしのことなんか……」
「知ってるさ、お徳さん」
「へえ。いつから知ってるんだい?」
「昔、上州に出張ったときにお忍び遊びで座敷に何度か呼んだこともある」
「でも、内藤なんて名は?」
「手下の名で遊んでいたからな。当時、金で転ばなかったのはお徳さんだけだったぞ」
「でも、なんでお前さんは、国定村のことにこんなに詳しいんだね?」
「昔、信州佐久に行ったときに、時宗の寺で出会った忠治親分に散々お徳さんのノロケは聞かされたからな」
「やっぱり。元は八州さまの内藤さんだったんだね? だったら、なぜ、浄瑠璃でご法を破ってるわたしを野放しにしてるんだい?」
「もう済んだことだ。わしも忠治親分と会ってるうちに武士が嫌になってな。だから今は政太夫でよいのだ」
浅太郎が今度はお勝に頭を下げた。
「姐さんに話さなかったのは詫びるが、あっしの死罪を救って遊行寺の寺男に入れたのは内藤さまなので」
「二人してあたしを騙したのかい?」
文蔵の意識が戻ったらしく、立ち上がってまた浅太に殴りかかる。
「おっと文蔵。もう止しなさい」
政太夫が腕を捻り上げると、もう力も出し尽くした文蔵は抵抗もできないらしい。
「痛えじゃねえか講釈師……」
「さっき、説経節だって言ったじゃないか」
「痛え。分かった説経節、もう放してくれ」
「分かったらそれでいい。少しいい話をしてやる。そこへ座れ」
「説経節、なにを威張ってるんだ?」
「おまえ達が揉めてる原因について聞かせてやる」
「痩せても枯れても三ツ木の文蔵、説経節に説教されるいわれはないぜ」
「文蔵兄い、命の恩人を見忘れたのか?」
「忘れやしねえ。さっき出会って助けられたばかりだ」
「そうじゃねえ。このお方は元八州回りの内藤政右衛門様だぞ」
「まさか?」
「まさかじゃねえ。本物に間違いねえんだ」
慌てて文蔵が政太夫の顔を覗きこみ、すぐ土下座して額を土に擦り付けた。
「先ほどは髭面とはいえ、命の恩人を見忘れるとは。面目次第もありやせん」
また、お勝が驚いた。
「文蔵、おまえもこの人に救われたのかえ?」
「事情は知りやせんが、死罪を免れた上に路銀を与えられ、夜陰に乗じて放り出されたのは内藤さまの差し金、こう聞いてやす」
「三人とも黙ってわしの話を聞け」
政太夫が先に立って遊行寺の本堂の広間の床に座ると浅太が蝋燭の火を灯し、政太夫が改まった。
「実はな、おまえら二人の命を助けてたのは忠治親分だ。わしは親分から多額の賄賂(まいない)を貰って書類を書き換え、死罪を免じて釈放させた。それで、温厚な浅太だけ寺男に紹介して、粗暴な文蔵は野放しにしたのだ。どうせ文蔵はどこかで人を殺めながらも生きながらえるだろう。あるいは捕まって死罪になるかも知れん。しかし、文蔵はこうしてしぶとく生きていた。今からでも文蔵がその気になれば、この寺に住み着いてもいいぞ。浅太とわしがお上人に頼めば、まず心配はない」
「その気はないからご心配は無用に、それよりも親分を役人に売ったのはやっぱり浅だったのかい?」
これを聞いた浅太が、血相変えて文蔵に掴みかかった。
「もう一度言ってみろ! 兄いだってこればかりは許せねえ!」
政太夫が二人を分けた。
「あいにくだが、どれもこれも違うぞ」
「じゃあ、なんだ?」
「役人が忠治の隠れ家に気づいたのはな。実は、お徳さんの賄賂からなんだ」
二人が思わずお徳を見、お徳は驚いて政太夫を見つめている。
「お徳さんはな、忠治親分を思うあまり、知り合いの役人の何人かに賄賂を掴ませた……あれが逆効果で命取りになったんだ」
「どうしてさ? みんな喜んで受けとってたんだよ」
「わしもそうだった。人間、誰だって欲があるからな。最初は後ろめたくても受け取るが、二度三度となると貰うのが当然となる。だが、貰い過ぎていると、多少は残っている人間の良心がちくちくと痛むことがある。大物はこれを乗り越えるが、小物は自分が嫌になってくる。それで罪滅ぼしに役目を全うしようとして依頼人を裏切り隠し事を表に出してしまう。それで病床の忠治親分は捕縛され死罪になったのだ」
「じゃあ、あたしが親分を売ったことになるのかい?」
「いや。お徳さんは忠治親分の最高の相棒だった。親分はいずれ病死したんだから。あれでよかったんだよ。歴史にも残ったからな」
浅太と文蔵が顔を見合わせ、お互いに納得したように頷いた。
「さあ。明日からどうする? お徳さん」
「あたしは、これからも二上がりのお勝で一稼ぎ……それから上州へ帰って親分の供養でもするかね」
「それでこそお徳さんだ。あんたがここでお勝でいるうちは、わしは今まで通りの政太夫でいくからな」
お徳がさっぱりした表情で告げた。
「今夜は、あたしのオゴリで飲み明かすかい?」
「そいつは宜しゅうござんすな。どこへ行きます?」
文蔵が言った。
「亀屋は? あっしはあの宿ですっかり世話になっちまった。保太郎さんにも今一度会いたいしな」
「ところで、文蔵兄いは、どうやって、あっしの居場所を探し当てたんだい?」
「そんなの容易なことだ。亀屋の保太郎さんが三橋の善太郎に頼んだら、すぐに分かったんだ」
お徳が不審気に聞いた。
「文蔵は、三橋一家の仇じゃなかったのかい?」
「どこをどう嗅ぎ付けたか三橋一家が和解の詫び状と縞木綿の着物に金一封を持って亀屋に現れ、宿にも心付けを置いてきやがった」
「和解? あっちからかい?」
「しかも、詫び状の宛先には、三ツ木村・文蔵様、和解の相手は善太郎本人で、生意気に花押の真似までしてやがる」
お徳が、「そうか、政さんか?」と納得したように呟いた。
文蔵には、何のことか通じない。
「よし。亀屋に行くぞ!」
酒を禁じられている寺男の列成こと浅太が、真っ先に腰を上げ、傷だらけの文蔵も嬉しそうな顔で立ち上がった。
政太夫がお勝の肩を叩いた。
「お勝、今夜の飲み食いの払いはさっきの稼ぎから出していいぞ」
「そんなの当然だろ。財布はあたしが預かってるんだからね」
四人が連れだって亀屋に向かうと、つい先刻の演目を観た地元や旅客が冷やかしの言葉を投げる。
「なんだ、おめえさん達、グルだったのかえ?」
「あの殴り合いは真に迫ってたぜ」
文蔵が怒った。
「てめえらまで、おれを殴ってたじゃねえか!」
お徳が振り向き、笑顔で言葉を投げた。
「次は、もっと激しいのをやるから、必ずおいで」
亀屋の保太郎は一行を歓迎して宴を設け、いつの間にか自分も地酒持参で座に紛れ込み、大いに酔って騒いでいる。
こうして盛り上がった酒宴で秋の夜は更け、藤澤宿の宙天には十三夜の月が冴え冴えと輝いていた。
了
蛇足
板割浅太郎の墓は遊行寺の墓地にあり、勝負強さ詣での受験生、ギャンブラーで線香の絶ゆる間もないと聞く。
また、現代の「説経節・政大夫」(政太夫から改名)は現存、時代を超えて説経節の歴史を継ぎ人間国宝級の弾き語りで人々を魅了している。
さらに、地元の郷土史家で著名な平野雅道氏は、宿場の中心・堂坂の旅籠・亀屋保太郎のご子孫とか?