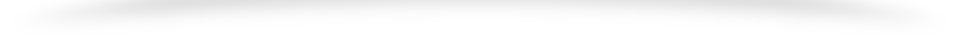1、二上がりのお勝
夕風が肌にひんやりと感じる初秋の夕暮れどきのことだった。
遊行寺(ゆぎょうじ)と呼ばれる藤澤山無量光院・清浄光寺(しょうじょうこうじ)は、時宗の総本山で、その門前町にあたる藤沢宿大鋸(だいきり)橋界隈は、提灯に灯が入るにはまだ少し早い時刻からすでに賑わっていた。この宿泊りの旅客や寺社参詣客は、この時刻から、いい飯盛女のいる宿を狙って宿場入りし、声を掛けてくる女に冷やかしの声を投げ値踏みをしながら歩をゆるめている。
遊行寺から街路樹の落葉散るいろは坂を下り、境川に架かる大鋸橋を渡ると江の島通りにぶつかる。そこから西に続く宿場の街並みがとくに灯りも人も多く大いに賑わっていた。
街並みは本陣・脇本陣に旅籠から木賃宿までを加えた宿泊施設が四十軒以上、飲食、雑貨、衣類、農具や服飾など商いの店や民家などが本道の両側に、合わせて約五百軒ほどが軒を並べて藤沢宿を形成していた。
藤澤宿は江戸日本橋を起点として十里余、品川、川崎、神奈川、程ヶ谷を経て、どこにも恥じない東海道有数の名宿場だった。しかも、この藤澤宿は幕府の直轄領だけに、伊豆韮山の代官・江川家から町を任された名主や案内人の三橋の善太郎としては宿場の治安を守るのが役目の一つで十手を預かる以上は、宿場の治安に使う心痛は並大抵のことではなかった。しかも、藤澤宿は江川家ば筆頭手代の柏木惣藏が直接担当するという異例の対応だけに気は許せない。したがって、宿場には昼も夜も三橋一家の子分達の目がどこかでぢ光っていた。
三橋一家の親分・三橋善太郎の家は宿場の西の見附を守るかたちで真源寺と地並びに名主並の屋敷を構え、つねにこの宿場を通る渡世人や名主から村役人までが出入りして絶えず賑わっていて、その侠客としての名は東海、相模、関東一円に知られていた。
そんな宿場町の雑踏の中を、旅の埃にまみれた無精髭の渡世人が暗い表情で周囲に目配せしながら、高札場のある下久保から大久保への雑踏を油断なく歩いていた。これが、いなせな縦縞の旅合羽に三度笠、男伊達の侠客なら、道の両側の格子戸内からも黄色い声が飛ぶのだが、この男には誰も声をかけない。うす汚れた破れ合羽をまとったその旅人は四十半ばと見え、痩せた髭面の頬に刻まれた不気味な刀傷は、飯盛女達の沈黙を誘い目をそらさせずにはいなかった。額に皺を刻ませ、上目遣いに周囲を見ながら歩く陰険な表情のその男は、十数年余の昔、上州国定村の忠治郎一家の大幹部だった三ツ木の文蔵、またの名を鬼の文蔵と呼ばれていた侠客だった。だが、その零落した風体からは昔の面影など窺い知る由もなく、この男が以前は肩で風を切って北関東一帯に名を馳せた豪気な渡世人だと気づく者もない。だが、それでもなお、その痩せた身体から発散される飢えた狼のような獣の体臭は、いまだに危険な殺気を漂わせていて、歯向かう相手があれば容赦なく斬り合いをするに違いない殺伐とした獣のような体臭は若い時と少しも変わらない。それは、すれ違う遊客や旅人が慌てて避けて通ることからも充分に感じ取れた。その危険な雰囲気は確実に敵を呼ぶ。
ましてや、ここを縄張りに渡世を生きる三橋一家の三下連中としては、こんな男を黙って見逃すわけはいないのは理の当然だ。とりわけ、こんな一目で凶状持ちと分かる男を見逃したのでは、この藤沢宿をはじめ南相模一円を仕切っている三橋の善太郎親分への義理も立たない。
旅慣れた男と見えるこの男は、渡世人の挨拶を知らぬのか、大久保の問屋場に屯して旅人に睨みを利かしている地回りを横目で一瞥しただけで頭半分も下げようとしなかった。これは彼らにとっては腹は立つが好都合だった。これで大っぴらに因縁がつけられる。
人間の貫録差を知らぬ無鉄砲な人間の屑が一人、何の考えもなく飛び出した。
「やい、そこの人。挨拶もできねえ渡世人は人間の屑だぞ!」
人間の屑が人を屑と呼ぶのも変だが、なにしろ多勢に無勢だから、どんな相手であろうと恐れなどない。混雑に紛れてわざと肩をぶつけて因縁をつけ、雑踏の中での争いに持ち込み散々と痛めつけた上で路銀を巻き上げようという魂胆だから身体ごとぶつかった。ところが、文蔵が軽く身を捻って避けたから、たたらを踏んで他の旅人にぶつかって口汚く罵って殴りつけてた。殴ってから相手が違うことに気づき、慌てて文蔵目がけて突っかけて何度か体を交わされてよろめき、ようやく肩が掠ったので居丈高になって喚いた。
「おう、痛えじゃねえか!」
文蔵は無言のまま歩を緩めてゆっくりと歩いていると、悪仲間が走り寄って総勢五人になり勢いがついた。
「なんだ牛、どうした? こいつがどうかしたのかえ?」
「兄貴。このうす汚ねえドブ鼠がよう、オラにぶつかって来やがったんだ」
「鼠が牛に当って来るとはいい度胸じゃねえか。こいつは詫び料ぐらいじゃ済まねえな」
「おい、ここは十手を預かる三橋一家の縄張りだ。でかい面はさせねえぞ!」
極めて人相の悪い地回り五人が、このうす汚い男をとり囲み、懐からとり出した匕首(あいくち)をチラつかせて凄味を効かせると、次々に集まって来る野次馬の群れが遠巻きにして成り行きを見守っている。髭面の文蔵が、ゆっくりとうす汚れた道中合羽の紐を解いて身体から外して左手に持つと、身構えるでもなく表情も変えずに暗い顔で立っている。
「やい! てめえ、詫びるのか詫びねえのかどっちなんだ?」
「聞こえねえのかこの野郎、これでも食らえ!」
十手持ちを口にはするが、十手は三橋家の神棚にあって、三下などは見たこともない。十手代わりの匕首で五人の三下が文蔵に躍りかかったが、道中合羽を振り回されて蹴飛ばされ殴られて、乱闘で痛めつけられたのは地回りの五人の側だった。一人は手刀で首を打たれ、二人は脇腹や急所に蹴りを入れられてうずくまり、一人はねじ上げられた腕が折れてのたうち回り、一人は叩きのめされて通りの真ん中に臥せって通行人の邪魔になる。彼らは元来が藤沢宿の寄生虫で、野次馬の誰もが憎んでいるから間違っても同情などしない。野次馬が怒鳴った。
「三橋一家の助っ人が来るぞ」
「役人も一緒だ!」
「早く逃げろ!」
群衆が騒ぐまでもなく、文蔵も役人との騒ぎは好まないから、とっさに体が反応して逃げ道を探した。
助っ人と聞いて、殴り倒されて地べたで呻いていた地まわり五人組もふらつきながらも落ちている匕首を拾って立ち上がり、虚勢を張って文蔵から距離をおいてよたよたと追いてかける。前からは宿場役人と三橋一家の助っ人、背後からは息を吹き返した五人組……文蔵が野次馬の叫びに反応し、人波をかき分けて逃げようとすると、野次馬の一部が退路を開いた。
弱いもの苛めの三橋一家と結託して、甘い汁を啜っている宿場役人や町のダニに味方する民衆などいるはずもない。男が叫んだ。
「こっちだ、おらに付いて来い。早く脇本陣裏に逃げ込め!」
男を追って脇本陣の裏に走ると、狭い道が入り組んで東西に延びている。
「この裏道を西に走ると常光寺という大きな寺にぶつかる。その裏の路地に逃げ込めば何とかなるからな」
「恩にきます」
文蔵は路地を抜けて走ったが、途中で道がなくなり田のあぜ道を走ったりしているうちに発見されて追われた。
ようやく辿り着いた常光寺の塀に沿って走ると細い路地があり、その先は行き止まりらしく、退路を断たれれば袋の鼠で逃げ道はない。
「そっちへ逃げたぞ!」
「あっちへ回って逃げ口を塞げ!」
追手の声が前後左右から重なって迫って来る。
その時、文蔵を追って路地まで走り込んで来た女が叫んだ。
「その長屋の右側三軒目、そこに飛び込むんだよ!」
振り向いた文蔵が、裾を乱して素足で追って来た艶っぽい女を見て驚く。
「まさか……お徳姐さんかい?」
女は荒い息を吐きながら平然と言った。
「人違いだろ。あたしの名はお勝だよ」
「済いやせん。あまりにも似てるもんで」
「いいから、その家だよ!」
お勝が先に走って、今にも潰れそうな五軒長屋の三軒目の引き戸をガタビシと開くと男を突き入れて自分も飛び込み、すぐに戸を閉めて心張り棒を噛ませて部屋の中を見た。その視線の先には三味線を抱えた図体の大きな髭面の男が、着流し姿で正座して何やら浄瑠璃のような抑揚で「小栗判官」の一節などを、声を抑えて語りながら弦を弾いている。
「……閻魔大王の自筆の文をば眺めたご上人、『あら有り難やの御ん事や』と、書き添えなさる。その書き添えのお言葉とは、『この者を、一引き引いたは……』、なんだ……お勝、その男は?」
部屋に駆け上がった女がビシっと告げた。
「政さん。この男をちょっとだけ匿うからね!」
政と呼ばれた三味線語りの男は、聞こえたのか聞こえないのか、面白くなさそうに少し頭を上下に動かしただけで語りを続けた。
「その上でご上人は、餓鬼阿弥を乗せし土車の、手縄をば引きたもうて、『えいさらえい』とばかりにお引きある……」
すでに、追手の叫び声が路地裏にまでも入り込んで来ている。
女がボロ雑巾を出して男に渡す。
「濯ぎなしで足を拭いたら、その雑巾にわらじをくるんで、そこの押し入れに入っておとなしくしてな」
女は素早く押し入れから布団を引き出し、男をその空き間に押し込んで戸を閉めると、破れ畳の上に布団を敷いた。さらに、帯を解き着物も襦袢も脱ぎ捨てて素っ裸で横たわり、三味線語りの男を招いた。
「すぐに役人が来るから、はやく政さんも裸になって此処へおいで」
三味線語りの男が、驚いたように目を大きく見開いた。
「いいのか? いままで拒んでたのに……」
「なんだよ。その目は? 本番じゃない、芝居だよ」
「ちぇ、くそ面白くもねえ」
男が三味線を置き、着物を脱ぎ捨て越中褌もとって布団に身を入れる。
2、三ッ木の文蔵
男がすかさず手を伸ばしてきた。
「お勝、お前さんは意外にまだ身体は若いんだなあ?」
「だめだよ。そこを触っちゃ……そこはもう生涯、店じまいにしたんだからね」
「誰に義理立てするのかは知らんが、勿体ねえ話だな」
「そんなのは、あたしの勝手だろ」
屋外に人声がして、激しく戸が揺すられる。
「二上がりのお勝。ここを開けろ! いるのは分かってるんだ」
「やかましいな、誰だえ?」
「お調べだ。誰か逃げ込まなかったか?」
今度はお勝が怒鳴った。
「いま、お仕事中だからちょっとだけ待ってくれないかえ」
「うるせえ! 開けなきゃあ、ぶっ壊っしちゃうぞ」
体当たりで内側に倒れた板戸を踏んで三橋一家の三下がなだれ込んで来たが、破れ障子の隙間から裸の二人がまる見えだから間が悪そうに立ち止まった。
「明るいうちからいちゃつきやがって……連れ込んだのは今度は誰だ?」
面白がって汚れ草鞋のまま上がり込んだ捕り手数人が布団を剥いで二人を覗き、呆れた表情で顔を見合わせた。
「なんだ、辻説法の政太夫じゃねえか、お勝のヒモじゃ面白くもねえ」
「お勝は色白で、いい体してるじゃねえか」
「政太夫、しっかりやってやれ」
「おれが代わってもいいぞ」
肌を見られたお勝が、あわてて布団を被って怒鳴った。
「人の家に土足で上がりやがって! 無粋な連中だね。さっさと戸を閉めて消えちまいな」
「いい加減にしやがれ。それより、お勝。おめえ、女には御法度の浄瑠璃を語って稼いでるって噂だが本当か?」
「あれは新内だよ……これからは、鳥目を払ってしっかりと聞くんだね」
「うるせえ。てめえの新内なんか聞きたくもねえや、浄瑠璃だから小銭を払ってるんじゃねえか」
「あら、お前さんもお客かえ? それは嬉しいね」
「やかましい! 辻説法やと勝手につるんでろ!」
三橋一家の下っぱを努めるトビや佐官の若い連中までが、あきれ顔で戸の建て付けを直して立ち去ると、お勝が素早く身繕いして戸口に立ち、また心張り棒で戸締りをしてから部屋に戻って掛け布団を剥いだ。
「政さん。いい加減におし。いつまで寝てるんだよ」
「なんだ、これで終わりか? ふぐりが起きてるんだぞ」
「そんなの知るかい。あたしは芝居だって言ったはずだよ」
「男にとっちゃ、酷な話だなあ」
「うちへ帰れば、古女房が鼻を鳴らして待ってるんだろ?」
「だから、いまはお産で実家に帰ってるって言っただろ」
「その間、仕事の相棒の家に居候かい? 虫のいい話だねえ」
「ここで一緒に仕事の打ち合せが出来て、かえって都合がいいじゃないか」
「ふん、自分の都合じゃないか。さ、そろそろ飯にして仕事に出るんだから、起きな!」
「お勝、おめえという女は、よっぽど人使いの荒い女だな」
「居候のくせにでかい口叩くんじゃないよ。嫌なら、いつでも出てっていいんだよ」
辻説法の先生で通っている説経節の政太夫が、渋々と身を起こして褌を締め直すと、背後に立ったお勝が政太夫の背後から一重の衣装を肩に掛け、帯を手渡した。
「ま、仕事で少し稼いだら茶屋にでも行っておいで」
「稼いだらか? それよりな、お勝」
「なんだね?」
「そこの押し入れにいるのは、何処のどいつなんだ?」
「そんなの知るもんか。困ってたから助けただけじゃないか。気になるのかい?」
「まさか、凶状持ちじゃねえだろうな?」
「だったらどうなんだね?」
「冗談じゃねえ。下手に凶状持ちを匿えば死罪だぞ」
「そんなの覚悟の上さ」
その時、押し入れの戸がガタビシと開き、出て来た男がボロ畳に手をついて頭を下げた。
「お二人さん、お助け頂き有り難うござんす。このご恩は生涯わすれやしやせん」
「何のこれしきのこと。困った時はお互い様、気にしなさんな」
「そうはいきません。すぐお暇しやすが、その前に一言お礼を。手前、生国と発しまするは上州三ツ木村の……」
「仁義なんかいいから、もう少しの間おとなしく隠れてな。あの連中は、一通り家捜しをしたら必ずもう一度、あたしらの留守中におまえを探しに来るからね。あんたが凶状持ちかどうかは知らないけど、その押し入れから天井裏に上って長屋の東端まで抜ければ板壁が剥がせるように細工してある。これは長屋衆の知恵だ。そこから飛び降りて裏道を左に逃げれば鎌倉道に出るからね」
「ご親切に有難うござんす。あっしはこの宿で人探しをしやす。どこか泊まれる宿の算段はございやせんか?」
「今夜は宿改めが厳しいからね。そうだ、亀屋がいい」
「心当たりが?」
「亀屋の保太郎さんなら仁義の厚い人だから、宿改めも隠し部屋で匿ってくれる。二上りお勝の紹介だと言ってごらん」
「場所は?」
「この裏を東にゆくと田んぼの中に慈眼寺という小さな寺があるからね。そこの細い道を北に進むと亀屋だからね」
「そこに行ってみます。それにしても、こんな見知らぬ土地でお世話ななるのも何かの縁、ちとお聞きしやすが」
「言ってみな?」
「これには、あっしの身の上が関わるんでござんすが……」
お勝を見た男が念を押す。
「なんだね、その目は? あんたとは初対面なんだから。人に聞かれてまずいことは言わないもんだよ。壁に耳ありっていうからね」
「お勝さんとやら、あんたが、あまりにも、あっしの知ってる人に似ていなさるもので。お徳姐さんと言うんだが……」
「人違いだよ。でも、そのお徳さんには心当たりはないけど、このお勝も、ここにいる祭文唸りの政太夫さんも、悪い人じゃあないから安心していいんだよ」
「おい、お勝。おれのは祭文じゃない、説教節だぞ」
「そんなのどうでもいいじゃないか」
「よくない。祭文は薩摩派で、説教節は若松派の……」
「うるさいねえ。それより、話って何だい?」
「では話しやす。故あってすでに死罪でこの世を去った親分の名は伏せやすが……」
「バカだね。上州で死罪になった親分なんて、誰だって知ってるじゃないか」
「ともあれ、あっしは上州三ッ木生まれの文蔵というケチな野郎でござんす」
「ちょっと待って……」
「なんでござんす?」
「あたしには縁のない話だけど……聞いた話だと、三ッ木の文蔵ってえ人は、その親分が捕まるずうっと前の天保十一年の春に、世良田の博打場で役人の謀略に引っ掛かって捕まり、江戸送りとなって、小塚っ原で獄門死罪になったんじゃなかったのかえ?」
「なんで、そんなことを?」
「あちこち旅をしてれば、耳年増になるからね」
「そうでやしたか。それがこの通り、三ツ木の文蔵は生きているのでござんす」
「それにしても三ッ木の文蔵なんて……あたしがね。十五年もの昔に座敷に出ていた頃、浄瑠璃の仲間から上州の戯れ唄でこんなのを聞いたことがあるんだよ」
立ち上がったお勝が自分の三味線を取り出し、座りなおして音曲を入れて口ずさむ。
「三ッ木には、もったいないのが二つある。稲荷の森に、お安が器量……」
髭面の政大夫が、文蔵をしみじみと見て首を捻る。
「聞いたことないが、そいつは何だね?」
「三ッ木で歌われてるざれ唄だよ。ここで有名なのはね。稲荷の森にある村の鎮守さま、それと、文蔵の嫁のお安さん。器量がいい上に弁が立って、どんな相手も言い負かすそうだが、文蔵がはりつけで死んでから、立派な文蔵さんの墓を立てたそうだよ。三ッ木の文蔵はやっぱり死んだんだろ? あんたは幽霊かい?」
「とんでもねえ。足もありますぜ」
文蔵が手を振って立ち上がり、脚絆を巻いたままの汚い足を見せた。