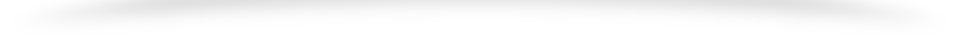一.群盗
「太兵衛どん! まだ遠いが、獲物が二っつばかり見えたぞ!」
雨風に揺れる欅の枝に跨がって物見をしていた雑兵姿の五助が叫ぶと、原生林の中から野伏の頭領、むささびの太兵衛の重い声が響く。
「みな、はよう隠れろ。五助もじゃ!」
五助と呼ばれた小男が樹林に飛び下りて、仲間の背後に身を潜めた。
ここ数日鬱々とした雨の日が続いていたが、その雨足より速く元弘三年(1333年)五月二十二日に鎌倉陥ちるの報は、すでにこの山深い甲斐路にも伝わっていた。噂では、執権高時を始めとする北条一族郎党数百人が寺に火を放って自害して果てたとも聞く。
甲斐から諏訪に続く信州往還の牧原から大武川沿いに本街道から離れて西の山に入った原生林沿いの曲がりくねった山深い間道は、密生する新緑の枝葉や雑草にすっぽりと覆われ昼日中でも暗い。ましてや風と雨に叩かれた遅い午後ともなると間道を覆う樹木の枝葉に視界もさえぎられ、まるで夕闇状態になっていた。
この辺りには日陰の三寸道などと呼ばれる獣道とも見間違える裏道も多く、日頃は人目を避ける凶状持ちか杣人(そまびと)か、猪や鹿などの獣以外には通らない。それが、鎌倉滅亡という噂が村々を駆けめぐると同時に、これらの間道には落武者の兜鎧や刀剣や着衣を狙って近隣の郷士や百姓が誘い合わせ、飢えた狼のように集まってくる。
戦いに破れた信濃武士が刀槍を杖に、次から次によろめきながら故郷をさして落ち行くのを甲斐人が襲う。誰一人として街道を通らずに裏道を通るのは、破れた者の心情からして当然かも知れない。だからこそ、落人狩りの群盗も裏道に網を張り獲物を狙う。鎌倉から地方に通じるどの道筋にも、落人狩りに狂奔する山賎(やまがつ)や郷士と百姓で形成する野伏の集団が、思い思いの武具に身を固め声を潜めて待ち伏せ、容赦なく落武者をなぶり殺しにして着衣や武具を奪う。それは戦乱の世の倣いでもあり、戦いに破れた将兵が無事に命を全うして故郷に落ち延びるのは極めて希有なことであった。
鎌倉陥落後七日もすると、飢えと疲労で戦い続けた不眠不休の飢えた落武者らも、たとえ、追討の兵から逃れても、道筋に群がって次々に襲う飢えた狼のような群盗の凶刃に倒されて、この甲斐の地にまで命を全うして逃げ延びるのは至難を極め、武者の数もめっきりと減少している。だからこそ、野伏側から見れば獲物の希少価値が高くなるのだ。
「今日あたりまで生き延びたってことは、手ごわい相手だぞ!」
左頬と額に刀傷のある醜悪な面貌の頭領の太兵衛が、山道を包む樹林の陰に伏せたまま低く太い地声で周囲に告げた。
飛ぶように足が早いことから「むささび」と呼ばれる四十半ばの太兵衛という男は、信州茅野谷の郷士出身で、かつては信濃源氏の足軽として幾多の戦場を馳せ、その真偽のほどは知る由もないが十数人もの敵を倒したというのが自慢の種だった。その太兵衛は何らかの理由で村を出て、流浪の末にこの甲斐駒の麓の山里にたどり着き、大武川の丸太橋を渡り損ねて溺れかけた村の娘を救ったことから村人の一員として迎えられ、その女を娶って所帯を持ち子をなしていた。太兵衛は村を出た経緯を誰にも語ろうとしない。
最近になって、この村の木賃宿に泊まった旅人が茅野谷で起きた太兵衛が主人公らしい事件を宿の主人に語ったことで、太兵衛の過去が明るみに出た。
それによると、戦場から村に帰った太兵衛が、妻が彼の留守中に姦通していたのを知って、妻と相手の村人を殺害して村を去ったという。その噂はまたたく間に村中に広がったが、太兵衛を見る周囲の目は、女房を寝取られた気の毒な男と、単なる凶状持ちという恐怖の入り混じった見方で評価は割れていた。
それでも、太兵衛が落人狩りで見せた駆け引きの巧さや、凶暴な戦い振りから察してみても、かなり戦場の場数を踏んでいるのは間違いないと思われる。しかも、最初の獲物の分け前は庄屋にも届けてあるから、この落人狩りは村から公認されたも同然で、選ばれた十人余の村人も、それぞれが腕や度胸を認められている命知らずの暴れ者ばかりだった。彼らの武器は竹槍と刀だが太兵衛だけは本物の槍を抱えている。その上に、猪撃ちの猟師が二人ほど参加していて、鉄砲も二丁あるのがかなり役立っていた。
太兵衛の背後に平和時であれば、野良仕事や木樵など山仕事などでおだやかに暮らしているごくふつうの村人が、武器を手に目をぎらつかせ殺気立って身を震わせている。その一人が声を震わせ遠慮がちに口を開いた。
「太兵衛どんは昨日、甲冑と大小独り占めにしたが、オラたちには、ろくな物もありゃあしねえ……」
髭づらの甚兵衛という男が不服顔で口を尖らして続ける。
「オラの分け前は、汚ねえ下帯一枚だった……」
他の者も続けた。
「刀が欲しいのに……」
「やかましい!」
むささびの太兵衛が闇の中で振り向いた。
「お宝を稼ぎてえなら、それなりの働きをしろ! 林に隠れて一度も戦わねえのヤツには分け前はねえんだ。え、甚兵衛、どうなんだ?」
「昨日は急に腹が痛くなった……」
「その前の日は?」
「それが……足が動かねえで」
「落ち武者が怖えなら、とっとと帰れ!」
「それが……カカアに、稼いで来いとせつかれてな」
「情けねえ野郎だな。今日の獲物は山分けだぞ。必死に働け」
「山分け? 本当にいいのか?」
「オレは高見の見物だ、オメエたちで戦って恨みっこなしの山分けにしろ!」
小男の五助が濡れた笠を傾け「シッ」と仲間を制した。耳を澄ませると、風雨が樹木を揺する音に混じって、かすかに枝葉を分ける音が近付いて来る。
「ほれ、近づいて来たぞ。さあ、みんなで好きにやれ!」
太兵衛がキッパリと告げると、甚兵衛が震え声で取りなした。
「でもな、何度も戦さに出て兵法を知ってる太兵衛どんが高見の見物じゃあ、わしらが殺られちゃう。今日も任せるだから太兵衛どん、機嫌なおして采配を振ってくれや」
「そうだ。太兵衛どんの働きで誰一人として命を落としてねえだからな」
「じゃあ、取り分でギャアギャア言わねえな?」
全員が「ああ……」と小声で承諾すると、太兵衛がすかさず告げた。
「オレは太刀一振りでいい。あとは山分けにしな」
各地の落人狩りを網をくぐり抜けて甲州の山中にまで生き長らえるのは、それなりの武将とみて太兵衛は太刀を狙ったのだ。それ以外には興味もない。
「相手は二人、こちらは十二人、万が一にも負ける気遣いはねえ。手筈通りに甚兵衛は太郎吉を連れて下へ行き二人をやり過ごし背後から逃げ道を塞ぐ……五助は、弓組の二人と一緒だぞ。あとの六人はオレに続いて二人を囲んでなぶり殺しにする。手におえなきゃオレの合図でみんな山に散って、あとは弓組に任せるんだ!」
太兵衛は笠の顎緒を締め直し、配置につく仲間を見まわした。
雨滴が雨除けの蓑を通して身体に滲みるのもあってか、誰もが顔色を変え歯の根が合わない様子で震え、仲間内の会話でも声が上づっている。
「五日も続けてるにまだ恐えのか。たった二人をやっつけるのにガタガタするねえ」
すでに、太兵衛を頭としての出撃は、ここ五日ほどで数十回を越えていた。
太兵衛は槍の柄にしごきを入れ、藪の裏側から目を光らせて仲間を叱咤した。もう、緊張するほどの相手などいないという自信が余裕を生んでいた。
当初こそ元気で手強い相手の抵抗を受けて手こずったこともあるが、この二三日は深手を負った死闘に疲れた武士や、いきなり土下座して命乞いする落武者などばかりで、中には途中で略奪にあってか下帯だけの男もいて歯ごたえがない。ここまで逃げ延びて来た男たちも、さしたる抵抗もせずに袋叩きにされて死んでいる。稀に、具足を奪われる前に自ら谷底に飛び込んで命を絶ち太兵衛らを落胆させた者もいるし、太兵衛らの姿を見たとたん山道に座りこみ刃の欠けた刀で自らの腹を刺し七転八倒の末に竹槍で刺されて息絶えた者もいたが、あらかたの武士は多少の抵抗を試みた後でなぶり殺しにされて着衣を剥がれている。身ぐるみ剥がれた落武者の身体は、死んでいようと生きていようと崖まで引きずられて雑木の間から谷底に投げ込まれ、そのまま山犬や禿鷹、烏などの餌食になる。
これまでの戦利品については、まず太兵衛が刀か甲冑をせしめ、金銀は頭割りで等分、その他は着衣、下着に致るまで仲間で順番に分配している。汚れ草鞋をむしり奪った者さえいた。それでもまだ満足する分け前に預かっていない者は、目を血走らせて竹槍を握り締め、つぎの獲物に望みをつないでいた。
太兵衛の兵法が巧みだからか、幸いに仲間からはまだ一人も犠牲者が出ていない。
まず、全員が竹槍で一斉に突き掛かり相手の機先を制し闘志を削ぐ。相手が強く、竹槍を切り払われ反撃された場合は、無理に戦わずすばやく山中に逃げ、弓組が樹の陰から矢を放ち獲物を仕留める。慣れ親しんでいる山中だけに一度逃げ込めば絶対に安全だし、空腹で満身創痍の相手には山中にまで賊を追う気力も体力も残っていないから、この逃げては攻め、攻めては逃げる手はかなり有効だった。自分たちは無傷の上で完璧に獲物を倒すことになる。それでも殺し会いで生きるか死ぬか二者択一の真剣勝負は何回続けても恐ろしいものだった。それだけに生き残ったときの喜びも桁外れに大きいものになる。
獲物の輪郭が雨の中におぼろげに浮かんだ。若者は身体こそ一人前だが、まだ十歳前後としか見えない。その大小二つの人影が背丈ほどもある雑草を分けて近づいて来る。
「なんだ一人はガキじゃねえか?」
樹の陰から首を出して前方を見た太兵衛が、拍子抜けした間抜け声で呟いた。
「あいつら、大分弱ってるな……」
太兵衛の一言で震えていた男達が急に勢いづき、今にも身を乗り出そうとする。
「待て! あせるな。もう少し引きつけてから一気になぶり殺しにするんだ」
降りしきる雨の中を笠も蓑もない大柄な武士がざんばら髪にぼろぼろの袴の裾を引きずり、十歳ほどのまだ幼い若者を労るように気づかいながら歩みを進めていた。
竹槍を構え藪の中に隠れ潜み沸き上がる殺意に身を強張らせた甚兵衛と太郎吉が、樹林の脇を通り過ぎる二人を見送ったとき、大柄な武士の鋭い視線がほんの一瞬だけ二人の隠れている場所を睨んだような気がした。
その瞬間、巧みに隠れているつもりだった甚兵衛と太郎吉が思わず顔を見合わせた。二人の表情に言い知れぬ恐怖と不安が浮かんでいる。その武士からは暗く深い藪の中が見える筈がない。だが、人を殺す寸前の緊張と恐怖の入り交じった獣のような殺気の気配は隠しようもないのか。それとも、生死の境を生き抜く研ぎ澄まされた武士の嗅覚が自分達を襲おうとする野獣の存在を無意識のうちに感知するのか。それとも甚兵衛らの思い過ごしだったのか……。
甚兵衛と太郎吉が恐怖の目で追うと、大柄な武士は傷めた様子の足を重く引きずる他は悠然と何事もなかったかのように雨水を滴らせた無表情な顔で前を見据えて歩いていて、二人の存在など歯牙にもかけていない様子にしか見えない。甚兵衛と太郎吉は安堵の目を見合わせて頷いた。甲冑こそ脱ぎ捨てていたが獲物の着衣や大小は安物ではなさそうだ。仲間内で甚兵衛だけには、ちょうど十歳のガキがいるから都合がいい。家で待つ妻の笑顔が目に浮かび甚兵衛の闘志に再び火が点いた。
太兵衛らが潜んだ藪の手前に差しかかると、大柄な武士が若者の横顔に視線を投げ、若者は顔を動かさずに目で応じた。
「オリャーッ」
太兵衛が槍を繰り出すと、群盗の群れは一斉に二人に襲いかかった。雑兵姿の村人ら数人が竹槍をくり出しながら正面から身を躍らせ、背後から遅れじとばかりに甚兵衛と太郎吉が竹槍を突いて踊りかかる。だが、彼らの計画は無残にも寸時にして消し飛んだ。襲われたはずの二人が意外にも攻勢に転じたのだ。
甲冑も身につけていない大柄な武士が軽く身をひねって刀を振るうと、空を突いて流れた太兵衛槍の柄が手元一尺(約三十センチ)を残して切断され、あわてて逃げた太兵衛の首元を大男の太刀風が追う。逃げ腰の太兵衛を庇うように繰り出した群盗の竹槍はことご
とく寸断され手先一尺を残して地に落ちた。鋭く振るった大男の白刃に、刀を握った雑兵の首が胴体から切り離されて宙を飛ぶ。それを見た太兵衛らが、素早く跳び退さり、二人を遠巻きにして隙を狙う。太兵衛がチラと樹上に潜む弓組を見た。
それを見た大柄な武士が腰を落として地にしゃがみ、切り落とした竹槍を拾うとそのままの態勢から腰を捻って林に向かって投げ入れた。にぶい弦音と悲鳴が響くと木の枝を裂いて胸に竹槍を突き刺した男が一人、地上に墜落して呻く。
それでも気丈にも立ち上がって胸の竹槍を抜こうと手を添えたところに、踏み込んだ大男の太刀が唸りを上げて首を撥ねた。男の頸部から血が噴き出し、その頭部の消えた身体が濡れた雑草の中に音を立てて仰向けに倒れた。それを見た群盗らが戦意を喪失して原生林に逃げ込んだ。しかし、太兵衛だけは違っていた。
血を見た山犬は凶暴になる。修羅場の戦場を駆けめぐった太兵衛にとって血を見ることは何の怖れもない。むしろ闘争心を高める作用に働く。
「みんな出て来い! こいつらは疲れ切ってるんだ。獲物が欲しくねえのか! いま五助が、助っ人を呼びに走ったぞ」
その声で、一度は林に逃げた雑兵姿の村人がへっぴり腰で現れて刀を構える。
太兵衛が雨足をも切り裂く鋭さで刀を振るうと、農兵らが叫び声を上げて続く。
相手が手強いと見ると距離を保ち、包み込んで攻め、反撃されると飛び退る。
二人を失った野伏の群れは戦法を変えた。持久戦に持ち込めば勝てると見たのだ。
「亀寿さま。もう少しの辛抱ですぞ」
「何のこれしき……三郎殿こそ異常はないか?」
亀寿と呼ばれた若者を、大柄な三郎という武士が励ましている。武士の名は諏訪の三郎盛高、ここに辿り着くまでどれほどの人を切ったのか……刀身が雨の中で鈍い光を放ち、血糊が浮いて水をはじく太兵衛が叫んだ。
「いいか、この二人の刀は金になるぞ」
この一言が効いた。
若者の刀の柄には金糸銀糸が巻き込まれている。着衣こそ破れ放題だが由緒ある育ちであることは、この危急の場にあっても動じない毅然とした姿と備えで一目瞭然だった。
幼い上に傷つき疲れているとはいえ、戦乱の世に対処すべく常日頃から鍛え抜かれているのか、有事への心構えが出来ているのか若者には動じた風もない。
二人を包む乱闘の輪は、一刻ほど動く間に人数を増していた。太兵衛らが二人を包んでいる間に、村に駆け戻った男が仲間に動員をかけたのだ。
あれから三人が切られ死に、二人ほど手傷を負って退いた。その退いた男が山師事仲間の小屋を走り廻って、獲物を追い詰めていることを知らせ、相手が手強いことから弓の加勢をも頼んでいた。
「さあ、みんなどけろ。矢を射かけるぞ」
梓の丸弓を構えた男が怒鳴った。
男達が獲物を残して身をひるがえそうとした瞬間、二人にとっての勝機が生まれた。大柄な三郎という武士が野盗の背に襲い掛かった。
若者も、どこにそんな余力が残っていたのか阿吽の呼吸で野盗の群れに飛び込み、ここを先途と一人づつ両手で狙って刀を突いた。もはや片手で刀身を振るう力はない。こうなると乱戦の中に矢も射かけられず、一度引き絞った弓を放たずに戻すと矢筈の位置も狂ってすぐには引き絞れない。木陰にいた弓手はおろおろと慌てふためき、矢を再びつがえ直す。その隙を衝いて若者が飛び込んだ。切っ先をまっすぐにして全体重を刀に預けて迷うことなく地を蹴った果敢な幼い少年の一撃が、弓組の男を襲った。
刀身は見事に男の胸板を貫き、二人は重なって林の仲に倒れ込む。悲鳴がわいた。
浮足立った野盗を大柄な武士が追撃し一気に四人を叩き伏せた。野党等が浮足立って一斉に逃げた。二人を見くびったのが敗因だった。
気丈に背を見せずに刀を合わせた太兵衛の刀身が折れ、万事窮した。
彼は膝からへなへなと崩れ落ち、踏みにじった草花の下のぬかるみにへたり込み、目を閉じた。
このまま、スパッと見事に首と胴が離れ飛ぶはずだ。
(どうせ今世もろくな生きかたはしちゃあいねえ)太兵衛の脳裏に家に残してきた女房と生まれたばかりの赤子の顔が浮かぶ。
「手柄立てて来るだよ」
そう言いながら送り出した女房に、こんな無様な姿をさらすとは思いもよらなかった。「下郎、目を開けい!」
男の声で、ハッとして太兵衛は目を見開き、思わず己れの首に手を這わせた。
「生きてる!」
目の前に立っているのは血塗られてはいるが地獄の閻魔ではない。
大男の武士が凄まじい形相で太兵衛を睨んでいる。
白刃が目の前にあった。
雨が血塗られた刀身から朱色の水をしたたらせている。刃こぼれが見えた。
太兵衛は急に命が惜しくなった。
彼はぬかるみに両手をべったりとつき額を土にこすりつけた。先ほどまでの勢いは失せている。
「食料を調達せい、少しでいい」
これが武士の命令だった。切っ先が首筋に当たっている。太兵衛はか細い声で応えた。「ヘイ。かならず」
林の中では若者が泥だらけの素足で盗賊の胸板を踏み、力を入れて刀を抜いていた。
太兵衛は生きた心地もせず足元も覚束ない状態で、二人に追われるように小道を下り滝沢の集落の外れにある己れの荒屋に辿り着いた。
「おっかあ。帰ったぞ」
蚊の鳴くような声で太兵衛が戸を叩く。
杉皮屋根上の小石が今にも落ちてきそうにきしみながら中から戸が開かれ、布で髪を束ねた色ぐろの女が今外したばかりの心棒を手に、亭主の背後に立つ白刃を持つ大男を睨んだ。板張りの隙間から覗いていたらしい。
小屋の中では赤子が泣いていた。それも、空腹なのか涙が枯れるほどの勢いで泣いている。
「おまえさん。獲物はこいつらかい?」
強がりを言ってはみたが状況は見れば分かる。太兵衛の腰に刀こそあるものの竹槍もなく、笠もなく蓑も千切れて濡れそぼり無残な負け戦さを物語っている。
太兵衛は無言で小屋に入った。
入れ違いに女が外に出て泣き喚きながらも気丈に棒を振るった。肩口から上腕部を打たれながら三郎盛高は避けようともせず髪振り乱し狂ったように棒を振るう女を眺めている。
亀寿と呼ばれた若者もただ立っていた。
女は打ち疲れたのか棒を放り出して崩れ落ちたが、すぐ身をひるがえして家に駆け込み、三和土(たたき)に足を投げ出し板敷きに腰を下ろしていた太兵衛の横面を平手で張りとばした。太兵衛は手で頬を押さえてうつむいた。
「ガラクタばかり集めて」
女は、太兵衛が落人狩りで得たであろう足軽胴を蹴飛ばし、足を痛めてよろめいた。
太兵衛が遠慮がちに声をかけた。
「おっかあ。この人たちに食い物分けてあげてくれ。そいでオレの命がつながるんだ」
女が絶句して目を剥いた。赤子は泣き叫ぶ。
女が呟くように声を絞り出した。
「そんなものがあれば乳も出るだに」
そして、決心したように帯を解き始めた。
身体を張って亭主の命乞いをしようとする女を制し、夕暮れが近付きつつある雨の中に主従は身を乗り出した。足取りが重い。
二人が野道を避けて山道と配流方向への三叉路に入る手前で、待ち伏せしていた数人の男達が刀を抜いて迫ってきた。
「こいつらだ。こいつらに仲間が殺られただ」
山道で二人を襲った時の仲間なのか新手の野盗の背後で男が喚いている。腰が引けているところを見ると闘うのは恐ろしいのだ。その時、女が叫びながら駆けて来た。
「おめえらダメだ!手え出すなあ」
髪振り乱し、濡れた單衣ものが身体にまとわりつき裾が乱れている。裸足のままだ。
近くまで来て止まったが息が荒く声が出ない。全員が女の口許を凝視した。
「おらの亭主が飯くわせるって約束しただ」
女が手に持った油紙を開くと、小さな粟飯の握りが二つ。それを亀寿丸に一つ手渡し、もう一つを三郎の目の前に出した。
「わしはいいのだ」
三郎が握り飯を返すと「約束だぞ」と、女が怒った。
三郎が詫び、女の好意を素直に受け二人が粟飯を口に入れると、周囲の男達が我慢しきれず一様に「ゴクリ」と唾を飲んだ。
二、行知法師
横なぐりに吹きつける谷風が烈しい雨を舞い上げ身体が下から濡れて行く。
一難去ってまた一難、一握りの粟飯にありついたのも柄の間、峠道にさしかかったところで完全武装の群盗が襲いかかって来た。
「亀寿さま。今度は手強い相手ですぞ」
「心得たぞ、三郎どの」
けな気にも刀を構えるがもはや余力はない。
その若者を庇うように三郎盛高は前に出て、行く手に立ち開かった二十人近い野伏に向かい、両手で刀を八双に構えジリジリと進んだ。もはや、逃れる道は閉ざされた。腕が立つだけに限界を知るのも早い。
山と谷にはさまれた狭い崖道は、一歩踏み損じただけで千丈の谷に舞い落ちる。
落人姿で甲州平を抜けて通るのが危険と見て山道を選んだのが間違いだったのか。
北条方の武将として名を馳せた諏訪の三郎盛高も、今際の覚悟をきめていた。
鎌倉から甲斐路まで寝食もままならぬ身で辿り着いてはみたが、手傷を負うた身の不運、手足が思うように動かない。それでも前に進むのは闘って死にたいという武人の本能がそうさせるのか。死ぬことはさほど恐ろしいことではない。
ただ、口惜しいのは執権北条高時殿が一子亀寿丸を、ここまで落としながらついに命運尽きたことだった。北条幕府再興の夢が潰える。無念やる方ない思いだった。
太兵衛の妻の善意で食した粟飯の効も失せて、雨に叩かれて冷えた身体はすでに戦闘能力を失っていた。気力だけが前へ進む。
「この武者は、一撃で倒れそうじゃねえか」
樫の六尺棒を頭上に打ち振るってから肩に担いだ男が頬当てまで用意した完全武装の甲冑姿で前に出た。他の野盗は高見の見物としゃれ込む。
まず一対一の勝負で片を付ける気らしい。
男は軽々と八角の樫棒にしごきをかけた。
棒が風を切る音が谷に谺する。
男は無雑作にそのまま棒を振りながら山側に跳んだ。意外に身のこなしが軽い。
三郎盛高は、刀をゆっくりと下に降ろし地摺りの構えで男に近付いて行く。棒で刀身を叩かれるのだけは避けたい。突如、男の身体が動き棒が長く伸び三郎の頭上を斜め横から襲った。早い動きだった。
多分、身体のどの部分に触れても骨は砕かれる。三郎は身を縮めながら三歩退った。
谷側の路肩に足がかかり崩れた土砂が雨水と共に谷底目掛けて流れ落ちた。
男の棒がさらに追い打ちをかけて迫る。
三郎は転がるように身を倒して棒を避け男の足元にとび込み、横振りに刀を振り力任せに男の足を薙いだ。
「グギャーッ」
異様な声を発して男が崩れた。鋸刃状に刀こぼれした刀身で叩かれては堪らない。肉が裂け骨が折れ、男は痛みに耐えかねてのた打ちまわった。
立ち上がりかけた三郎盛高の頭上に、踊り込んで来た新手の敵の長刀がきらめいた。
体を躱す余裕がない。とっさに刀身を頭上高くに掲げ左手を切先近くの峰で受けた。
烈しく火花が散り、金属の焼けるキナ臭い匂いが散った。三郎が左手でぐっと耐え、右手を下げると敵の刀が鍔元まで滑る。
三郎が体を外すと敵はたたらを踏んで前のめりによろめいたが、すぐ体勢を立て直した。
しかし、その一瞬の隙を三郎は見逃さずに反撃した。三郎の太刀が男の右手首を左逆手から痛打する。肉と骨を断つ鈍い音と男の悲鳴がひびいて野盗の群れを刺激した。
すでに抜刀して待機していた数人の野伏ガ一斉に三郎目がけて飛びかかろうとした時、群れの中から声がとんだ。
「順を守らぬかっ。一人づつ掛からぬと戦利品で揉めるぞ。そ奴の刀は値打ち物だからな」
しぶしぶと刀を引く男達を背に短槍をしごいた髭面の男が悠然と三郎の立ち上がるのを待っていた。いかにも自信あり気だった。
三郎盛高はすでに意識が断続的にもうろうとして来るのを感じていた。足がもつれた。 槍が鋭く胸元に走って来た。本能的に腕が動いて穂先を切り落としたつもりだったが刀は空を切った。槍が素早く敵の手元に戻って再び矢が飛んで来るかのように胸元に迫る。
千軍万馬の古つわものの三郎盛高が同じ手で二度は失敗しない。見事に穂先を斬り落とし、返す刀で男の胸から顎を裂いた。
男は終始無言のまま倒れ、痙攣して果てた。
しかし、勝負に勝った筈の三郎盛高の左の脇に槍の穂先が触れたのか血が流れている。 三郎の左手がその傷口を押さえた。
手強いと見たのか、次の男が仲間を呼んだ。二人で左右から三郎目がけて進んだ。
三郎は刀を右手で構えようとしたが思うように動かず、刃先は地面に着いたままだ。
成り行きを見守っていた若者が健気にも三郎の前に出て両手で刀を構えた。
それを見て頭領らしい野伏が叫んだ。本気になったようだ。
「あのガキの刀はわしが貰うぞ。二人共包み込んでなぶり殺しにしろ!」
「おう!」
一人ヅツ獲物を狙って闘うという彼等の不文律が頭領の一言でけし飛び、瀕死の獲物を狙って群がるハイエナのように飢えた野盗の集団が二人に刀を振るって襲いかかった。
疲労の限界を気力で切り抜けて来た主従二人の終焉の刻は迫り、鬼神の加護が切れる。その瞬間までは例え五体が切り刻まれても刀を振るい野盗に一矢を報いねばならない。
すでに二人は、手傷と返り血で朱塗られ、それを烈しい雨が洗い流し続けた。
「亀寿さま。もはやこれまでお覚悟を!」
「三郎どの。来世で‥‥」
その時だった。
一陣の疾風のように群れの中に駆け入った人影が一つ。奇声を発しながら棒をめまぐるしい速さで振るい、五人、六人とまたたく間に叩き伏せて行く。野盗の群れが動揺した。 死を決した三郎盛高と亀寿丸が立ち直る。
剣を振るう合い間に三郎盛高が雨すだれの先を見ると、ぼろをまとった小柄な乞食僧がわらじの泥を跳ね上げて躍るように棒を振るい、槍剣を繰り出す野盗達を叩き伏せているのが目に入った。かなり年老いた僧だった。
絶叫を上げて谷底へ落ちる男達が何人か続くと、さすがの野盗集団も浮足立った。
二十人近い群れがほぼ半数に数を減らしている。
谷に落ち、草に伏せ、崖土を掻きむしり息絶え一人づつ戦闘集団から脱落して行く。
さらに一人、老僧に肩口を打たれよろめいた野伏がいて、若者がその腹を突いた。男刀を捨てその刀身を両手で握ったが、若者が全力で刀を引いたため指が切れ、甲冑から噴き出た血と混ざって足元に見る間に血溜まりが出来、男は呻きながらその中にうずくまってもがき苦しみ、自分から這うようにして谷に落ちた。絶叫が残った。
「に、にげろっ!」
頭領が喚いて刀を引き、踵を返して峠道の下手へ逃げようと体勢を変えた。その背に死力を振り絞って襲いかかった三郎盛高の刀の刃先が突き立つ。そのまま二人は倒れ、三郎の体重がのしかかり刀身が身体を貫く。泥の中に顔を埋めて男が絶命した。
野盗の群れは消えた。
雨風がぶなの梢をゆすり、崖上から泥土が流れ落ち山道に溝をつくり川となる。
三郎盛高は、脇から流れる血を押さえてうずくまり、亀寿丸は、べったりと草の根に破れ袴の腰を下ろし肩を上下させて荒い息を吐いている。
二人共、精も根も尽き果てていた。
その様子を崖下の凹みで、武器にもなる曲がりくねった太い柿の枝の杖を支えに立ったまま雨を避けている老僧が、じっと眺めている。
その目は、生命あるものは蘇生し、命運尽きたるものは死するという自然の掟を見ているかのように静かなまなざしでもあった。
やがて亀寿丸が刀を杖に立ち上がった。
幼い身に、間断もなくおとずれる招かざる客による襲撃はあまりにも過酷な試練だったものと思われる。
日々の鍛練では倒されることはあっても殺されることはない。ここでは殺さねば殺されるのだ。
いつまた野盗が襲って来るかも知れない。その恐怖が亀寿丸を立ち上がらせた。
「三郎どの。三郎どの」
諏訪三郎盛高は、亀寿丸の声で意識を取り戻した。眠っていたのか黄泉路に彷徨い込んでいたのか定かではない。しばしの間、傷の痛みも空腹の辛さも忘れて恍惚となっていたのも事実だ。しかし、現実に戻ると傷ついた身に苦痛が走った。
三郎盛高は顔をしかめながら立ち上がった。
満身創痍の身ではあったが気は確かだ。
生きている喜びが身体を包んだ。
二人は老僧の姿を目で求め崖下に立つ僧を認め目礼をし、よろよろと歩き始めた。
老僧は何事もなかったように歩き始めた。
二人はごく自然に無言でそれに続いた。
老僧は、傷ついた二人を労るようにゆっくり歩いた。峠道を下るうちに雨は小降りになっていた。道はまだぬかるんでいる。
「一夜の宿を進ぜよう」
老僧が歩をゆるめ二人に優しく語りかけた。
「かたじけのうござる」 三郎が応えた。
「この辺りはとくに落人狩りが盛んでのう」
二人を励ますように時折、老僧が語りかけるが返事を求めるでもなく呟く。
「幕府の命によってどの村も流浪の者に軒下も一夜の宿をも貸すことならず、恵みを施すも禁ずとなり、わしのような乞食僧にさえ口をきくのをはばかるように戸を閉ざす」
老僧は杖を突いて立ち止まり、破れ笠の庇に手を当て空を見上げた。雨がまた激しく降って、松やぶなの梢が崖道の空を覆い暗い夕暮れをさらに暗くしていた。低い雲が動いている。老僧がまた歩き出し、二人がゆるゆると続いた。
彼等が歩んで来た方角で山犬の遠吠えが長く尾を曳いて谺した。群れを呼んで屍を漁り、飢えを凌ぐのか。呼応する山犬の声があちこちから響く。
夜烏の群れも声高に騒いでいる。山犬と屍肉をめぐって争っているのでもあろうか。
北条家没落の噂は、雲よりも風よりも速く全国津津浦浦、海辺はいうに及ばず鄙びた山間の寒村にまで聞こえ、それまで長い間隠忍自重して屈辱の日々に明け暮れていた甲斐源氏も蜂起し、村人までもが殺気だっていた。
路傍の山薄荷や、密生するあかざの群落で鳴く虫の音が濡れわらじの足音に驚いてかピタリと閉じ、一行が行き過ぎるとまた騒がしく音を奏でる。
曲がりくねった坂道を下り、林を抜けると瀬音がして木橋が姿を現した。釜無川の支流らしい。
老僧は、橋の袂の雑草をかき分け、慣れた足つきで道なき坂を下りながら振り向き二人を手招いた。露草と雨で全身から水が滴っている。
亀寿丸が河原を走り腰を折り、濁りの強まっている流れに顔を埋め存分に水を飲んだ。口の中に豊かな潤いが満ちた。
三、諏訪一族
「折居の部落まではまだ遠いでのう‥‥」
人里に立ち寄ったとて寄辺なき身に囲炉裏の火や煮えたぎる猪鍋が待つでもない。老僧にとっては、この藁の褥を隠した橋の下や古木の根の洞穴、堂などの縁の下が家であり、身も心も安らぐ休息の場だったのだ。
雨の届かぬ橋桁真下の藁の底をまさぐっていた老僧は、やがて油紙の包みから薬草をとり出して三郎に与え、自分は火打石と点け木を手にして腰を下ろした。
比較的濡れの少ない橋下の石場に、藁や集めてあった木片を重ね石を打ち火を点した。 小さな炎が橋下の夕闇に男達の顔を赤く照らした。三人はじっと炎が燃え上がるのを待つ。寒さと飢えで身体は冷え切っている。
「さ、さ、脱いで乾かすならこの棒を立てて掛けなされ」
僧が枝切れを二人に渡し、なお藁の底を探すと、瓢箪が出た。確かめるように両手で持ち、さらに耳元でそれを振ると、僧は満足気に皺の多い顔をさらにくしゃくしゃにさせるとまばらに残る歯が笑った。
三郎盛高に促されながらも亀寿丸はかたくなに表情を硬ばらせ一向に着衣を脱ぐ気配もない。幼い身を襲ったここ数日の恐ろしい闘いの連続によって亀寿丸の心は閉ざされていたのかも知れない。
「まず、毒味をな‥‥」
老僧は瓢箪に口を付け上を向いて喉を鳴らした。喉仏が二度三度上下し口が離れた。
「ごくらく、ごくらく。さ、遠慮のうやりなされ。まだまだたんと蓄えはあるのじゃ」
火は薪に移り、炎が橋板を焦がさんばかりに燃え盛った。瓢箪が三郎の手に渡った。
三郎盛高はすでに衣服を脱ぎ力任せに水を絞ると石間に立てた枝木の上に広げ、下布一つの身になり薬草を揉み、亀寿丸と分けた半分を傷に貼り、筋肉隆々の身体を火に焙りながらいかにも旨そうに少量づつ味わいながら酒を飲む。その顔には闘いの陰はない。
僧もまた破れ衣を脱ぎ枝に乾した。
やせた身体に刀傷の跡が見える。僧が口を開いた。
「わしの聞き違えかも知れんが、たしか先刻そちらのお子を『亀寿丸さま』と申されたかの?」
三郎が顔を上げ僧を凝視し、亀寿丸が刀を引きつけ身構えた。僧は委細構わず続けた。
「亀寿丸さまと申さば相模の入道殿が御嫡子、すでに兄ぎみの万寿殿は、ご実母の兄でもある五大院の右衛門宗繁殿が預かって密かに隠まっていると伝え聞いてござる」
そこまで聞いた亀寿丸が立ち上がり刀を抜き一歩前へ出て炎を中に振りかぶった。
それを三郎が制した。しかし、三郎の手もまた刀に伸び、目に殺気が浮いている。
「幕府倒るるとき、その一族郎党子々孫々に至るまで誅殺しその根を絶やすは戦国の世の習い。生かさば必ず仇をなすのは必定。源家頼朝公の例をまつまでもない」
亀寿丸が火を飛んで僧の頭上に刀を振り下ろし、僧が軽く横に飛んで逃れた。
「危ふし危ふし、武将は無闇に刀を用いず」
老僧は何事もなかったように火を突く。
刀を捨て石に伏した若者が哭いた。
「泣くがよい。存分に気の済むまで泣くがよい。いずれ泣こうにも泣けない日々が来る。多分、兄君の万寿丸殿は近々討たれよう」
「ご坊。なぜだ? なぜそのように酷いことを申される……」
と、三郎が問う。
「それは戦国に生き抜く処世だからじゃ。五大院の宗繁はそなたと違い戦いに明け暮れる武将ではない。生命を惜しむ政務の士よ。平氏北条家執権の嫡子をどうして庇い切れようぞ」
「宗繁殿が反逆くといわれるか?」
「人それぞれじゃ。止むを得ぬ仕儀もある」
「わしをなぜ違うと見られたか?」
「その顔よ、顔。この鎌倉街道をどこまで落ちなさる。甲斐路を過ぎれば信州諏訪の領地。諏訪に落ちる武者で三郎殿といい、北条殿が一子を委されるは諏訪の三郎盛高殿をおいて誰があろう」
三郎が周囲を見た。山里の谷間に人の佇む気配などあろう筈もない。すでに刀の鯉口は切ってある。これだけ知られているとしたら僧とはいえ神佛に逆らってでも切るより他に口を塞ぐ手段はない。亀寿丸も元の位置に戻り、成り行きを見守っている。老僧が笑顔を見せた。瀬音と虫の音が姦しい。
「まあ、その難しい顔を崩して今少しご酒を嗜みなされ。そちらの若者もどうじゃな?」
三郎が気勢を削がれて刀を置いた。
瓢箪が再び三郎に渡った。
亀寿丸も無言で三郎の勧めるまま口をつけむせって咳き込んだが、濁り酒が意外に口に合ったのか喉を鳴らして飲み干した。
焚き木がはじけ炎が煙を生み、三人の顔に生気が甦った。交互に酒がまわる。
静かな沈黙の時が過ぎ瓢箪が空になると、老僧が再び藁の下をまさぐり二本目の濁り酒をとり出した。沈黙を破って三郎が口を開いた。
「ご坊の名はなんと申される?」
生木を火にくべたため燻されたせいもあってか顔をしかめた老僧が焚き火の薪を並べ替えながら自嘲気味にぼそっと投げやりに呟いた。
「名もない乞食僧じゃが、名乗らぬのも詮ないこと‥‥」
と、しばし間をおいて、ぽつりという。
「わしには、たしか行知という名があったかな」
三郎が宙を見た。
夕闇に包まれて周囲の山々が黒く迫っている。
雨は小止みになり、雲が速く走り切れ間が見え隠れしている。梟が飛んだ。夜陰にまぎれて野鼠でも襲うのか。
段丘状になった崖上の樹林の幹や枝葉を通して鳥居峠の西に遠く観音岳の黒い稜線が、暮れなずむ谷間の雨に煙っていた。
「行知? 行知上人? と、なればすでに亡き人では?」
三郎が遠い思い出を手繰り寄せでもするかのように空を見上げたまま続けた。
「父より聞きし一族の縁に繋がる樋口の殿がご出家話、ご存命なれば齢すでに七十余」
「恥を忍んで生きさばらえし七十余年、今は一介の放浪の僧なれば上人でも殿でもない。行知という名すら久しく忘れておったものじゃ」
「わが父と樋口の殿は旧知窮地の間柄と聞き及び申すが‥‥」
「知らいでか。左馬の介入道殿は幼時より文武に優れし者。鎌倉でも忍んで会うたわ」
「恐れ入り申す」
「して、入道殿は如何なされたかな?」
「執権殿より亀寿さまを預かりなされて私めにその任を譲り、郎党を引き連れて極楽寺の切通しに討って出て老い花を咲かせ、見事に散ったと聞き及んでおりまする」
「それは重畳、武人は最後を飾ってこそ誉れあるもの、わしの如く老惨をさらし生き永らえたとて何の益があろう。ましてや一族の恥と謗られののしられての出家ではな」
三郎盛高は黙して行知法師を凝視した。
父左馬の介入道は各地の風聞に詳しく平氏北条の末路を予言し、執権を練めて幾度も不興を被っていたのもかような伝手があった上での讒言であったのか。ならば、なぜ?
その三郎の心を読むように僧が続けた。
「お父上は、わしが如き縁者にも優しかった。しかし、いずれの地をも往来する流浪の僧を身内に持ち接遇するなどという噂が幕内に聞こえでもしたらあらぬ疑いをかけられたであろう。ましてや諏訪は上社下社共昔は源氏方の頭領。今さらわしが申すまでもなきことじゃが、華美酒宴に万貫を費やし逸楽にふけって幕府の命運を閉ざした暗愚の執権相模の入道殿が助役ではさぞかし辛いお勤めであった筈」
「いや、ご上人。わが家のことは‥‥」
「ならば亀寿丸ぎみに話して聞かそう。三郎どのとてその手傷ではすぐには眠れまい」
「いかにも」
出血こそ止まったが薬草を刷り込んだ傷口はまだ痛む。三郎は遠慮なく酒を飲んだ。
行知法師は訥々と抑揚もなく語る。
「古の物語じゃが、昔、諏訪地方一帯に神族の名を借りて暴れまわった出雲集団と呼ばれて恐れられた一族があった。
その古代民族は、山岳神崇拝の上社と海の神崇拝の下社とに分かれたが互いに結託し、共存共栄を計りながら北信一帯に勢力を拡大したそうな。
その諏訪社がなぜ全国に広まったかというと、延歴年間に征夷大将軍田村磨の軍勢に将として加わり軍功を立てた諏訪氏一族が神の加護を得た軍団として鳴り響き、その名声に時の為政者が目をつけたのじゃ。治安の維持や民心の統一を計るには、神佛の名を立てるのが常道。祭事の奨励などに諏訪社の名が用いられ、その行事頭人として諏訪一族の系類縁者が勤めることになった」
亀寿丸が口をはさんだ。
「なぜ源氏方の諏訪が平氏北条家の重臣となったのだ?」
「さればでござる。保元の乱、平治の乱に続く平氏一族の勢いが調停を脅かす存在となり、高倉天皇はついに全国各地に隠れ忍びいた源氏一族に平氏打倒妥当の密書をまわされたのじゃ。
雨後の筍のごとく源氏の武士は決起せしが数を頼りの寄せ集めの軍勢では、全盛の平氏に歯も立たず蹴散らかされて謀り事は無惨にも破れた。しかし、それは終わりではない。 伊豆に流されて育った源氏の頭領頼朝が挙兵し、それに呼応して諏訪一族と我らが遠祖中原、樋口も義仲を立てて挙ったのだ。
当時、木曽谷から伊那、諏訪一帯に勢力を誇っていた中原の権守兼遠が、源義賢の遺児駒王丸を奉じて兵を集め、諏訪上社の頭領である千野の光弘を将とした諏訪一族も参戦している。これが三郎殿の祖にあたる」
「行知どのが遠祖樋口の兼光は中原の兼遠の次男」と、三郎が口をはさむ。
「勇猛で鳴らした今井太郎兼光と樋口二郎兼平の兄弟は天下無敵の勇者だったそうな」
「その話は幼い日々に聞きおよんでいる」
亀寿丸が続けた。
「その駒王丸が長じて義仲殿となるのだな」
行知法師が頷き、話を続けた。
「義仲の父源の義賢は甥の悪源太に討たれ、その遺児駒王丸も殺される運命にあったが、兼遠は妻を乳母とし、駒王丸長じて義仲と名乗るに及んで己れが娘巴を娶らせ、一気に積年の野望を果たすべく立ったのだ」
瀬音、虫の音に混じって梟が二声鳴き、行知法師が一声応え、さり気なく話を続けた。「木曽の山猿といわれ戦闘力だけは抜群に強かった義仲軍の勢威は本隊であるべき頼朝軍をも凌ぎ、旭日昇天の勢いから旭将軍とも称されたが、軍兵や兵糧の徴発で頼朝軍と争ったのに端を発し、ついに仲違いをすることになる。その折、木曽党に伴いていた甲斐源氏一党が鎌倉方に寝返ったことで諏訪と甲斐との確執が始まり、今の世にも続いておるのじゃ」
「それで諏訪の落人に甲斐の野伏は辛く当たるのか?」
と、亀寿丸。それには応えず行知法師が続ける。
「嘘か真実かは知らぬが、頼朝の元に間謀からの報告が届いた。義仲が敵将平の宗盛と和睦し秘かに手を結ぶという話だった。
真偽はともあれ、危険な芽は早く摘むに越したことはない。頼朝はまようことなく義仲討伐の軍団を木曽に向けて発進させた。
義仲は身内の争いを好まず軍を越後に下げ、頼朝との誤解を避けるため、長子の義高と頼朝の息女との縁談を進め一時的ではあったが和睦が成立したのだ。
義高殿の鎌倉入りは人質同様で、これに付けられたのが文武に秀でた諏訪一党だった。いわば諏訪一族も木曽源軍から送られた人質だったのだ」
行知法師は三郎から渡された瓢箪に口を付け旨そうに口許を手で拭った。
三郎が焚き火に枝木をくべながら話を継いだ。亀寿丸は腕を組み目を見開いている。
「寿永三年、冬の粟津で鎌倉軍に追討されて三十一歳の生涯を遂げた木曽冠者義仲に次いで、鎌倉にいた義高も討たれ諏訪一族も捕われの身となった」
行知法師が続けた。
「神社崇拝の心をもつ頼朝公の決断で諏訪党は許され、以来、幕府と命運を共にせざるを得ない環境に置かれて諏訪一族は平氏北条幕府の要職に就いて来たのじゃ。」
「木曽方は絶えたのか?」亀寿丸が問う。
「鎌倉六万騎との闘いに破れ、粟津に敗走した義仲軍はわずか十三騎、わが祖・樋口二郎兼光様も凍てついた冬田に射落とされて果てたのだ」
さらに続けて、行知法師が呟いた。
「戦さとは惨いものよ」
ここで言葉が絶え夜の闇に炎が燃えた。
四、天王寺の戦い
諏訪三郎盛高は、鎌倉が勢いを失い始めた今から一年ほど前の正慶元年(一三三二)五月、河内の悪党組の旗頭である楠多門正成と、南朝と北朝方に分かれて戦陣を張ったことを懐かしく想い出し、焚き火に手をかざしながら語りだした。
「楠殿が非凡な武将であることは以前から聞こえていあたが、あそこまで手強いとは思いもよらなんだ。これは、まだ、楠殿が我等に味方であった頃の話じゃが……」
三郎盛高が行知上人を見た。
「数年前のことになるが……その当時、幕府に逆らって乱暴狼藉の限りをつくしていた摂津の住人で渡辺高右衛門という悪党がいた。さすがに執権の高時殿も腹に据えかねてか次々に直属の兵を討伐に差し向けたが、のらりくらりと逃げられるか返り討ちにあうかで一向に埒があかない。この渡辺一味の暗躍に散々に手を焼いた執権殿が、私らに相談なさる前に、なに気なく楠殿に渡辺一族の討伐を打診したところ、気軽に出陣した楠殿は数日にして敵を殲滅し、お味方を唖然とさせたことがござる。その楠殿を敵にまわして争うことになろうとは思いも寄らぬことでござったが、その後の活躍はご承知の通り……」
「幕府が勢いを失ったのも、その楠党を敵にまわしたあたりからじゃな」
行知法師が亀寿丸を見た。
「そなたは賢こそうじゃから心してかかれば、再び天下も奪れよう……だが、名家名門の崩壊はた易きことなれど、お家再興は難事中の難事。父君の高時殿は暗愚の上に華美を好み、民の暮らし向きの苦しさなど斟酌することもなく田楽酒宴に空を抜かすうつけ者じゃ
った故に滅びたことを忘れるでない……」
この行知法師の言葉から三郎盛高は、共に手を携えて闘った北関東の武将・宇都の宮治部大輔公綱の口ぐせが「心してかからねば」だったのを思い出していた。
楠多門兵衛正成が後醍醐天皇を迎え、幕府に反旗を翻して赤坂域に挙兵したのは元弘元年十月、ここから一進一退の攻防が始まり幕府は思いもよらなかった消耗戦を強いられ、行知法師の言葉通りこの辺りから幕府は衰退への坂道を転がり始めたのは確かだった。
京都六波羅軍の隅田源七左衛門を大将とする五千の軍勢も天王寺の戦いに破れ、城兵わずか五百名という楠軍がたて籠もった小さな山城の赤坂域は、三十万の兵をもって攻め立てても材木や大石を落とされ熱湯を浴びせられるという体たらくで、幕軍は敗北を重ね、ようやくの思いで赤坂域を攻め落とすと中はもぬけの殻……しかも、正成の影武者の死体を本物と思い誤って勝利の雄叫びを上げた直後に、突然の襲撃を受けて死者続出で軍は乱れ敗走に次ぐ敗走という始末でまったく手に負えないし歯が立たない。
幕軍としても引くに引けず、宇都宮公綱を大将とし諏訪盛高を副将とする強力な本隊の出動となる。いよいよ弓矢の名手を揃えた諏訪党にも出番が廻って来たのだ。宇都宮と諏訪の連合軍二千の将兵は意気高らかに出陣した。その中には一度ならず二度までも正成に苦汁を飲まされた六波羅の高橋九郎左衛門や、大館二郎宗氏なども手勢を引き連れて参加していた。宇都宮連合軍は、仁和寺から宇治川沿いに摂津、生駒山へと迂回して野営、翌朝に天王寺を攻める手筈で粛々と駒を進めた。
最初に楠軍が襲って来たのは四条畷の森にさしかかった時だった。
突然、背後から見事な手綱捌きの騎馬武者が約百騎、横合いから幕府軍の隊列を横切って切り込み、矢を放ち刀や槍を振り回して風の如く去った。それだけで幕府側からは死者八名、負傷者十数名が出た。瞬時の出来事で矢を番える間もなかったが、それでも三郎は三の矢までを射て二人を倒した。残された敵の死者はその二人と、宇都宮公綱の刀にかかった一人のわずか三名だけだった。幕軍の射た矢や刀槍などで倒した敵も何人かはいたはずだが、馬から落ちた負傷者は仲間が馬上に引き上げて運び去ったから、敵の重軽傷者の正確な数は分からない。
宇都宮公綱と諏訪盛高は直ちに話し合い、縦に長く続いた隊列を小隊編成部隊に組み替えることにした。楠軍の波状攻撃は三波まで続いたが、臨戦体制になった幕軍の備えを崩せずに楠軍からも十名におよぶ死者が出て攻撃は止んだ。倒すのも倒されるのも拮抗して
いては被害が増えてお互いに効率が悪いし、これでは勝敗はつかない。
生駒山の麓で日が暮れると軍列は野営地を求めて森に入り、宇都宮・諏訪両軍の将を招集しての軍議となる。宇都宮公綱が言った。
「今夜、敵は必ず寝入りばの時刻を狙って夜襲をかけて来ると見た。各々構えて油断めさるな。敵が小人数であれば包み込んで殲滅するまでじゃが、森に火を放たれて馬が暴れると厄介なことになる。絶対に敵を森に近づけんように戦うのじゃ」
諏訪の三郎盛高が応じて、指をさした。
「われらは、あの丘の中腹に陣を構えるによって、雲間洩れで月でもあらばじっくりとご笑覧あれ。じゃが今宵は雲厚くいつ月は消えぬとも限らぬ、闇夜の矢は無駄が多いことゆえご無用にな」
「いや、外れ矢は明朝探すによって案じ召さるな。それより当方からの夜襲は?」
「勝手知らぬ敵地での夜襲は危うござる。生半可な夜襲で警戒されるよりは、夜明けと共に正攻法で敵に挑むが常道。勝つも負けるも一気呵成の勝負で決まり申そう」
「今宵はこれからどうなさる?」
「すでに乱破をあちこちに放ってあるによって、森の中に陣を張って待ち、敵の備えを知ってから動きを考えましょうぞ。正成に策は通ぜぬ、無策こそ最上の策と思案致した」
小雨は上がったが雲は重く垂れ込めていて暗い夜の闇が忍び寄る。
戦闘を間近に控え将兵は馬を労り装備を解いて餌を与え、三郎自らも干し飯を噛じり味噌を嘗め水を飲む。
軍議での公綱の言は本音ではない、三郎はそう見抜いていた。
やがて、闇の中に兵が消え、止んでいた虫の音が騒がしくなった。将兵がそれぞれ草叢の中に潜んだのだ。
放っていた物見の兵が忍ぶように戻って来て楠軍の動向や備えを報告しまた闇に消えて行く。しかし、物見の兵の半数が襲われてか戻らない。
暫くして、三郎盛高の許に宇都宮公綱からの召集がかかり、森に入ると幕内の燭台のゆらぎのなかで案の定、公綱を中心に数人の将だけで密議をこらしていた。
「おお諏訪殿。お待ち申し上げた。さ、さ、どうぞ」
廻って来た酒盃を一口で呻り、三郎は平台に置いた朱入りの地図を見つめた。
公綱が口を開いた。
「諏訪殿が見えたところで本軍議を進めるが、なんなりと意見を申し述べられよ」
そして、淡々と斥候の兵の報告を告げた。
「天王寺境内には赫々と篝火が燃え盛り、兵共は酒を酌み交わし、女を侍らし、裸踊りを舞っているとか……」
「なんと? 舞いをな?」
大館二郎宗氏が目を剥いて叫んだ。
「今から夜討ちじゃ。一気に攻めようぞ」
「ところがだ。主だった将をはじめ正成の姿も見えぬそうだ」
「罠だな」
高橋九郎左衛門がポツリと呟いた。
六波羅の将として雪辱戦として参加したている高橋の九郎も、楠軍の兵略は裏の裏を読んでも見抜けない。
「周囲の山にも兵馬の姿が見えないそうだ」
つねに正攻法で闘うことを武将の誇りとするっている宇都宮公綱にとって、正成の軍略は邪道と見た。しかし、その邪道に幕軍は翻弄され続けて刃が立たない。なんとも歯がゆい状態なのだ。
「山へでも逃げたのか?」
長崎四郎左衛門泰光という武将が嘲るような口調で吐いた。それを無視した公綱の目が三郎盛高に向いた。
「諏訪殿はどう考えなさる?」
「楠党は全力を挙げてここを襲う……」
全員が三郎の口許を見つめた。
「どうも気がかりなのだ。先刻我らを襲ったのは、馬印こそないが平野将監入道に間違いない。以前、楠党がお味方にあった時に見知っている故万が一にも見誤ることはない」
「楠党四天王の一人、平野将監がなぜ?」
「それは、我らが備えの強弱を試さんとしたまで。すでに本隊は近くまで忍び寄っているとも考えられるが、各々方はいかが思われるか?」
三郎の言葉が終わらぬ内に物見の兵が一名息せき切って走り込み、膝を折って頭を下げた。口もたどたどしい。
「申し上げまする……」
「なにか? 早う申せ!」
「先刻、物見に出た関谷孫兵衛があの丘の横で切られ、果てておりまする」
「なに!」
「近くを探りましたところ、この森の北に楠軍の軍馬が潜み機を窺っております……」
「して数は?」
「その場に数百、さらにその西の林に本体らしき兵馬約五百騎、その北に二百!」
「いかがいたしたか!」
物見の兵ががっくりと首をうなだれて叫ぶ。
「無念! 敵は我らを待ち伏せ、つぎつぎに切って捨てて……」
三郎が抱いたとき、物見はすでに息絶えていた。
首筋から血が流れている。
「よしっ。敵はすでに我らが動きを察知していよう。かくなる上は先の先をとり丘の上から攻めようぞ」
その諏訪の三郎の決断に、宇都宮の公綱も迷いはない。
直ちに全軍への伝令が草叢に散り、将兵は背丈ほどもある雑草の中を匍匐して諏訪党が潜む雑木の丘に合流すべく動いた。だが、その動きは楠軍の乱波に見破られていた。
楠軍は、連合軍のが移動し切らぬ内に森を遠く迂回して攻撃を開始した。
先刻まで幕軍が潜んでいた叢に風上から火が放たれた。火が風を呼び炎が草原を包む。刀を振るう武者が、まだ丘に辿りつかぬ幕兵目がけて駒を走らせた。敵が怒濤のように押し寄せて来る。
炎が楠軍の武者を夜の闇から浮かび上がらせると、幕軍がそれを狙って矢を放った。諏訪の三郎が片膝立ちで弓を引き絞り矢を放つと、その絃音が夜空に響いて全軍を驚かせ、楠軍の騎馬武者が喉を射抜かれて悲鳴を上げ刀を放して落馬した。
諏訪党の放つ矢は的確に敵を射続けた。
闇夜で弓は使えまいと三郎の助言に逆らって、弓の用意のなかった他の武将は兵を引きつれ刀槍をきらめかせ雄叫びを上げて丘を駆け下り敵陣になだれ込み乱戦となった。
雨が降り、火が消え、闇が訪れた。
火は森までは届かず、馬は騒いだが無事だった。
敵は見事な引き際で闇の中に姿を消した。
諏訪党のすぐ下の藪木の群れが風もないのにガサゴソと枝葉が擦れて揺れた。
三郎盛高が目をこらす。
槍でも伸ばせば届きそうな位置から声がした。
聞き覚えのある正成の低く太い声が地を這って響いた。
「諏訪殿! お手並見事であった。明日また見参。宇都の宮の大輔によしなにな」
三郎の周囲の兵が一斉に藪を分けて声のあった方角に押し入ったが人影は消え、あざ笑うような低い笑い声がはるかに離れた丘の麓から尾を引いて残った。
「追うな。追えば相手の思うつぼぞ!」
それでも血気な兵が声のある方角に迫ったが、周囲からくり出される槍の餌食になり草葉の露と消え、異郷の地の土と化す運命を辿った。
雨は止んだが雲間は切れず星もない夜だった夜鳥が啼き、虫がすだく。
各隊が点呼を始め、無事を喜び合った。
翌朝、夜明けを待たずに幕軍は天王寺に攻め入った。焚り火は燃え上がっていたが人影はない。夜が明けると朝の陽が射した。
「充分に休め。ただし心してな」
油断と見せかけて敵を誘き寄せる。
宇都宮公綱は、軍団を半数に分け戦闘員を物陰に伏せ、半数を休ませた。昨夜は仮眠する余裕もなく戦い、夜明け前から早駆けして敵陣に入った。皆、疲れているのだ。
敵の姿が見えない安堵からか、休息を許された兵は、食事もそこそこに死んだように眠った。五月の風は緑の樹々を抜けまどろみを誘う。
物見の兵が敵の動きを知らせに馳せ戻った。
敵は四方八方から迫っているという。
公綱が不敵な笑みをもらし三郎に伝えた。
「ここの総大将は諏訪殿にお任せする。敵が山門内に入るまでは姿を現さず隠れ伏せて下され。我らは一時撤退と見せかけまする」
公綱が下知すると、熟睡と見えていた兵までがと跳び起きて公綱の馬に続いて走り出した。攻め入る楠軍の法螺貝の音が響き、鬨の声が谺した。
敵の物見が幕軍の敗走を知らせたのか、追撃の騎馬武者とそれに続く兵が宇都宮軍を追った。
無人と思われる天王寺の山門内になだれ込んだ将兵に隠れ待った諏訪三郎の指揮する幕軍が雨霰と矢を射かけ、倒れ伏し慌てふためく楠軍に縁の下に伏していた幕軍の将兵が襲いかかり切り掛かり乱戦になる。
用心して遠巻きに待機していた楠軍の本隊が支援に駆け入り、撤退と見せた宇都宮軍が追撃した敵をけ散らして隊列を揃えて天王寺に攻め戻った。
敵も味方もない。
己が生き残ることだけのために刃を振るい組み打ち首を刎ね腹を刺した。戦闘は夕暮れまで続き、両軍の優劣の見えぬまま両軍の総力戦は山場を迎えた。
乱戦のさ中、正成の本隊と諏訪三郎盛高の本隊が堂の廊下で遭遇し、大将同士が刃を交える白兵戦となった。
宇都宮公綱がそれに気付いて力添えに走ると三郎が制した。周囲の兵はそれぞれ斬り合う。
「正成、一対一の勝負ぞ!」
「おう、心得たり盛高!」
正成の豪剣が風を切って三郎を襲い、刀と刀が烈しいひを散らすこと三合、鍔迫り合いから組み打ち。また離れ刀を拾い、打ち合う
。
「盛高!」 正成が刀を構え息を弾ませた。
「なんだ!」
「互いにここで生命を落とすは本望ならず」
「なんとする?」
「両軍引こうぞ。いずれまた生命あらば」
「よし。貴様の生命預けおく。粗末にすな」
「心得た。公綱も承知か。また闘おうぞ」
「二人の決め事、不服なれど承知!」
「盛高。公綱! 武運に誉れあれ!」
「正成! 次の機には心してかかられよ!」
「おう。そなたらもな!」
両軍に撤退命令が同時に発した。
攻めるより難多い引き上げを互いに追うこともなく、大海の潮の引くが如く山門を裏表に分かれてすみやかに退いて行く。
その日から十日ほど攻防を繰り返した後、楠軍は金剛山の山際に退いた。
宇都宮、諏訪の連合軍は意気揚々と京都へ凱旋した。大将、副将の二人以外は真相を知らない。 連戦連勝で戦えば必ず勝つという常勝神話を築きつつあった楠軍を敗ったと信じる幕兵の意気は上がった。
だが宇都宮公綱の軍は京都から鎌倉へ戻ってすぐ、兵を纏めて上野へ去った。幕府に見切りをつけたのだ。
楠正成が再び天王寺に入ったときは機内の豪族を集め、軍勢は数倍に膨れ上がっていたという。幕軍はここから衰運の坂道を転がり落ちた。
「あの時、正成を倒しておけば……」
三郎が呟くと、行知も呟く。
「魔がさしたのだ。昔、わしも若気の至りで魔がさしたことがあってな……」
行知が炎を見つめた。
五、花散る谷
正応四年の春四月、山桜が満開となって奥信濃安曇野の山深い白駒の峯を包んでいた。 山城の眼下はるかに犀川の流れが地形に沿って曲がりくねり陽光を浴びて流麗にきらめいている。樋口行時三十一歳の春だった。
白駒の峯の要害に立つ山城を白駒城と人はいい、城主の樋口行時を白駒の殿と呼んだ。 城の守りは完璧。西側以外の三方は目もくらむような断崖で、木造の城は東西十五間、南北十間の白い塀の中にあった。
城の西側にも断崖絶壁が続き、そこには戸張橋と名付けられた粗末な木橋がかけられていた。橋幅は狭く、人馬はすれ違うことが出来ない。先に入った人馬が橋を渡り切るまでつぎの人は待つことになる。外敵が攻め入るに難しい難攻不落の山城だった。
その橋から眺める景色は天下一といっても過言ではない。全山の桜と共に岩肌に密生する山桜が一斉にその赤味の強い明るい色を惜しげもなく満開にし、崖はおろか谷底までをも花で埋め、人々を感嘆させる。
例年、白駒城主樋口行時が催す花見の宴がこの橋際の広場に筵を敷きつめ一族郎党、遠来の客をも招いて盛大に行われた。
信濃の山々にはそれぞれ源平に分かれて闘った信濃武士の拠点となる山城が築かれていたが、鎌倉北条幕府の開設後は争いもなく交流し親睦を深めていた。高麗より襲来した元軍が壊滅して十年余、天下は太平の世にあった。
昔の敵味方が平和に酒を酌み交わす。しかし、武将達に不満がない訳ではない。弘安の役に従軍し闘った武人に恩賞も乏しく、幕府に対する不満は年々高まりつつあった。
そのうっ憤を晴らすかのように、近郷在々から集まった武将たちは酒宴に乗じて大いに語り国政を憂い、日頃鍛練した武技を発揮する場のない無聊を嘆き、剣舞を舞った。
酒宴には、招かれた武将の妻妾や近郷から呼ばれた郷士の娘達も参加して彩りを添え、華やかな宴をさらに華やかなものにした。
恒例の花見の会を無礼講と知る領地の農民が重ね箱に精一杯の酒の肴を詰め進物として携え家族連れで宴に加わり、殿より直々のお流れ杯を有り難く嬉しそうに頂き感涙に咽ぶのだった。白駒の城主は誰からも慕われていた。
妻女達にとっても花の宴は、家事と野良仕事に明け暮れる日常生活から開放される唯一の娯楽の場でもあるのか、その表情は皆喜々として一様に明るい。
「おい、そこな娘ご。わしにも酌をせい」
酔った武将に呼ばれ、娘と見間違えられた妻女が笑みを浮かべて酒器を運びしなだれかかり科をつくる。それを見て女達が笑う。
酒宴は女房や娘が晴れ衣の裾をなびかせて笛や鼓に合わせて舞うにおよんで最高潮にたっした。詩を唄うもいる。
手拍子も響いた。
そのざわめきは、北側の眼下はるかな宮の平から三州街道へと届かんばかりに谷から峯へと谺した。桜がはらはらと舞っている。
「樋口の次郎殿は果報者よのう」
峯を隔てた滝沢城の主で、先祖の名を継いでいる手塚太郎頼重が万座の中で大声を上げた。
「ほう。そは何故かの? 頼重どの」
他の招待客である武将が酔い声で問う。
「知れたこと。三国一の美女を二人も抱えおって、鎌倉までも京までも聞こえおるわ」
その一言で喚声が沸き拍手が鳴った。妻女達すらそれを肯定して囃し立てた。
「さような戯れ言を……」
行時が酔いの廻った顔をさらに赫くして打ち消そうとしたが語尾は空しく揶揄と羨望と妬みの声にかき消されていた。
事実だった。戯れ唄として知られている。
「信濃山城白駒城。殿には二つの宝あり。
一つは正妻ふじ殿で、一つは愛妾きよ女殿」
こう唄われて伝わっていた。
恒例の花見の宴に集まる人達の中には、酒宴そのものよりも花よりも、この生命ある二つの華やかな宝を一目見ようと訪れる輩も多かった。美しい花は桜だけではなかったのだ。
樋口行時二十一の夏。早逝した父に変わって信濃軍を率いて元の蒙古兵と闘った弘安四年武勲を立てて帰国し、親族の長老が薦めるままに、近郷随一の美しい娘との噂高い大町在の武士米持徳右衛門の自慢の娘ふじを娶ったのである。ふじ十八歳、行時は一目見て胸が踊った。
ふじもまた行時を鬼をも凌ぐ猛将と聞いて緊張していたが、会った瞬間に見せた笑顔に優しさと含羞(はじか)みを見て一度に心が和み好もしく頼もしく、そして愛しさを感じたのだ。
行時とふじは仲睦まじく暮らし、ふじの気配りにより白駒城保護下にある人々の暮らし向きは近隣と比べて豊かに明るく楽しいものとなる。二人を慕う人々は機会あるごとに曲がりくねった山道を汗かきながら作物を運び、ふじ女の労いの言葉に感激し喜々として家路に就くだった。
ふじ女の美しさは、一面に山を包む桜花の華やかさではなく、雨に濡れた川辺の樹林に雅びに咲く淡紅色の海棠の花の気品ある輝きだった。その美貌と奥床しさは噂の的だった。
行時は、そのふじ女をこよなく愛した。
その相愛の二人の間には子供がいない。周囲の期待にも関わらず懐妊の気配もないまま五年の歳月が流れた。
ある夜、ふじ女が添い寝の耳元で囁いた。行時の手が優しい。
「お子を生じなされませ‥」
「なんと?」
「お相手の娘ごは、すでにお選びしてございます」
「わしは、ふじ。お前一人で存分ぞ」
「所領を守るは武将の常。世継ぎが無うてはお家が絶え、殿を慕う
て住む領民の暮らし向きが不安になりまする」
「じゃとて」
「娘ごは、家老の清野殿の……」
「なに? 勝左衛門の娘か?」
「二女のきよ女と申しまする」
「なんと……きよ、あの、きよか?」
行時の手が止まった。日頃から気にしている娘の名を言われ言葉を失ったのだ。
新年の茶会で見る大輪の花一つ。きよは一年一年華やかに蕾を開いていた。
幼い頃から花見の宴にも母と共に連れ立って見えている。幼い頃から人一倍目立つ娘だった。
「あちこちから縁談が殺到していて、わしも再三勝左に良縁を持ち込んでおるぞ」
「承知しております。先年長女のうめ女が深志に嫁いだ後、次女のきよ女には近隣の武士達からのみならず遠く西国からも縁談が殿の許に届き、その都度殿が清野殿を呼ばれて談合されていることも存じております」
「ならば、余分な口出し無用。わしには三国一の誉れ高いそちが居るではないか」
「それが。殿の口添えの良縁が数を重ねるにも関わらず娘のふじ女が心動かぬ理由を両親が問うたところ……」
「いかがした?」
「白駒の殿のようなお方に、と」
「愚なことを」
「真実,そのことをお聞きして私も驚きましたが、母のよし殿とご一緒に会うて聞くところによると、私が嫁いだ頃から殿を恋い慕っ
ていると申しておりました」
「その頃はまだ十歳にもならぬ幼な子ぞ」
「殿ごを好くのに年齢はございません。きよ女なれば良きお子に恵まれましょう」
「されど、そちが居るというに‥」
「容貌よき妻妾を持つは武将の甲斐性。私は充分殿の寵を受けて満たされております。ただひたすら子を授からぬ身が申し訳なく思うておりました。清野殿の娘ごなれば私も安心して喜び迎えることが出来まする」
そこで会話が絶え、ふじ女の喘ぎが続いた。
行時の情愛が生命を取り戻していた。
その後、ふじ女の積極的な勧めによりきよ女が白駒の城に入った。きよ十六歳の春だった。
側妻とは思えない堂々の輿入れで華やかな晴れの舞台を飾ることができたのも、正妻ふじの配慮によるものだった。清野一族をはじめ当のきよ女の感激もひとしおで、これを知った人々をも感動させ噂は噂を呼び、この話題は京や鎌倉にも聞こえたという。
再三縁談を申し入れ断れた血気盛んな若い武将の一人は口惜しさから語った。
「戦国の世なれば、攻め入って奪い取ろうものを」
それから三年、一女を産んだ後のきよの美しさはますます磨きがかかり、天下一の果報者といわれた樋口行時もまた男盛り、一族の武将と共に騎馬を走らせ山野を駆け一朝事ある時のために武技を磨いた。
正応二年二月生まれの女児には、行時の一字をとりユキと名付け、正妻ふじも我が子のように可愛がる。ユキも母二人かのように懐いて甘えてのびやかに育ち三歳になる。
花の宴でも久方ぶりに一族近隣の幼子達と遊びはしゃぎ、ユキは周囲の寵愛を一身に浴びてあちこちから名を呼ばれ元気に愛くるしい声で応じ、さらに人気を集めていた。
それを二人の美しい母がおだやかな笑顔で見守っていた。
正妻のふじ女は敷物ごとに賑わっている各家族の人群れに万遍なく声をかけ花の宴をいやが上にも華やかな楽しいものに盛り上げていた。
きよ女は動かず挨拶を笑顔で返し楽しげに周囲の若い娘達と笑いざわめいていた。
きよ女が座を動かず酒杯も傾けないのには理由があった。二人目の胎児を宿っていたのである。少しお腹が出てからも熟女の艶麗さが輝く。
「今度は男だ。間違いない」
行時が断言していた。
初産の女児を当てているだけに行時の一言は重みを持っていたし家臣達の願いも同じだった。
周囲が必要以上に気遣うため、きよ女は好きなように動けなかった。座をめぐり酌をしたくても許されない。幼女の駆けるのを追うことも出来ない。
懐妊数カ月時折寄せる吐き気にも耐え、笑顔を絶やさないでいるきよ女の許に寄った武士達も腰を低めて形式だけの杯を持ち交わる替わる立ち寄り、その麗しい顔だちを眺め鼻の下を長くして、一層酔いを深めるのだった。
「これで寿命が五年は伸び申した」
「ますます白駒の殿が憎うなりましたぞ」
「いやあ。わしもも一人子が欲しいなった」
「子じゃあるまい。娘が欲しいのじゃろ」
午後の陽が少しかげると風が出た。
子供達も遊び飽きたのか、それぞれ母の許へ戻り甘え、空腹を満たすため食についたり、まどろみの時を得ていた。
ユキも足許をふらふらさせながら母の許へ戻ろうとしたが、まだ幼い身でどう歩いていいのかの判断はつかない。正妻ふじ女や武将の妻女達の宴席に走り込み、重ね箱や酒杯を蹴散らした。煮物や菜や酒が女房達の晴れ着に散乱した。
悲鳴が起こった。一斉に皆が振り向く。
「こらっ。いかんぞ!」
行時が思わず大声を上げた。
目に入れても痛くないほど可愛い我が子を怒鳴るなどついぞないことだった。あり得る筈もなかった。しかし、怒声は確かに行時の口を衝いたのだ。
驚いたのは幼児のユキだった。生まれて初めて叱られた恐ろしさに動転したのか。
「アーン!」と、泣くや敷き物から走り出て戸張橋の方角に小走りに逃げた。
「いけません。あぶないですよっ!」
きよ女とふじ女が、同時に席を立ち白足袋のまま衣の裾を乱したのも気にせずに必死の形相でユキを追う。
誰もが動こうとして動けない瞬時の出来事だった。それでも、一瞬の間をおいて行時も走り家来が続いた。
遅かった。一瞬、橋の際から三人の姿が消えた。
橋の手前でユキに追いつきながら、間に合わなかった。体勢を立て直す間もなかったのか。きよ女の袂をしっかりと掴みながらもひきづられつようにふじ女も姿を消した。
「落ちたのか!」
行時はじめ宴の席から駆け寄って一同が見たものは、満開の山桜が断崖をおおう谷間をゆっくりと舞って行く二人の美女と一人の幼児の姿だった。谷間に大輪の花が舞って落ちて行く。
ふじ女の衣は、緞子織の透き通るような淡い藍地に桃の花が鮮やかに浮いていて、その横に孔雀が一羽描かれていた。
きよ女は、唐織の赤地熨斗の友禅に鶴と牡丹が染め抜かれた衣だった。鳥の鳴く音にも似た悲鳴が谷間に谺する。落ちてゆく二人の美女の襦袢と足の白さが眩しく、谷を覗く者達の視界を奪った。
折からの風が谷間の桜を散らし、花びらに包まれた三人の姿は、声もなく立ちつくす一同の視界に鮮烈な幻影を残してそこ知れぬ谷間の奥深く吸い込まれて消えた。
狂乱状態で橋から飛ぼうとする行時を家来が必死で抱き止め悪夢と変わった花の宴は終わった。
あの日からすでに四十年余の歳月が過ぎている。とうに忘れ去られた遠い出来事でもあった。その伝説の主が三郎盛高の目の前にいる。
三郎は手で目をこすった。
「白駒の殿がご出家されお堂を建立され、その後、家老にお譲りになった城を訪ねた帰路戸張橋から身を投げられたと父より聞き及んでおり申した。殿がご存命とは祝着至極、お陰をもって主従二人生命を救けられ、こうして美酒に喉を鳴らして五臓六腑まで生き返ってござる」
三郎盛高はあえて行知法師の過ぎし日を尋ねる気はないが、父が話した言葉の響きは忘れない。
「美しき女人を娶るは身の破滅よのう」
美しい妻妾と愛児を失った白駒の殿は生きる気力を失い、城を捨て出家し三人の供養の寺を建て朝晩拝み暮らした末、後を追い谷に落ちたと聞いたが、それは真実ではなかったのか。
三郎は、恐ろしい物でも見るように法師の横顔を凝視した。
六、幻視幻聴
森で梟が三声鳴くと、法師が手を口に当て二声鳴いた。
「焚き火を消しますぞ。手伝って下され」
三郎と亀寿丸は、事情は呑み込めぬも只ならぬ気配を察し小砂利を積み火を消すのに手を貸す。法師は破れ衣を脱ぎ瀬に浸し、それを焚き火に被せた。火は音を立てて消え、闇がおとずれた。法師の姿も消えた。
「お二人は、その橋桁の下の奥で藁に潜ってご見聞なされ。手出しはおろか声を出すこともなりませぬぞ!」
その声は低く強く、絶対という稟とした響きで三郎の腹の底に響いた。
三郎の背筋をぞくぞくと寒気が走った。火が消えると山谷の夜は寒い。雨は小降りになっている。あちこちで喚声が沸いた。
追手と、追手を阻む者達が闘っているのか。
遠くから法螺貝が鳴り響き人馬の駆ける音が聞こえる。それは幻聴のようでもあったが確かに近付いている。
三郎は酔いがまわったのを感じた。日頃は酒豪をもって鳴る三郎盛高といえども三昼夜も食わず眠らずで過ごした身では、少量の酒でも眠りに誘われるのは止むを得ない。身体が重くなったのか動こうとしても動けかない。
瀬音が遠のき、軍馬のいななきが聞こえる。
「そんな馬鹿な……」
声は出ない。
どこか遠くで三郎を呼ぶ声がする。
「やあやあ、諏訪の三郎盛高! いずこにありや。千種の太郎。一騎討ち所望ぞ!」
「おう!三郎盛高、これにあり」
三郎盛高は藁の中でわが耳を疑った。千種の太郎とは旧知の仲だが、確かに馬上で剣を振るいつつ叫んだのは、紛れもなく三郎盛高その人、自分に間違いないのだ。
三郎は闇の中で目をこらした。
亀寿丸は寝息を立てて眠っている。
流れの彼方に戦闘が見える。河原の右方に山が霞んで見え、谷間の道を人馬が駆けている。刀槍がきらめき、矢が飛び交う。
「あっ!」
三郎は声にならぬ声を上げた。
見覚えのある地形だった。攻防ところを変え三郎は鎌倉に攻め入っている。
鷲峰山の山裾を抜けて巨福呂坂の切り通しに敵味方がひしめき合い一進一退の攻防を繰り返している。
その様子が朧に霞んで見えた。
赤草縅の鎧に鍬形兜の若武者が葦毛の馬にまたがり大刀を振るい雑兵を斬り倒した。頬当ての隙間から顔が見えた。亀寿丸に間違いない。なんと雄々しい姿だ。
その横で三郎盛高と覚しき武将が、千種と名乗った武士と闘い、馬上で組み打ちとなり落馬し鎧通しで敵を刺し刀をとり直して首を掻いた。三郎が立ち上がり大音声で叫ぶ。
「諏訪の三郎盛高、足利方の将・千種の太郎孝明の首をば討ち取ったり!」
(足利? 高氏のことか? 新田ではなく、あの足利高氏が鎌倉で采配を?)
諏訪方の若武者に武将が襲いかかる。
「北条殿の遺子・亀寿丸こと相模の二郎時行殿とお見受けしてござるが……相違なきか!」
(ああ、そうか。亀寿さまは時行と名乗るのか)
若武者が武将を倒し、攻める側は雪崩を打って鎌倉に駆け入った。火が放たれた。かつて北条一族が枕を並べて果て滅び陥ちた鎌倉は荒廃したままだったが、再び戦禍に襲われた住み人は右に左に逃げ惑い馬のひずめに蹴散らされている。~ 極楽寺坂方面から攻め入った海野党一族が敵を破ったのか、鎌倉
に入り勝鬨を上げているのが騒乱の中から響いて来る。独特の声の延びる雄叫びだった。
鎌倉は南に相模の海路を封じれば、三方を山で囲まれた要害の地であり、稲村崎寄りからみると山を切り開いた極楽寺、大仏坂、化粧坂、亀ケ谷、巨福呂(小袋)谷、朝比奈、名越谷の七ケ所の切り通しを固めれば鬼神といえども入ることは不可能な天然の城塞だったはずだが、すでにその神話も消えている。
新田軍は、海辺から攻めて鎌倉を陥としたが、今、亀寿丸を大将とした軍勢は、堂々と柏尾から長沼を経て山之内郷から一直線に守備の固い巨服呂坂を攻撃し、鎌倉に入っていた。
(勝った!)
三郎は目を見開いて対岸の岸辺に拡がる光景を一瞬たりとも見逃すまいと目を見開き、走馬灯のように移り行く修羅の光景を見守っていた。血生臭い風で呼吸が苦しい。
敵の将が引き出され首を刎ねられている。
床上にどっかと腰を下ろした総大将相模守時行のまだ幼い顔立ちが凛凛しい。
だが、その傍らで仁王立ちになって采配を振るっている三郎盛高の顔に生気がない。
並いる諸将を見渡すと、弟の頼継をはじめ、船山、坂木、保科、四宮の各将が猛々しい顔を列ねているがどの顔にも死相が現れている。皆一様に影がうすいのだ。
(勝ち戦さなのにどうしたことだ……?)
地獄の底からでも這い上がって来るような低い嗄れ声が、陰を含んで三郎の耳元に囁く。
「三郎。この先は見ぬがよい。目を閉じよ。決して目を開くでないぞ」
この世のものとも思えない重苦しい声だが、まさしく行知法師の声に違いなかった。
三郎盛高は目を閉じた。すべての景色が消え、真の闇がおとずれた。
暫しの間を置いて、再び鬨の声が上がった。
木橋にはじける雨の音、瀬音にまじって再び激戦が間近に聞こえ始める。戦闘の場は対岸の岸辺から川を走る人馬の叫びと剣の触れ合う鋭い金属音、肉を断つ重い気合い、悲鳴、重なり合って組み討つ敵味方の怒号。小石が撥ね、騎馬が跳ねた川瀬の水が三郎の頬を濡らした。地の底から再び法師の声が響いた。
「三郎。よく聞くがよい。
北条の天下九代百五十余年。盛者必衰が理なればもはや命運は尽きたるものを、己れが野望を捨てかね、年端もいかぬ幼君を擁して諸国の兵を動かし鎌倉攻めとは愚かなこと。一時の勝利の雄叫びも次なる敗北には露と消えるのみ。その末路は哀れなるかな。
鎌倉を落とした新田義貞は足利に討たれ、世は高氏の天下になる。その足利も何れは滅びる運命ぞ。三郎。要らぬ野心を捨てよ」
法師の声が絶えた。続々と軍馬の嘶きが崖道を駆け木橋に蹄の響きが烈しい音を立て通り過ぎ、矢を放つ鋭い絃音と風を切る矢音が間断なく宙を飛んだ。馬上から人の落ちる音、それに群がる雑兵、それを蹴散らす騎馬の将、攻守入れ替わり勝敗はいつ果てるともなく続いた。三郎の耳も頭も戦闘に飽いた。
(もういい。もうやめろっ!)
「ハッハッハッハッ‥‥」
笑い声が闇を飛び遠退いて行く。それは夜鳥の羽音のようでもあった。戦いが止んだ。 闇を透かして横を見る。亀寿丸は幼い身に辛く苦しい逃亡の道がよほど堪えていたのであろう。安堵したように深い寝息をたてている。雨の音が穏やかになり、瀬音に混じって虫の音が騒がしい。
三郎盛高もやがて睡魔に襲われ、いつの間にか眠りに入っていたが、快い眠りというよりは、死出の旅に引き込まれるような恐ろしい眠りだった。
一刻ほどは眠ったのか。あるいは眠りの中で聞こえているのだろうか。人声がする。
「ささ、寒かろう。こちらへ来られよ」
老人の声が聞こえる。行知法師のようだ。
目を開くと落武者が二人、もはや武人の体もなく髪は乱れ武具も胴だけで直垂も兜もない。三十前後の武士が杖替わりに持つシゲ藤の矢の太さと巻き糸から名のある武将と判別がつく。闇をすかして横顔を見つめる。
(どうした手塚の頼重‥‥なんとしたのだ?)
諏訪下社の社人の手塚太郎光盛の子孫として三郎と並ぶ弓馬の達人である。
頼重は疲れ切った様子で背から切斑の羽の揃った矢が十本程残った箙を背から降ろし、どっかと石に腰を下ろした。足から血が滲んでいる。草鞋はすでになく素足が痛々しい。(その顔はなんだ。急に老けおって) 陰になってもう一人の若者の顔がよく見えない。
どうも、よく事態が呑み込めない。
行知法師が寝ている三郎の身体に触れんばかりに近付いて藁の中をまさぐって油紙の包みを取り出し、付け木と乾いた藁を重ね石を叩き火を点けた。闇の中に人の顔が浮かんだ。
焚き火に凍えた手をかざし暖をとりながら唇を噛みしめ無言で嗚咽を堪えている若者は紛れもなく、この藁の中でねむっている亀寿丸こと相模二郎時行だった。
雑兵に化けて逃げたのか足軽胴に持ち慣れない槍を手許に投げ出している。腰の差し物も粗末な茶鞘もの、黄金造りの大将太刀はどこにも見当たらない。
これだと落武者どころか、稼ぎのわるい野伏の親子としか見えないから誰も襲うても来ることもあるまい。
「それにしても口惜しいことよ」
極端な老け込みようの行知法師が、腰を曲げながら酒の入った瓢箪を手渡すと、それをまず亀寿丸こと時行に渡し、つぎに自分も一口喉を鳴らして法師に返しながら誰にともなく吐いた。
「天下盗りもわずか二十日。錦のみ旗を正面に各地に檄をとばして集めた将兵数十万騎。怒濤のごとく荒れ狂って押し寄せた敵で諏訪の三郎殿も大御堂に火を放って自らの生命を絶たれた」
三郎は声もない。自分は自害したのか?
「ご坊……」
亀寿丸が重い口を開いた。顔はまだ童顔だが身体はかなり逞しさを増している。
「一度ならず二度までも世話をかけた。あのときご坊の行時という名を知り、それを用いて時行としたが、武運尽きてこの有り様、面目次第もござらん」
「いや、いや。この世はすべて夢うつつ紙一重。勝つも負けるも生きるも死ぬも、過ぎてしまえば幻のようなもの。人はいのうなっても春が来れば……」
「木々は萌え……」 頼重が呟き、
「小鳥囀り……」 亀寿丸が和し、
三人が同時に叫んで立ち上がった。
「獣は野山を駆けめぐる!」
頼重が刀、法師が太木の杖、亀寿丸が槍を持ち、橋の下の三郎達二人を睨んだ。
目が青白く光り赤黒い口許に牙が光った。獣だった。
三頭の獣は一気に三郎と寝入っている亀寿丸目がけて襲いかかった。三郎の身体が突然呪縛から解かれたように藁の中から刀を振るって躍り上がった。
刀は鞘を走り獣の頼重を刺し、獣の法師の肩先を叩き、返す刀で獣の亀寿丸の腹を裂いた。
「ギャーッ」 悲鳴と同時に焚き火が消えた。
襲って来る敵を本能で倒す武人の習いが窮地を救ったのだ。これが夢なれば余りにも悪い夢だった。
亀寿丸が藁の中で目を覚まし、大きく欠伸をし藁を振るいながら立ち上がった。
「おう。よう寝た。三郎殿も休まれたか?」
三郎が我に返った。やはり夢だったのか。だが、夜目にも刀から滴る血が見える。
「刀など抜いてなんとする?」
「いま、獣を切り申した」
流れで刀を洗い、数度空を切って破れた着衣で水を拭き鞘に収めて空を眺めた。
雨は止んだ。雲が流れ、月がのぞいた。
行知法師の姿もない。
焚き火の跡がくすぶっている。三郎達が暖をとったままの火種が残っていたのか。
二人は石に腰を下ろし藁と枝木をくべた。
七、運命
静かな夜である。
雲が切れ上弦の月が姿を現した。
河原に群生する雑草の葉ずれの音、草むらの虫の音、雨で増水した川の瀬音、野鳥の羽音、遠くで尾を引いて仲間を呼ぶ山犬の声、それでも静かな夜だった。
剣と剣が打ち合う音、甲冑の擦れる音がないだけでも充分に静かなのだ。
まだ雨が乾いていないのか、河原の石が濡れて光った。
よく見ると、石を濡らすのは血痕で、それは足許の石から瀬まで続いている。
「この血は?」
亀寿丸が、周囲を見まわしながら言葉を継いだ。
「法師はどうされた?」
そして、亀寿丸は三郎盛高の顔を恐ろしいものでも見るような目で凝視した。
「斬ったのか? 法師を……」
三郎盛高は返事に窮した。
自分が斬ったのは、獣とも人ともいえないし、夢と現実すら定かではない。
「何故に、あの恩人である僧を斬らねばならなかったのだ?」
亀寿丸は怒った。絶体絶命の窮地から救われ一夜の夜と暖をとる火や酒までも振るまわれたのに斬殺するとは何たる非常な仕打ちなのか。
「物の怪だったのでござる」
確たる証拠を持たぬ三郎が、不安気に口ごもりながら答えた。
「物の怪? ならば、これは何とする?」
亀寿丸が足許の瓢箪を手にし、耳元に当てて振り、栓を抜くと口に当てて濁り酒を一気に飲んだ。
幼いと思っていた亀寿丸が人が変わったように元気を取り戻している。
三郎が瓢箪を受け取り、疑わそうに匂いを嗅ぎ、要心しながら口に含んだ。強い刺激が鼻をつく。しかし、まぎれもなく濁り酒の香りだった。
「これは確かに酒だ」
「三郎殿、少しお気が変になられたか?」
「いや、正気のつもりではあるが……」
自信はない。なにやら頭の芯が重いような気もする。
遠くで梟が続けて五声啼いた。
すると、橋を渡りながら誰かが梟を真似て啼いた。あちこちで梟の声がとび交い、その声が遠のいた。足音は行知法師だった。
草を分ける音がして土手を降り法師が戻った。手に裏返した破れ笠を持っている。
笠の内には芋や干した川魚、山采などが積まれていた。
「眠れましたかな?」
行知法師は、刀の柄を握り睨み据えるような目付きで自分を見つめている三郎盛高を怪訝な表情で眺めたが、屈託なく持参した食物を火にかざした。
「法師、どこへ行かれたのだ? あの梟の啼き声は誰が?」
「ああ、梟は山の人の挨拶じゃ……」
「山の人? 山窩か?」
「今のは別れの挨拶でお互いの健康と再会を約したものじゃが、彼らは夜の内に山を移るでのう」
「先刻、法師を招いた啼き声は?」
「ああ。あれはお二人に追手がかかったのを山の人が知らせてくれて、防いだのだ」
「亀寿さまを存じておるのか?」
「いや。三郎殿を慕っている者達で南信濃の山を棲家としている者共が、こたびの乱で一働きするつもりで甲斐まで来たところ、諏訪の若殿が執権のお子を伴われて落ちるのを見て、お守りする気になったようじゃ」
「なんと?」
「この山に二人ほど残したそうじゃから、もう諏訪までの道程は安全とみてよろしゅうござるな」
「そうか……そうであったか」
「さてと、話はこれまで。さぞ腹も空きなさったろう。山の人からの差し入れじゃ。さ、たんと食べなされ」
「重ね重ね有難きこと。今は何の礼もできぬのが面目ない」
「なんの。先刻、この辺りから流れ落ちた深手の狢(むじな)を三つも拾うて大喜びで帰りましたが、見事な太刀捌きを諏訪さまに違いないと言うておりましたぞ」
「むじなか?」
法師が屈み、血塗られた石間に目を凝らし手を伸ばすと、その手を三郎の顔先に突き出した。指先の長い銀毛に血が見える。
「これは確かに狢じゃが、かなり年老いていて肉は硬かろう。酒の香に誘われたか?」
「むじなか?」
再度呟いて三郎は法師を見た。
「老いたむじなは人を誑かすか?」
「狢に誑かされましたかな?」
「なにか、見えない筈の幻を見せられたのだ」
「ほう。それはまた希有なこと。して、どのような?」
「わしらが鎌倉を攻め落とす」
亀寿丸が焼いた芋を食す手を休め、目を見開いた。
「三郎どの。私もその夢見ましたぞ」
「亀寿さまもか?」
「今日、われらを追い落とした新田は足利に敗れ、その残党も組して関東各地から軍を集め政務定まらぬ鎌倉を一気に攻め取った」
「して、その後はいかに?」
「幕府再興の人選や褒賞で揉めごとが続いている間に、足利を将としてわれら討伐の勅命が降り雲霞の如き大軍が押し寄せ……」
「殲滅されますかな」と、法師が呟く。
「そして、亀寿さまは再び落ち延び、それがしは一族郎党と共に戦火の中に果てる」
三郎が宙を見つめて探るように続けた。
「しかも、敵に見分けられぬように面皮を剥いで腹かっ切り堂に火を点け、燃え落ちる」
「その数、同行百四十余人、場所は鎌倉八幡宮大御堂……」
老僧が見たように呟く。
「法師。なぜそれを?」
「年老いたら人もむじなも一緒でござる。人は誰でも不安が心の臓に迫ると悪い夢を見、枯れ雑木も妖怪変化と見違えるもの、悪い夢はえてして正夢となるもの。現に今も……」
「今も?」
「とうの昔に谷に落ち地獄に堕ちた行知と語り明かしているではないか」
「なんと?法師は生き霊なるか?」
「浄土では死ぬも生きるも一場の夢、己れが死ぬと思えば死に、生きると思えば生きる。恐れず運命のままに進むのみ」
「ならば、今しがた垣間見し幻影は運命と申されるか?」
「さよう。その運命を変えるのも人の心」
「いかように?」
「そちらの若君の心の内は震えおののき、戦い傷つき殺される運命を恐れてござる。されば、運命に逆らって山へ逃げ、山窩と暮らすも一つの道。望まれれば喜んで案内しましょうぞ」
亀寿丸が立ち上がり刀を抜いた。
「妖怪めっ。わしを臆病だと申すのか!」
太刀風鋭く真っ向から刀を振り下ろす。
頭を割られ血煙り上げて倒れ伏す筈の法師の姿がそのまま残り、何事もなかったように薪き火に新木を焼べながら煙に咽って咳込んだ。刀は石を打ち火花が散った。
刀を手に亀寿丸は立ったまま茫然と法師を見つめている。三郎も奇妙なものでも見るような目付きで行知法師の皺の多い顔をじっと見ている。
法師が顔を上げ微笑んだ。
「死ぬも生きるも過ぎてしまえば一場の夢。運命じゃ」
法師の姿がうすれて行く。
法師の姿の向こう側の景色がうっすらと明るくなった月景色の河原を映している。
「運命じゃ。運命なのじゃ……」
声が残り、姿が消えた。
河原に咲く小さな白い花が風にそよぎ、瀬音にまじってカジカの澄んだ声、虫の音などが聞こえる。
やはり行知法師は、とうの昔に死んだ人だったのか?
老いた梟が,二人をあざ笑うかのように二声ほど啼き、羽音を残して遠のいて行った……。
了