狩 野 川 慕 情
花見 正樹
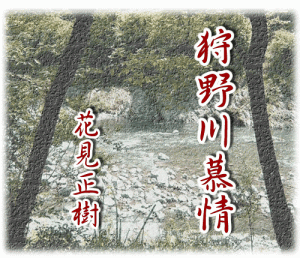
一 川漁師
昭和三十三年、つい昨日のようでもある。
真夏の遅い午後、日射しはまだ強烈だった。
「ほら、雑魚がいっぱい上がって来てるぞ。見てみろ!」
膝の上までズボンをまくり上げて川に入って川底を覗いていた増田敬一が、岸辺で握り飯を口にしている仲間に声をかけた。
陽に焼けた額に絆創膏を貼った痛々しい顔が嬉しそうにほころび、目が少年のように無邪気に輝いている。
額の傷は、十日ほど前の七月二十二日に伊豆地方を襲った台風十一号のために危険に晒されていた何人もの村人の命を救った際、家屋の倒壊に遭遇して受けた名誉の傷でカギ形に八針も縫ったが、痛む素振りも見せていない。
敬一は、三島の高校を卒業後、公務員試験を受け、地元の大仁町役場に勤めていた。住居は白山堂地区にある。
台風に際しては、官民一体になっての必死の活動によって被害者は最小限に食い止められた。とはいっても、彼等が腰を下ろしている土手の上流に見える神島橋の無残な姿を見れば、この狩野川流域を襲った台風の凄まじさは一目瞭然。橋脚の一部だけが残っていて、河原は上流から流れ落ちた土砂で埋まり、岸辺の雑草や灌木もなぎ倒されたまま灼けつくような真夏の太陽の下に眠っている。
それでも、緑を失うことなく力強く起き上がりつつある草木もあるのが救いになる。
この季節に一度落ちた鮎は、上流からは姿を消すがこの辺りまでは戻ってくる。
「敬一が呼んでるぞ」
勝村新吾が、湯飲み茶碗を口から離し、くぐもった声で隣の輝夫をみた。例年、台風の後は鮎も激減する。そのわずかな鮎が見えたのか。
飯島輝夫は口を動かしながら首を振った。彼はまだ食べ足りない様子だった。
輝夫が動かないのを見て、勝村新吾が「どれどれ」と呟き、飲みかけの酒を干し、茶碗を傍にいた敬一の妹加代に渡して立ち上がった。
気温で熱燗になった酒のためか足元がふらついている。酒に強くてもこの暑さでは酔うのも無理はない。
「新吾さん、気をつけて……」
加代が危ぶむのは新吾も膝を痛めているからだ。彼は、大仁町内の消防分署に勤めている。
輝夫ら三人は、地元の大仁中の同窓生で高校からは別の道を歩んだ仲間だが、休日にはこうして一緒に顔を合わせ、酒をくみ交わし、いつも加代が食事の差し入れをする。
輝夫は、東京の大学を卒業し故郷にUターン、長岡南小学校の教師をして二年ほどになる。ようやく教師の仕事にも慣れてきた。
二十六歳という結婚適齢期の三人にとって、多感な青春を語り合える親友の存在は頼もしい。しかも、増田敬一の妹加代は、本人の辞退で実現はしなかったが、伊豆の観光協会から観光ポスターのモデルにと推薦されたこともあるほどの美人であるだけに、輝夫と新吾は敬一以上にその妹加代との逢う瀬を楽しみにしていた。
加代は兄の敬一達より四つ下の二十二歳、三島市内の短大卒業後、長岡の園芸農場に勤め二年になる。縁談も十件近く舞い込んでいた。しかし、加代は全く興味を示さない。
敬一と新吾は川に入って鮎を見つけては騒いでいる。いくつになっても、水遊びをすれば童心に戻れるのだ。
土手の斜面に足を投げ出して並んだ輝夫と加代が、笑顔で川を眺めている。緑の山々が真夏の青空に映え、蝉の声が川原の灌木に騒がしい。
加代が手に持った日傘を輝夫の頭上に傾けた。自然に二人は接近するかたちになる。
「輝夫さん、これだけ水が増えて川かんじょう、できるの?」
「やるさ。子供たちは元気だぞ。台風で何日か遅れたが、盛大に祭り上げるんだ」
「じゃ、精霊流しもやるのね」
加代は、兄の友人である二人に、小学生の頃から兄以上の親しみで甘えて来た。
川かんじょうとは、八月の始めの数日間の夜、麦わらで作った筏の上に太い松明を立てて火を点け狩野川に流すこの地方に伝わるお盆の風習だった。三メートル四方の四角な竹の筏の中心に、高さ約六メートルの竹の松明を立て川に流すと、星を散りばめた夏の夜空を赤々と染めて炎が川を下って行く。
伊豆半島の中央を流れる大動脈の狩野川の氾濫は、川に沿って暮らす人々にとって時には致命的な痛手を負わすこともある。川かんじょうは、川を静める祭りなのだ。
村の長老の話だと、大正九年の洪水では七メートル近くも上がった水位のために堤防が決壊し、この川沿いの大仁の町は、湖のように水の中に沈んだという。その時の多くの犠牲者を弔う慰霊碑が橋のたもとにも立っている。
「あら、セドのジサマが……」
土手に姿を現した老人が、輝夫と加代の姿を見て、なんだか嬉しそうに顔をしわだらけにして歯を出して笑った。
「テルオ。カヨ坊とデエトかい?」
「違うよ。そんなんじゃねえってば……」
「ほう、じゃあ、なんだ? 顔赤くして」
「川かんじょう出来るかどうか、見に来ただけだ。ジサマ、鮎は戻ってるのか?」
「十日もすりゃ、苔もつくし隠れてた鮎も出てくるだ。大水のあとは腹へらしてるでな。ただ、砂利っ腹の水ぶくれ鮎だから注文分しか掛けねえ、まずくってな」
日頃よたよたと腰を曲げて村内の道を歩いている七十を越す老人が、篭と竿を担いで土手下の竹藪を抜け、淵の上の瀬脇の河原に荷物を置き、川に入り大石まわりのハミ跡を丹念に調べてからのんびりと支度を始めた。まず、オトリをとるらしい。
継ぎ目にブリキを巻いて継いだ手づくりの竹竿で瀬を引くと、穂先がしなり、獲物の鮎が銀色の輝きを見せて舞った。
ゴロ引きで仕止めた鮎を、丸いブリキ製のイケス缶に入れて川に沈め、仕掛けを替えてから缶の中の鮎を出し鼻環を通すと、すばやい動作で瀬尻の石裏にオトリを泳がせ、そのままジサマも川の中にゆっくりと踏み込んでゆく。穂先が少し揺れ、竿が弓なりになる。
ジサマが竿を立ててゆっくりと下流に動いた。
「オッ。もうかかってる!」 敬一達が驚く。
村の長老でもある職漁師のジサマに遠慮して川から上がった敬一と新吾が、土手上の輝夫と加代を手招きして場所を移った。
ジサマは腰を沈め、竿を担ぐようにして糸をたぐると、ごく自然の動作で手網に二つの鮎を落とし込む。
それからは少し移動しながら、同じ動作を寸分の狂いもなく繰り返して、無駄がない。
「あのジサマ達は、普通の人の給料の四倍以上稼ぐそうだぞ」
ジサマの立ち込む瀬から少し離れた河原に腰を下ろした仲間に敬一が話しかけた。
「オレも転職すっかな」
輝夫が応じると、敬一が笑った。
「とんでもねえ、輝夫じゃ十分の一も釣れねえぞ」
「なんで、そんなに違うんだ?」
輝夫が反発し、敬一が鼻で笑う。
「腕さ」
「腕? 腕ったって、たかが鮎だべが?」
「たかがだと? 鮎をなめるなよ」
対岸の田京側で、深沢川の流れ込みの下の荒瀬脇にまた一人、篭を担いだ男が入った。セドのジサマも、それに気付いて手を上げると、対岸に入った釣り人も下手の方で手を上げ、なにか叫んで挨拶するのが見えた。
「あれは、オレの村のトメさんだな」
「白山堂のか? どうして分かる?」
輝夫の質問に敬一が応じる。
「鮎漁で暮らしてる人は、今は十人ほどに減っちまってるけど、縄張りはきまってる。あの瀬からは、トメさんの場所だからだ」
その漁師はオトリを持参したらしく、すぐ追い鮎を掛けた。
壊れた神島橋の上手の田京側にも、一人の職漁師が入るのが見えた。
「あそこは、ムラタのオヤジさんだな」
まるで申し合せでもしたように職漁師は同時刻に川に入る。
台風後の高水が去って水が澄み、石に苔が付き始めると、岩陰や岸辺に身を隠していたり、一度下流に落ちた鮎が戻り、付き始めた新苔を争って喰む。いい鮎とはいえないが料亭から注文を受けている職漁師はそれを逃さない。
縄張りを必死で守ろうとしてどの石からも追い星の鮮やかな大型の鮎が掛かって来る。
ひとしきり鮎を掛けて、セドのジサマは水から上がった。オトリも引き舟の中の鮎も、岸近くで手綱にあけ、缶に入れ替える。
「すげえなあ!」
近寄ってのぞき込んだ輝夫たちが感嘆の声を上げた。小一時間の間に入れ掛かりで釣り上げた型揃いの鮎が数十、手網の柄を曲げてひしめいている。
「驚くこたあねえ。大水の後はこれが当たりめえだ。だが、大味で食えたもんじゃねえ。でもな、チラシに、狩野川の鮎をうたってる宿もあるで仕方ねえだ」
ニコリともせずセドのジサマが手際よく鮎を移し、缶を水中に沈め石を乗せてから、若者たちの顔を眺め、手を出した。
「タバコあるか?」
軍隊用の水筒から水を一口飲んでから、輝夫の出したタバコを口にくわえ、両手で風よけをしながら敬一の出すマッチの火を受け、うまそうに煙を吐く。
「そっちの若い衆は、よく見かけるけど田京かえ?」
「いや、白山堂です」
「ほう、あすこで漁やってるトメさんと同じか?」
「ええ、多福院の裏手でトメジサマの家からは百メートルほど離れたところです」
「なめえは?」
「増田敬一といいます」
「亡くなった平助さんとこのか?」
「平助は、ウチのジイサマです」
「そうか。平助さんとこのニイちゃんか」
「ジイサマを知ってる?」
「田中の尋常小学校二つ上で、よく遊んだり叱られたりしたもんだが、奉天第三師団に入隊して旅順へ派遣されたらな、平助さんが上官について、ずい分と助けてもらっただ」
「えらい昔の話ですね」
「そりゃそうだ。駿豆電気鉄道が開通して伊豆醸造が出来たあと、川の決壊で何十人も死んだのも見たしな。城山の石を切り出して江間の用水堰に使うことで、この神島と江間村で大ゲンカが続いたもんだ。オレらぐらいの歳になればな、いろんなことを体験するもんだぞ」
「ジイサマもよく江間堰の話をしてたです。二七〇年以上もの昔の江戸時代に城山の石を使って高さ三メートル、長さ一八〇メートル、流れに向かっての上下幅は十八メートルだったそうですね?
これで水位が上がった狩野川は、長岡、古奈から一里以上の水路を通って江間の田畑を潤して農家の苦難を救ったとか……」
「だけどな。それから堰をめぐる争いが続いたのさ。石争いより、台風が来る度に水が出るようになってな。堰がなきゃ江間が困るが、堰がコンクリートで高くしてから長雨の度に堰上の村は水浸しだ。こないだの洪水だって前の堰なら石が崩れて流れが落ちるから、神島橋だって壊れるこたあなかったんだ」
「また、大水がでるかしら」 加代が聞く。
「ああ、九月は毎年台風が通るべさ」
ジサマは立ち上がりながら振り向いた。
「鮎掛け覚えたきゃ、いつでもここさ来い」
「えっ、教えてくれるの!」 輝夫たち男三人の目が輝いた。
「若いおめえらに狩野川の鮎を守ってもらいてえからな」
重くなった荷を背負ってジサマが遠ざかる。
清冽な狩野川の流れに緑の山々が映えた。この美しい自然をいつまで守れるのか。
二 鮎の川
「へえ、テルアニ、釣りを始めるのか?」
五つ違いの弟の昭二が目を見張り、信じられないという顔で輝夫の顔を見て、台所の土間で朝食の支度をしている母親に顔を向けた。父は夜勤でまだ帰らない。
「おっ母さん。テルアニがあんなに嫌ってた釣りを始めるんだと。
雨でも降んなきゃいいがなあ」
母親の声がすぐ返った。
「雨なんかうんざりだよ。釣りはダメだ。おまえたちのジィちゃんが川漁で亡くなってから、この家は鮎を釣らないことになったの知ってるでしょ…」
輝夫が反論した。
「その話は、オヤジさん止まりにしようや。なにも、ジィちゃんみたいに鮎で稼ごうってんじゃないんだから」
「大水が出るたんびに、川漁をしてた人が流されて死ぬのは、殺生のたたりなのに」
「そんなの迷信だよ。オレと昭二だって、モリで突いてずい分と我が家の食料にしてるはずだぞ」
「そりゃあ、食べれば功徳になるからね」
「なら、職漁師の掛けたのも誰かが食べてるんだからいいんじゃないか?」
「川漁で食べてる人はそれでいいが、あんたは小学校の先生でしょ? 釣りなんかやってる暇あったら子供たち集めて勉強でも教えなさい」
「そんなの誰も喜ばないさ。夏休みぐらいは子供たちもめいっぱい遊びたいのに、週に一回ホームルームで登校させてるのも可哀そうだと思ってるんだ」
「やめればいいのに」と、昭二が口をはさむ。
「そうもいかん。宿題だけじゃない。家庭環境や健康に心配ないのか、とか。それに、子供たちも友達の顔を見られるから、と理屈をつけて登校させたいのがPTAなんだ。生徒も教師もみんな迷惑がってるのにな」
「テルアニは鮎を始めても、夏休み中釣りができるからいいな。オレなんか仕事だから。でもな、物置にジィさんの使った物干しみたいなぶっとい継ぎの竹竿いっぱいあるが、あれ全部ダメだぞ」
「なんでだ?」
「実は、オレも鮎掛けしようと思って出してみたら、竹が古すぎててひび割れしてるし、穂先なんか少し曲げただけでポッキリ折れちまう」
「あんたたちな。あれは、おまえたちのジイちゃんの手作りで、鮎竿なんて買うとビックリするほど高いんだよ」
「昭二が買った蓄音機とどっちが高い?」
「そりゃあ、安い竿だってあるさ。母ちゃん大げさなんだよ」
「なら、なんとか買えるな。せっかくセドのジサマが教えてくれるっていうんだから」
「敬一さんや新吾さんもやるのか?」
「敬一は役所だから土曜の午後と日曜の休み。新吾は消防で夜勤もあるし休みは不規則だから、あまり出来ないだろうな。まあ、夏休み中、オレが先に教わることになるかな」
母親が膳の上に二人の朝食を並べた。
父親は夜勤でもうすぐ帰って来る。母はそれから一緒に朝食をとるのだ。その母が懐かしげにいう。
「セドのジサマなら、あたしがこの家へ嫁いでから、よく集まってはうちのジイサマを囲んで飲んでたよ。いつも、仕掛けがどうの竿がどうの、川がどうの、沼津より三島のほうが値が高く売れるなどと川漁のことで夢中だったねえ」
湯気のたつ白いご飯に箸をつけながら昭二が聞く。
「この川は、毎年、八月か九月になると台風にやられて大水が出るから、鮎で稼ぐのは運のいい年の話だけが伝わってるんだね。稼いだとか儲けたとかよく話してたよ」
「で、ジサマは稼いだ?」
「あまり、いい方じゃなかったようだねえ。結局、仕事忘れて大鮎ばかり狙って、自分が深みにはまっちゃったんだから」
「泳げないわけじゃなかったんだろ?」
母が嘆き、昭二が言いなれた疑問を投げる。
「泳ぎは達者だったが、掛けた鮎が惜しいから竿を離せなかったって、オヤジから何十回となく聞かされた、もう聞き飽きたな」と、輝夫がわざとらしくあくびをする。
「そりゃあ、川漁師が自分の商売道具を流したら笑い者にされちゃうでしょう?」
「死んでもか?、バカらしい」
「よほど、大きいのが掛かったか、鈎がなまってたのか、二本鈎の元鈎がのび切ってたというから、竿を立てて引きづり込まれたってえ話も満更ウソじゃないんでしょうね」
母の言葉に二人が笑い、昭二が時計を見た。
「あ、いけねえ。また遅刻しちゃう。毎年、この話を聞く度に、おっ母さんの話まで大ゲサになってくる。いくらジイさんだってプロだろ。プロが川魚に力負けしちゃうなんてあるわけないさ。テルアニも、そんなことよそでしゃべると恥かくだけだぞ」
輝夫が頷き、箸を目の前で立てて見せる。
「そうだよなあ。セドのジサマが掛けてた鮎もいい型だが、こやって竿を立てて少しこらえながら下手へ動いて、それを肩に担いで魚を寄せて、まあ、簡単なことだ。誰だって出来そうなことじゃないか」
「誰だって出来るなら、プロなんていない筈だろ?」
昭二がお茶を飲みながら立ち上がり、母親に叱られる。
「なんだね。行儀がわるい」
「だって。橋が流されたおかげで目と鼻の先の分所まで、自転車でぐるっと大仁橋まわりじゃ、足が丈夫になって競輪選手にもなれるぜ。そうだ、テルアニ、鮎で稼いでオヤジさんにミゼットの中古でも買ってやってくれないかな。バイクじゃ雨の日可哀そうだから」
「いくらするんだ?」
「沼津の自動車屋で働いてる友達に聞いたらまだ中古が出ないけど、八万ぐらい用意しとけば出たときに確保してくれるそうだ」
「八万か、大金だな。昭二、半分出せ」
「冗談いうな。オレの給料、八千円だぞ。四万円もどうやって作るんだ。火事場泥棒でもしろってえのか?」
「分かった。一万でいい、オヤジが一万、オッ母さんがヘソクリから一万、オレが一万、あとの四万を鮎で稼ぐ」
「へっ、本気かよ」
「本気さ。敬一の話だと、ヨボヨボのジサマが給料の四倍なんだぞ。いい若い者が同じぐらいにならなきゃ可笑しいだろが」
「なにいってんだ、素人のくせに……」
「ま、素人だから半分にみて二倍だ、月に二倍で二万、二ヵ月で四万、今期いっぱいでミゼットが買える。いや、ダットサンかな」
「じゃ、予約しちゃうぞ」
「まて昭二、ま、ものには予定というものがある」
「だから何だ?」
「予定はすべてまだ未定だ」
「バカらしい。相手にしてられねえや」
玄関が閉まって、自転車にとび乗って走り去る音がした。
母親が心配そうに輝夫の顔を見る。
「輝夫、あんなこといっていいのかい? 昭二が本気にしちゃうじゃないか」
「いいさ。なんでもね。目標ってものが必要なんだよ。ただ、川が目の前にあって鮎がいるからとか、面白いからとかで釣りをやるんじゃ張り合いがないじゃないか。」
「でも、鮎に凝ったら仕事がおろそかにならないかい? 父さんもきっと反対すると思うけど」
「オレはオレで、この狩野川が大好き、大仁町も好きだ。生まれて育ったこの神島はもっと好きだ。で、両親には大学まで出してもらって感謝してる。でもオレの体の中には、川漁を仕事にしていたジイちゃんの血が流れてる。この狩野川は鮎の川なんだから、鮎を釣るなという方が無理なんだ。しかも、夏休みのほんの短い期間だけなんだから」
「父さんが帰って来てから相談したら……」
「大げさな。たかが鮎掛けだよ」
輝夫は、朝食を済ますとすぐ鮎竿を買うために自転車で町へ向かう。家から近い神島橋は流出していて渡れない。下流の大門橋へ行くのに土手道に上がって川を眺めながら走ることにした。
一日毎に緑が濃くなっている。
八月の猛暑でも朝風は川の冷気を運び、台風の痛手から起き上がった雑草が涼しげに揺れている。
壊れた橋のすぐ下の川原は広場になっていて、神島の子供達や若衆のいい遊び場になり、お盆のころには相撲大会や花火大会をすることもある。
その下側が竹藪になっていて瀬があり淵がある。
その瀬頭の浅い流れの中に、背を丸めて老人が作業をしていた。
よく見るとセドのジサマらしい。川虫でもとっているのか。
輝夫は、自転車を降りて川原に行き、両手を口にあて流れに負けないように大声で叫んだ。
「ジサマー!」
膝上までの流れの中に足を踏ん張って腰を上げたセドのジサマが、朝陽を浴びてまぶしそうに輝夫を見た。なにやら、柄の短い竹ぼうきのようなものを手にしている。
ジサマが、何かを洗う仕草をした。
「なにを洗ってるですか?」
流れを切ってジサマが水から上がった。手が冷たいのかまっ赤になって小さく震えている。しかし、何事もなかったように顔をくしゃくしゃにして嬉しそうに笑った。
「テルオ。学校休みだろ、朝からどこゆくだ?」
「竿を買ってくる」
「なんだ。川漁師だったジイの家に鮎の竿一本もねえのか?」
「古くて使いものになんねえのです」
「手入れしてなきゃ当たりまえだ。そんなこったろうと思った。余った竿持って来てやるぞ。くれるからそれ使え。なにもわざわざ買うこたあねえ。おめえとこのジイさんと一緒に竹をあぶって作った竿だからな。どうせ、仕掛けもねえんだろ? ま、しばらく竿は要らねえがな」
「竿がいらないって?」
「大水が出た後はな。石の上に泥ヌクが被っててな苔がつかねえんだ」
「でも、昨日いっぱい釣ってたじゃないですか?」
「流れのきついところはな、大水で覆われたヌクも何日かすれば表面は流れ落ちてな、いい石は鮎が必死になって泥を剥ぎ取る。そいで、二日もカーッ照れば、珪藻などの水アカが大石の前後から付着して、それを餌にする縄張り鮎が付く」
「その鮎を掛けちゃえば終り?」
「いや、追い鮎を掛けると、その空き家に順番待ちの腹あ空かせたのが待ってましたとばかりに、自分の餌場を確保しようと侵入して来て、またオトリを追ってくれるんだ」
「魚が濃いと、同じ場所で続けて釣れる?」
「そうだ。その石を今、つくってたんだ。テルオたち用のな」
「つくるって?」
「素人用の釣り場だ。いいか、あの上の大石から今、わしが洗っていた石、分かるか? 少し頭のとがったヤツ。あの間十メートルの段々瀬の半分ほどはわしが洗ったが、あとは自分たちでやれよ。泥を落としとけば今日、明日とカンカン照りだと明日の午後は鮎が付く。下の淵の鮎は腹へらして死にそうだからな」
「じゃ、すぐでも釣れる?」
「ダメだ。竿を出せば釣りにはなるが、アカのなめ方でも見て、しばらく、見物だな」
「川原に座って?」
「詩を作るんじゃねえんだ。川原から川の石眺めてたって仕方ねえ。シャツとパンツ一枚で顔だけ潜らせて眺めてろ。平瀬だから流される心配もねえ。そいでワシの鮎掛けでも見てりゃあいいだ」
「鮎の泳ぐのを見るわけ?」
「息の続く限り石につかまって川の中に潜ってな」
「そいで?」
「鮎になったつもりで潜ってれば鮎の動きが分かるからな、あとで役に立つ。それに、今掛けても砂利を飲み込んでて、肝心のワタも食えねえしな」
「ワタが?」
「そうだ。自分で砂利を呑むのか、砂利まじりの泥水を飲んじまうのか、身体を重くして川岸の石裏に隠れてな、ちっとでも流されねえように工夫してるだ。その上、ブヨブヨだからまずくて鮎の味もしねえ。注文だから仕方なく漁してるが、いくら品薄で歓迎されたからって嬉しくもなんともねえ」
「ブヨブヨって?」
「鮎の身が水ぶくれで、ハリ掛かりしてもな。無茶やると身切れしてバレちゃうのが増水時の鮎だ」
「水が少ないと?」
「渇水の鮎は、表面が硬くなっているで、ハリ先をよく研がねえとしっかりと掛からねえだぞ」
「分かった。今日は潜るけど、まだ水が冷たいようで嫌だな」
「始めは、大石の上に腹ばいになってな、顔だけ水に入れて石と鮎でも眺めて暑くなったら石を洗ったり潜ればいい、シャツは背中を焼くから着といた方がいいぞ」
あとは、知らぬ振りでさっさと篭脇に置いた三間半の竹竿を継ぎ、ゆっくりと支度をして川に入った。もう、見向きもしない。
輝夫は、仕方なく大石を抱いて川底を覗いていたが、やがて潜っていた。鮎は彼の存在など無視してアカを喰み、際限なく縄張り争いを繰り返している。彼はもう無我夢中だった。まるで、自分自身が鮎になったようでもあった。
こうして輝夫達の鮎修行の第一歩が始まった。
子供のころから慣れ親しんだこの川も改めて眺めてみると、毎年のごとくに襲って来る台風による洪水の影響を受けてか明らかに流れの形が変わって来ている。
それでも川の水は変わりなかった。岸辺から潜ると水中がパノラマのように広がり、端から端まで見通せるほどに澄みきっていて、ハヤ、鮎、ヤマベなどが群れていた。
それにしても不思議な光景だった。流れに負けないように底石につかまって、じっと息をひそめてジサマの指示する大石裏の巻きだまりを凝視していると、そこには村社会があった。
ボス鮎がいて、おのれの荘園を必死で守り抜こうと胸の追い星を黄金色に染めて侵入者を威嚇し、歯を剥き出し横っ腹に体当たりして追い回している。
その一番のボス鮎の後方で虎視眈々と隙を窺っている数尾の二番鮎は、仲間内でもお互いに牽制しながらも果敢にボスの縄張りに飛び込み、彼が命懸けで守っている餌場の大石にかぶりつき電光石火の早業で良質のアカをかすめ取る。
それをボス鮎が追いまくり、その隙に他の二番鮎が侵入して餌場を荒らす。実に巧妙なたくまざる連携プレイだった。明らかに二番鮎の方がボス鮎より食欲を満たしている。
ボス鮎はますます怒り狂って不法な侵入者を追うことにエネルギーを注ぎすぎて、食事をする間もない。怒りに背びれを震わせたところへ、ふざけたヤツが下手から登場して来る。
生意気にも縄張り内に入ってから上下動して敵意を誘い逃げる素振りもない。下腹部に鼻先から体当たりした瞬間、鋭いハリがガッチリと背に刺さって自由が失せ、暴れながらジサマの手元に引き寄せられてゆく。
その空いた餌場では、たちまち縄張りをめぐるつぎの死闘が始まっている。そしてほどなく、なにが起こったか分からないくらいの自然さで、また序列がきまる。石付きの縄張り鮎がきまると、敗北した鮎が未練気に争いを挑み、後方にウロウロと待機している三番の遊び鮎が二番に昇格する。ジサマはそれを無視し、新たに換えた
オトリの野鮎をつぎの石に誘導する。
ジサマは周囲の石から石へとオトリを泳がせ鮎を拾い、また縄張り争いの落ちついた元の石に戻り、二番から一番に成り上がったボスや二番鮎を釣る。そのシステムには寸分の狂いもない。
輝夫が見ていると、ジサマの放つ刺客は、ただ漫然と縄張りを荒らすだけではなかった。あるときは逃げると見せ、威嚇し、上から下から反転しながら群れ鮎から昇格してくる鮎を挑発して襲い気を出させて掛けまくった。ジサマは、穂先を微妙に操って自由自在にオトリを止めたり泳がせたりしながら、追い気の少なくなった野鮎を挑発し怒らせている。
これは、自分の漁場を熟知しているからこそ出来る技なのか。それとも、自然に身についた技なのか。
それにしても、「鮎は川の虫」とは言いえて妙だった。大水でかなりのダメージを受けたはずなのに、かなり魚影は濃い。
これが、昭和三十三年の狩野川だった。
三 三番だし
九月の二十六日。朝から台風が接近していた。
雨足がかなり強くなっている。
輝夫の家は、狩野川西岸の神島地区にあった。そこは、柱状岩石がそそり立つ標高三四四メートルの城山のふもとにあり、葛城山への登山路にも接している小高い位置にある。しかし、川の暴れ方次第ではここでも危ない。
輝夫は、居ても立ってもいられない思いにかられていた。
台風接近中で休校にはなったが、長岡南小学校の教え子達の家の殆どがこの下流にあり、そこまでは橋を渡らなくても行ける。
それ以上に心配なのは、敬一と加代が住んでいる対岸や下流の白山堂地区のことだった。そこに行くには神島橋が壊れているために、下流の大門橋を渡らねばならないが、そこも壊れている。
伊豆醸造に勤める父親は、昨日からの泊まりで帰宅せず、その工場は対岸の田京にある。大門橋も前の台風でかなり痛んでいて、多分、これ以上の水には持ちこたえられない。
「おっ母さん。オレ、心配だから長岡まで行って来る」
年老いた母親が、いざという時に備えて用意した握り飯を竹皮に包み、黙って輝夫に手渡した。包みが二つ、水筒も二つある。
「分かった。オヤジに届けるのか?」
母親が頷いた。父が心配なのだ。やはり橋は渡ることになる。
(オヤジの会社は食料には困ってないのに)
輝夫は、口には出さずにズックの下げカバンに、それを押し込み、懐中電灯も入れてから母親を見た。
「オレ。もしかしたら夜までに戻れんかも知れんが、ここまでは水は来ないと思うけど、万が一のときは公民館に逃げてくれよな」
「ハイよ」
気丈な母親は、動じた風もなく玄関の土間にある履物を、上がりかまちに敷いたベニヤの上に並べている。横には十匁ローソクとビニールに包んだマッチが大量に置いてある。いかにも、苦労性の母らしかった。
過去、幾度となく体験していて、台風への備えは万全だった。
すでに、近所の人が逃げ込んで来た時のために、焚き出しまでしていて台所には握り飯の山が出来ている。なにもなく終わったときは、しばらく家族中でそれを食することになる。
雨合羽に長靴姿で出かけようと戸口に向かったところで、外から戸が開き、雨と風が吹き込む。弟の昭二がびしょ濡れでとび込んで来て引き戸を閉ざすが、板戸が烈しく震えている。
昭二の声も震えていた。
「テルアニ。大仁の量水標が警戒水位を超えた。白山堂の三番だしの土手がやられそうだぞ」
「わざわざ、知らせに来てくれたのか?」
「テルアニのことだから、子供が心配で学校さ行くだろ?」
農協に勤める五歳下の弟の昭二は、輝夫とよくケンカもするが、、親思い兄思いの優しい心を持っていた。
母にも声をかけまたすぐに出ようとする。
「じゃ、オレは土手の補強だからな。じゃ、おっ母さん、気をつけてくれよ。テルアニ、オレは大仁橋を渡るからな」
戸を開いて二人は外へ出た。合羽が胸までひるがえって早くもびしょ濡れになる。戸を閉めたときは、すでに頭にかぶった野球帽がとび去っている。
「加代さんも心配だろうけど、大丈夫だ。新吾さんが……」
弟の声が雨風に消えた。
輝夫も弟に続き、母の肩を叩いて表に出た。
弟は暴風雨に逆らって南に走り、兄は風雨に押されて下流へ走った。まだ正午過ぎのはずなのに宵闇のように暗い。
走りながら弟の声を反すうした。それを伝えに戻ったのか。
その後に続いた言葉が気になった。
「……新吾さんが、救けに行くから安心しなってさ」と、聞こえたのだ。
加代の住む上溝の地区も危ないと聞く。新吾たち消防団がその白山堂地先の補強に行っている。弟は、それを伝えたかったのだ。
兄の敬一は多分役場に詰めているはずだ。
(加代と、その母が危ない!)
だが、新吾が救助に行けば心配ない。彼なら必ず救い出すだろう。これでいい。新吾に任せておけば間違いない。
「新吾のバカ野郎! 加代を大切にしろよ」
大声で嵐に向かって叫んだら、すっきりした。二人が一人の女性に惚れたら、どちらかが傷つく。
新吾は、親友の輝夫に遠慮してか派手な言動こそなかったが、加代への思慕が高まっていくのは誰の目にも分かった。さり気なくすればするほどその素振りはぎこちなく映るし、輝夫も辛かった。
これで、今までの悩みが一気に解決する。
知り合った頃は幼かった加代も成人を迎えてからはめっきり大人びて来た。兄の友人には平等で接していたのが微妙にバランスを崩し、新吾が加代に思いを強める以上に、加代の心は輝夫に傾いていた。だが、その微妙な娘心を知る者はいない。
輝夫の涙を雨水が流している。輝夫は、泥水に足をとられながら走った。雨足はますます激しさを増している。
父親がまだ十歳ぐらいだった頃の大正九年の大洪水の話が頭をよぎった。深沢川の堤防が決潰して水位が六メートル七〇センチを超え、家は壊れ人は叫びながら流されたという。
狩野川の歴史は、台風と洪水の歴史でもあった。
また、その歴史がくり返されている。
五日ほど前に、グァム島の洋上に発生した弱い低気圧が、徐々に勢いを増して発達しながら西北に進路をとりながら本土を狙っていたが、中心気圧八八〇ミリバール、最大風速七五メートルという大型台風となって八丈島の南西海上に達している、とラジオが正午のニュースで伝えていた。
風雨は次第に勢いを増し、雨量は上流でも六〇ミリを超えている。台風が上陸したら一たまりもない。ずぶ濡れの輝夫は長岡南小学校にようやくたどり着いた。
この頃、新吾は消防隊員の先頭に立って、白山堂地先の狩野川の堤防内の石を積み、出しと呼ばれる水勢緩衝の補強作業に当たっていた。
一番だしは田京の泉、二番出しはそれに続く泉下のカーブ、三番出しは急流がモロに激突する白山堂の下ノ田に築かれている。
この三番出しが土手ごと破られると、大きく狩野川の流れで囲まれている白山堂地区は、下ノ田、芹田、尾町、上川原、中ノ川原、原田、上堀など全地域が川の底に沈む。
激しい雨と風の中で、建設省からも人が出て官民一体の補強作業が朝から続いていた。
建設省が持ち込んだトロッコのレ−ルを、竹藪に続く土手に並べて打ち込み、その内側に土砂をリレ−して詰め込んだ。
濁流が渦巻いて刻一刻と水かさを増してくるのが誰の目にもはっきりしていた。
先の台風が去ってからまだ一週間も立っていない。その二十一号台風で、すでに狩野川は狂気の氾濫を起こして各地の堤防を痛めつけていた。補強に次ぐ補強も間に合わない。絶望的な空気が作業する人達の間にも流れ、また、それを否定する。
そして、今、台風二十二号の先兵となる豪雨は、大きく湾曲して流れる濁流に石を呑み込み堤防に牙を剥く。補強が勝つか、魔の台風が勝つか、もう誰にも分からない。
携帯ラジオのニュ−スを聞いた男が怒鳴った。その声すらかき消されていく。
「台風が上陸したぞう!」
悲鳴にも似た叫び声が起こった。それでもひるむ男はいない。今までもこれで切り抜けて来たのだ。
(ここが破れたら…)
頭のなかを駆けめぐるこの思いを口に出すものがいないのは、七月の神島橋を流出するほどの大洪水にも、九月に入って打ち続く台風にも、被害を最小限に押さえて耐え抜いてきた自信が誰の胸にもあったからだ。新吾は、ひたすら加代を想った。
肉体の疲労は、加代を想うことによって和らぐ。この工事現場からわずか一キロと離れていない上溝の家で、彼女は村の女衆に混じって焚き出しと幼児たちの世話をしているはずだった。その甲斐甲斐しさが目に浮かぶ。
補強が一段落したら加代の元に行かねばならない。だが、そのための余力が失せてゆく。
夕刻になった。疲労はすでにピ−クに達しているが、誰一人として補強の中断を口にせず、脱落者も休む者もいない。
「交代で休んでくれ!」
村落ごとの消防団のまとめ役の補佐に付いた新吾が、メガホンを抱えて走り回ったが返事をするものもいない。誰もが、この三番出しこそ、狩野川流域の村を守る生命線であることを知っていた。
「おい、あれを見ろ!」
上流から人が流れてくる。濁流にもまれて頭と手が浮き沈みしている。誰かが叫んだ。
「助けてやれ!」
昭二が、長靴を脱ぎ合羽を捨てると、傍にいた人が止める手を振り切って、激流に頭からとび込んだ。新吾がメガホンで怒鳴る。
「昭二。がんばれよ!」
狙い通りに、昭二が溺れる人の肩口をつかんだかに見えたが、それも一瞬、二人の姿はたちまち闇に呑まれて消えた。
サ−チライトの光の届く範囲内の流れのなかに、土手下に引き上げられていた木舟や道端から流されたリヤカ−などに混じって牛がもがき、家財道具や家屋の破材、家までが流れ落ちていく。
携帯ラジオにしがみついて耳を当てていた建設省から出向の担当者が地方局のニュ−ス速報で台風による被害状況を聞き、作業の人々に伝えていたが、嬉しそうに叫んだ。
「おい、小降りになったぞ!」
歓声が沸いた。確かに雨が細くなっている。
「どうだ。みんな疲れたべえ。監視番に二人ほどつけて一時間交替でどうだ?」
土木事務所の職員が提案した。全員が腰も立たないほど泥と水にまみれて疲れ切っている。一度、身体を休めると濡れた身体に冷えが走った。五分でも十分でも暖かくして横になりたい。空腹でもあり熱いお茶も欲しかった。土砂や石を運ぶ手が止まった。
「これ以上に増水したら、すぐ連絡できるよう監視番と連絡員二名づつで、四人にしたら……」
新吾の発言で、四人ずつの交替に決まり、作業に従事する消防団、建設省、土木事務所関係者や住民五十人以上もの人が、交替順位を決めることになった。
誰もが、自分の家族の心配でいっぱなはずだ。それでも全員が監視に残ると言い張る。これでは結論が出ない。
「でしゃばって悪いけど」
新吾が手を上げて発言した。
「家族持ちは、家に帰ってもらって。ヒトリもんだけ交替で監視にたったらどうだろか?」
原町地区の年長者が反対した。
「だめだ。気持ちは嬉しいが、ここを死守してこそ家族が守れるんだ。年寄りにも花を持たせてくれ」
結局、希望者の中からクジ引きで順番が決まり、一番手を残してそれぞれが家路を急いだ。
「昭二を探しに行ってくる…」
二番手に決まった新吾が懐中電灯を手に土手の上を下流に向かって走りだした。濡れて冷えた身体は重いが、今は昭二の無事を祈るだけだ。生い茂った雑草に足をとられ、何度倒れたことか。
「しょうじ−っ!」
新吾の叫びは空しく豪雨と濁流の音にかき消される。雷鳴が轟き、暗い雲間に稲妻が走った。
新吾の脳裏に濁流に喘ぐ昭二の悲痛な顔が浮かぶ。
土手道すれすれに川波が押し寄せ堤防を崩しにかかっている。
懐中電灯の光の輪の中に、えぐられた土手道に魔性の水が逆立っている。光がなければ落ち込むところだ。それを飛び込え滑って転び、起き上がって走った。
疲労で心臓の鼓動が早鐘をつく。呼吸が苦しい。足が重い。口は開いたまま雨を受けているのにのどが渇く。
懐中電灯の光の先に、土手道に人が座っているのが入った。昭二の顔が向いて、新吾が駆け寄ると抱きついて泣いた。精も魂も尽き果てた表情で訴えるようにいい、両手で自分の顔をかきむしる。
「流されてたのは、修善寺の大工だった。見覚えがあるんだ。でも、すぐ死んだ、死にかかってた。助けられなかった……」
「分かった。よくやった。昭二だけでも生きててよかったよ。さあ、肩に掴まれ。帰ろう。雨も小降りになったし、これで終わりだ。
みんな、家へ帰ったぞ」
「新吾さんがオレを助けにきてくれた。ここは町屋下あたりだから、上溝の加代さんちを通り越してオレを助けにきてくれた……」
「バカ、泣くな。もう帰るんだ」
「分かった。頼むから新吾さんは、加代さんちへ行ってくれ」
「おまえが先だ」
「オレ、兄きに、新吾さんが加代さんを助けるって言ったんだ」
「そうか。輝夫が承知の上ならそうしよう。おまえは帰れ」
「オレは、もう一度、三の出しに戻る」
昭二が決然として立ち上がった。
四 狩野川狂乱
敬一は、一度家に帰りかけたが暴風雨に自転車を倒されて考え直し、役場に戻った。
「家が心配なものは、すぐ戻れ」
荒井助役は、六時になると宿直の二名を残して全員に告げた。もうすっかり暗くなっている。台風慣れしている助役の予測では、二ヵ月前の七月二十三日に大仁地区を襲った洪水の記録が三・二九メ−トル、同じ水位までなら問題はない。雨に弱い地盤になっているにしても、三・五メ−トルまでなら被害を最小限にくい止めること
ができる。
そこまでの氾濫を想定した上で役場では救援対策を考えた。
「焚き出しが必要かどうかは、明日になって決めればいい。とりあえず、今夜は家を守り、ぐっすり眠ってくれ」
助役の家も、安全とはいえない芹田地区にあり、堤防の水が溢れたら床上浸水は免れない。それでも助役は帰宅せずに陣頭指揮をとっている。
「なんだ増田。おまえも居残り志願か? 白山堂は一番危ないんだぞ」
助役が心配そうに声を掛けたが、その表情は嬉しそうだった。敬一は頼りになるからだ。
「高島も戻ってきたからな。今、電力会社の人と、断線箇所を調べにいってもらった」
「私は、何をしますか?」
「おまえは、民間の警防団の連絡係を手伝ってくれ」
「消防署の人は?」
「ほぼ、全員、堤防補強に出動しててな、運転手を残して空っぽだ。各地の警防団員を召集しているが、皆勤め先や家の手当てで忙しい。連絡も満足にとれてないんだ」
「じゃ、おれも連絡に行ってきます」
「助かる。課長と消防車で走り回って召集かけてくれ。万が一を考えて警防団と救助隊だけは結成しとこう」
電線が切れているとなると、連絡は拡声器で呼びかけ、各地区に伝言するしかない。町長は、所用で他県へ行っていたが台風状況の悪化で急きょ呼び戻され帰途にあるという。
夜にはいると、大仁の町役場に情報を求めて人々が集まった。
土田町長も戻って来た。
電力会社の必死の応急作業で、役場の電話がつながったが、いつまた断線するか分からない。敬一も戻り、救助隊をまとめあげている。
「何! 下田が豪雨圏に入った?」
町長が報告を聞き、顔を蒼白にした。
今まで、何十回となく台風の洗礼を受けているだけに、その恐ろしさも身に沁みて知っていた。その町長がおののいたのだ。その一瞬の表情を敬一は見逃さなかった。
町長の声にかすかな脅えがある。
「雨が強くなる。各地ごと、いつでも避難できるよう連絡に走り、警防団は全員、堤防を守ってくれ。わしも町内を見てくる」
そして、悲痛な声をわざと殺して、「万が一、堤防決壊必死の報が来たら、早めでいいから、半鐘を鳴らしてくれ、いいな」
町長は念を入れると、雨具を手にした。
「増田、おまえは上溝だったな、これから家へ帰れ。ついでにな、芹田にも寄って区長に避難場を確保しとくように伝えてくれ。いいか、上溝も水に呑まれるかも知れんぞ」
町長は、助役の家にも気づかったのだ。
「私も仕事をします」
「ダメだ、家へ戻って家族を守れ」
その時、電話にしがみついて各所の状況を集めていた宿直が、受話器を持ったまま近いところにいた荒井助役に伝えた。
「助役! 三福の新道が不通、水が出て倒木があったようです。県道も城山下で崖下に土砂が流れて不通、村の人が除去作業を続けています。修善寺下で死体が重なって流れています」
再び、受話器に耳を当てる。
「河津で一時間雨量百ミリ超えた? 千二百ミリですか? もうダメだ……」
その絶望的で悲痛な声は、すでに屋外に出た町長と敬一の耳には届いていない。町長は、横殴りの豪雨を衝いて川岸に走った。敬一も続く。
やはり、町長は堤防が気になっていたのだ。
田京の役場から一番出しのある泉の下までは目と鼻の先にあり、たちまち河原を埋めつくした激流が闇のなかで湖のように広がって視界に入った。
かなり危険な状態なのか、堤防を見て人が騒いでいる。敬一と顔見知りの村人が下流を指さす。
「三番がやられてる!」
土手道の草を分けて二番出しを無視し下ノ田の三番出しに走ると、激しい水音が続く。
数人の村人に混じって昭二がいた。
「どうした!」
敬一を見て首を振る。
「負けた。もう止めきれないんだ」
「弱音を吐くな…」
町長が励ました。
柱に備えつけた電灯の光の届く位置に水が溢れ、土手を越えていた。誰もが言葉を呑んだ。突然、敬一が走った。上溝の家が危ない。水は勢いを増して堤防の傷口を広げようとして荒れ狂っている。
町長が重い口を開いた。覚悟を決めた口調だった。
「危険地区に知らせを出したか?」
「手分けして、役場にもいま、行きました」
「もう時間の問題だな」
空がほんの一瞬だけ明るくなったように見えた。
これが天の仕掛けた罠だったのか。貯水池の底を抜いたかのような豪雨が視界を奪って落下し、一気に狩野川の激流が堤防を崩して白山堂地区の下ノ田、芹田、上堀、屋町、上川原の耕地や家屋に一気に襲いかかり、平和な家庭を阿鼻叫喚の地獄絵の世界に引きずり込むために波の壁をつくって突き進んだ。
水に巻き込まれた村人が闇のなかに悲鳴を残して消えた。さらに一人、二人と……。
「早く上に逃げろ!」 町長が叫んだ。
堤防の上にいた全員が、土手伝いに上流に逃げ、水浸しになった道を走って小高い位置に辿り着き、腰を落とした。
町にも村にも、堤防決壊を知らせる擂(すり)半鐘が鳴り響き、洪水の危険のある地区の人々は避難場所を求めて豪雨の中を夢中で走った。その背後を二メ−トルの高さの濁流が襲う。
小降りになった状態で一安心した人々は、三日続いた雨も峠を越したと思って警戒をゆるめ、しばしの眠りに入っていたのが致命傷になった。
「中島がやられた! 村が沈んだ……」
泣きながら役場に走り込んできた警防団の若者が、雨の吹き込む入り口で腰を抜かした。中島地区は、田京からみて南に一キロ、狩野川の上流で広瀬神社を左に見て深沢川にかかる橋を渡らねば行けない。その深沢橋も濁流にもまれているという。
全員に悲創感が漂った。
中島地区の対岸やや下手が神島地区だから神島も危ない。
下流の白山堂、宗光寺、原地区からの悲報が次々に入ってくる。
もはや、収拾のつかない状況になっているのは間違いない。
(夢であってくれれば……)
再度、町へ出た町長が疲れ切った表情で役場に戻った。だが、その顔は、狩野川流域最大の悲劇を予感させるかのように苦悩に満ちていた。
明かりも暖房もない絶望的な夜を迎えた。
町長は、断線している電線の復旧を待ちきれず田京駅に走り、特別回線を借り県庁、県警、自衛隊と救援依頼の電話をかけまくった。すでに伊豆地方の惨状は伝わっていて、陸上自衛隊が沼津市内の倒壊家屋からの重傷者の救出に向かったという。
それでも、大仁町の惨状を告げると、伊豆地方各市町村から続々と悲報が続いているが、速やかに救援部隊を送り込むとの確約が得られた。
「夜明けまでが勝負だな……」
町長は、一斗樽を運ばせた。今は、気力が頼りだ。茶碗一杯で勢いずいて雨の中に飛び出していく若者を励ます。
「頼むぞ! 一人でも助けて来い!」
悲劇は際限なく続いた。
敬一は、洪水に巻き込まれて死んだ。
死の寸前、敬一の心はおだやかだった。
父は早逝して今はなく、母は病弱で心臓の病を抱えている。妹だけは幸せにしたい。だが、輝夫と新吾がいる。あの二人が必ず、母と妹を幸せにしてくれる……。
洪水に流されながら恐怖は消えていた。
石魂に打たれ、家屋の破材に内蔵を破られ、泥水に呼吸を閉ざされ、そして、敬一の魂は宙を舞った。
ひたすら、母と妹と親友の無事と幸せを祈りながら……。
輝夫は、一度学校に出てから、洪水が出た場合に危険区域と思われる児童の家を地図の上に朱印でチェックし、雨のなかを勢い良く飛び出していた。
もう自転車は無理だった。ひたすら走って家々をまわった。
家族が離れたくないというと、子供だけでも学校に避難するよう説得した。
どんな事があっても子供たちには指一本ケガをさせたくない。
「子供だけでも助けて!」と、頼みこむ家族もある。
ラジオでは、すでに最悪の被害状況を報じていた。
まだ、長岡地区は辛うじて電線が切れていない。しかし、それも時間の問題と思われる。できるだけ食糧を持ち寄るように伝えながら、子供たちに手を継がせて豪雨を裂いて走った。
教師は、ほぼ全員が同じ行動をとっていた。輝夫だけではなかったのだ。率先して家族ぐるみ避難している人達もいて、学校の二階の各部屋は賑わった。
やがて、狩野川堤防決壊の報が入り、各地の悲劇がつぎつぎに携帯ラジオを通じて知らされた。狭い土地だ。それぞれに家族や親類がいる。身体を寄せ合って暖をとっている。輝夫が近くにいる子供に声をかけた。
「どうだ、歌でもやるか?」
「うん!」
日頃は目立たないその男の子が、小学三年生とは思えないしっかりした声で叫んだ。とっさに、これを歌おうと思ったのか。
「これから、小さい子らのために『山の音楽隊』を歌います」
拍手がわき上がり、全員が手拍子で唱和した。沈んでいた空気が一気に軽くなった。
“わたしゃ おんがく かやまのこりす じょうずにバイオリンひいてみましょう
キュキュキュキュキュッ キュキュキュキュキュッ いかがです…… ”
その歌声を背にして、その場を同僚に任せた輝夫は、階段を降りて外に出た。
雨合羽の下は下着までびしょ濡れだが乾かす余裕はない。
(いまならまだ大門橋を渡れる)
疲れも寒さもひもじさもない。ひたすら加代のことを思って走った。電灯の光が弱い。
(新吾がいるのに、なぜ行くのだ)
ハッとした。ジェラシ−を感じるのは、加代が好きだからか、愛しているからか。走りながら思いはまた原点に戻る。
(やはり新吾、おまえが加代を幸せにしろ)
懐中電灯の光の輪のなかに橋が浮かんだ。
橋の上を濁流がよぎる大門橋は、今にも崩れ落ちそうに水中できしいでいる。その橋桁上流には、幾重にも流された家や納屋や動物、果ては人間の死骸が重なり合って枝木に覆われている。
せき止められた水流は土手を越えて田畑を埋めつくし、見渡すかぎり浅い湖に変貌しているのが闇のなかでも分かった。
腰骨を打つ水流に耐えて対岸に渡った輝夫は、道を求めながら何度も足を踏み外し水中に没したが、やがて膝上までの安全な高地にたどり着き、南へ、白山堂の上溝へと水しぶきを上げて走った。
上溝の部落はまだかろうじて人家を残していた。だが、それは輝夫の見誤りだった。
流された家があちこちで肩を寄せ合って滞留していたのだ。
屋根の上に懐中電灯の光が振られ、揺れながら流れていく。叫び声、泣き声が浮かんでは消えてゆく。
暗闇のなかに地獄絵があった。
これがあの清冽な狩野川の本性なのか。
輝夫は必死で水中に没しかけた家から人を引き出し、引きずり背負い抱いて安全な場所に移した。何人運んだかも記憶にない。
懐中電灯の電池が切れた。それを捨てる。目が闇に慣れて雨の中でも周囲が見える。
いつのまにか悪魔の夜が明けつつあった。
その黎明寸前のほの暗さの中に、加代の家が浮かんだ。そこだけが見えたと言うべきか。輝夫が身を踊らせて流れに逆らって泳ぎ着いたのは屋根下のひさしだった。
その屋根下の窓に根のついた倒木が引っ掛かり、濁流が渦を巻いて流れ込んでいる。
輝夫はそこから家の中に入った。
平屋造りの家だが間取りが多く、手探りで潜ったりして部屋から部屋に泳ぎながら探し求めると、ようやく人影がみえた。
三人が重なるように部屋の隅にいる。新吾が守っていたのか。
水流に押されて輝夫も三人に重なった。
とうに長靴を脱ぎ捨てていたことで素足が冷えて感覚を失っていた。その足が家具の中に入った。敬一の家に大きな仏壇があったことを輝夫は思い出した。足の指先が位牌に触れた。見上げると天井に割れ目が入っている。
まず、荒い呼吸をしている母親を先に助けることにする。脈もしっかりしている。
足を仏壇の溝にかけて背を延ばし天井を突くと、壊れかけた板材が音をたてて崩れた。手探りで横木を見つけ腕力を使うと上に昇れる。
しっかりと抱きあっている三人から母親を外して抱え上げ、何度か苦労したが屋根裏に運び、そっと横たえると水を吐き、呼吸が正常に戻った。
つぎは加代を抱いた。脈も心臓も弱まっている。
屋根裏に引き上げ、必死の口移しで人口呼吸をすると、烈しく咳き込みながら首を動かして水を大量に吐き、大きく息をすると脈も呼吸も正常に戻った様子だった。
思わず嬉しくて涙ぐむが、感傷に浸る暇もない。
また水中に漬かり、必死で持ち上げるが、すでに意識のない新吾の身体はさすがに重い。
輝夫が声を枯らして励まし必死の気力で、新吾を屋根裏に引きずり上げたとき、すでに新吾の命運は尽きていた。呼吸が絶えている。空しいと知りつつ泣きながら叫ぶ。
「新吾−、しっかっりしろ!」
だが、今は泣いている時間すらない。屋根の壊れた穴から雨が吹き込んでいる。
水が天井裏まで来たら、二人の命も危ない。
輝夫は、天井の梁(はり)を足場に、注意しながら両手で瓦を押さえて必死で屋根上にはい上がる。
ここまで二人を引き上げるのだ。雨足は強いが空は明るさを増している。
輝夫は屋根の上から空を見上げた。
そのとき、上流から流れてきた家の屋根だけの屋材が加代の家に激突し、輝夫は、その瞬間の衝撃で屋根から水中に転落した。
ゴミ混じりの水をしたたかに飲んだ輝夫は、必死で流木につかまり濁流の中を流れ落ちていた。
故郷の山々が明けていく初秋の空の下、小雨のなかにくっきりと浮かび、冷えと疲労が重なってか意識が遠のいてゆく。
台風二十二号通称狩野川台風は、一夜にして千人に近い生命を伊豆半島から奪った。
堤防決壊によって洪水の直撃を受けた大仁町白山堂だけでも七十四人の死者が出た。
輝夫は二キロ余の距離を流されて、大門橋にせき止められた流木のなかから瀕死の状態で救われ、一命を取り留めた。
三番出しから姿を消した敬一の死体は、上溝の我が家の近くの立木に絡んで発見されたが、背骨が曲がり凄惨な姿だったという。
浸水家屋の天井裏で発見された増田加代とその母清乃は、ゴムボ−トで救出作業をしていた自衛隊員によって救出され、その傍らで息絶えていた新吾の遺体も収容された。
水中に没しかけた屋根裏から二人を発見した自衛隊陸士の証言と、失神していた母娘のおぼろげな記憶から、息子の親友の勝村新吾が二人を救い、その末に力尽きて死んだものと推測された。この、悲惨な一夜に咲いた、徒花のような美談にマスコミが群がる。
「命を賭けて、恋人とその母を救った勝村新吾!」
テレビ、新聞、雑誌とあらゆる媒体が生き残った二人、というよりは加代を追った。しかし、加代もその母も体調が戻って病院を去ると、修築中の家に籠もり人目を避けて、沈黙を守り通した。
その姿勢が、世を去った彼への鎮魂の服喪として美談になり、自薦他薦を含めて数多くの縁談が殺到し、それがまた話題になる。
それでも、加代が頑に取材を拒否し続けるうちに、人の噂も七十五日、美談も縁談も忘れられていった。
輝夫もまた、一時は危篤の状態で心神喪失に落ち入ったが、一ヵ月ほどで奇跡的に回復し記憶も戻った。だが、彼もあの悪夢の一夜を口にしない。多分、それは生涯続くことになるだろう。
恐ろしい夜だった。
生涯の友として自他ともに認めていた二人の親友を失い、数多くの知人隣人を失った上に、さらに、悲しい出来事が起こった。
彼ら三人が鮎漁で師事することになったセドのジサマが、台風で死んだ孫たちを追ったのか、ある日、川で死んだのだ。
辛い話だった。
セドのジサマは敬一と新吾の葬儀の折りに、入院中の輝夫の心配ばかりして、輝夫の父に、輝夫に川漁の後継者になって欲しいと伝えてくれと、語っていたという。
その日、セドのジサマは、「川を見てくる」と、家を出て、そのまま川に入って死んだ。ジサマが川に入るのも流されたのも橋や土手の上から何人もの人が見て、救出に走った。
この時期に続いた大水で落ちた鮎は、もう二度と戻ることがないのを誰よりも知っていたはずのジサマが、なぜ、川に入ったのか誰も知らない。澄んできたとはいえ水量はまだ多く、流れも早い。
ジサマの死体は、岩影に沈んだのかついに発見されなかった。
遺体のないまま葬儀が終わった。
だが、輝夫だけは知っていた。ジサマは、あの段々瀬の石を洗いに行ったのに間違いない。そこだけでも早く新アカを付着させ、数少ない残り鮎を呼び寄せ、輝夫に一つでも釣らせようとしたかったのに間違いない。
それからの輝夫は、極端に寡黙になった。鮎の話題を避け、ひたすら学校教育に専念し、児童にも父兄にもよき相談者として慕われ、いい教師らしく過ごしていた。
その輝夫は休日になると、心身共に立ち直って勤めも始めた加代を誘い、あの台風の犠牲者の墓参に通った。
敬一の墓は上殿の共有地内にあり、そこには白山堂地区六十五体の犠牲者の殆どの霊が無念の眠りについていた。中島にある新吾の墓にも花を欠かすことがない。それぞれの思いを込めて手を合わせ冥福を祈った。
やがて、周囲からすすめられて二人は結婚した。
輝夫に抱かれた加代は、唇の感触で本能的にあの日の人工呼吸の相手が輝夫だったことを知る。
意識が戻りかけたときに優しく抱きしめたあの手の位置も癖も同じだった。
命の恩人が新吾だけではなかったことを知り、輝夫に抱かれて加代は泣いた。嬉しかったのだ。
五 第二の人生
あれから三十有余年、飯島輝夫は二十二歳で教壇に立ち、西伊豆などの各地の小、中学校を歴任、奇しくも出発点でもある長岡南小学校の校長として停年を迎え教育の場の表舞台から来春、身を引くことになった。
それまでにも、大仁町神島区の区長、農部会の会長を始め地元の教育委員会の主軸として町史村史の編集に携わり、古文書や古記録の収集、文化財の調査など未発見の資料を求めて精力的に奔走し、地元の世話役として貴重な役割を担い、内外の信頼を集め、周囲の期待にも充分応えて、第一の人生を全うしたといえる。
人はよく定年後を第二の人生という。
(教育の場を退いたら……)
若い日、初めて一日中鮎の生態を観察する機会に恵まれ、短い日々、夢中で川に通い一冊のノ−トが黒くなるほどその興奮を書き連ねた日々が、彼の第二の人生への原点だった。
(定年になったら、シ−ズン中川に通い竿を出し鮎と戯れ、余生を故郷と狩野川のために…敬一、新吾、祖父、セドのジサマなどの眠る川へ)
この思いは、多忙に明け暮れた教職員生活三十余年のあいだ、一日たりとも忘れたことがない。それが、川で失った多くの友や身内への供養になると彼は信じた。
しかし、ある秋の日、翌年の解禁に胸踊らせながら改めて川辺を歩き愕然とした。
昔、川漁師になって鮎で稼ぎ、父親に軽自動車を買う、などと放言した頃の狩野川はいつの間にか、その放言同様、幻のように消えていた。川の流れは昔のままのようにも見えていて明らかに何かが違う。岸辺にゴミが多い、ビニ−ル袋や空き缶、コンビニ弁当の食べ残し、心ない釣り人が捨てたのか腐った小魚の死骸、石の色も違
う。川の匂いも変わっていた。
洪水の要因の一つと見られていた江間のコンクリ−ト堰は取り除かれ、白山堂地区を取り巻くように湾曲して流れていた淵も瀬もある狩野川中流部が、ショ−トカットの人口河川に変わり、洪水による地元の被害を防いでいる。これも見慣れた風景になっている。
あの忌まわしい台風のあと、道路も整備され、昭和三十六年には大仁橋下流に国道一三六号線の通じる狩野川大橋も完成し、観光伊豆の要所としての大仁の発展は喜ぶべきものである。だが、なにかがずれている。
過疎化しつつある農村部に工場を誘致することで、Uタ−ン現象や農閑期の主婦のパ−ト県外から人を呼ぶ、地元の収入増などと地域の発展を錦のみ旗に、狩野川流域の町村には次々に工場が進出した。
その許認可をめぐっては、官公庁役人、政治家の暗躍や、買収工作、増収賄などのきな臭い噂が必ずといっていいほど飛び交ったがいつか力の論理と経済効果の甘言に押し切られて、工場進出反対の声も尻つぼみに終わり、多くの企業が進出していた。
工場排水の問題は、やはり単なる危惧では終わらなかった。公式文書には残らないにしても狩野川史上の汚点ともなったシアン流出事件も発生している。下流に大小の川魚が死屍累々として白い腹を浮かべ、海に落ちた。犯人は最上流にある鉱石会社と判明した。
その元凶となる工場も、漁協との補償問題も「三尺流れて水清し」のようにあいまいに終り、どこで手打ちがあったのか、政治的決着がついたらしく騒ぎは静まった。その過去の不明朗さが尾を引いて川を悪くしている。水は清くならなかった。
ただ一筋に狩野川の鮎に夢を託した退職後の第二の人生への思い込みが針で指された風船のようにしぼんで行く。子供たちは家庭を持ち孫もいて、後は鮎だけなのに。
その彼の危惧は現実に狩野川の鮎シーズンを直撃していた。
以前は澄んだ川の底が見えなくなるほど群れて遡上した40トン近い海からの若鮎が、影も形もない。調べによるとわずかに0・5トン、無に等しい数字でしかない。
天然鮎で知られ清流でなる狩野川にとって屈辱的な秋が来た。
鮎がいない。
小さな台風が来て、大水が出ただけで大鮎のシーズンに鮎が激減したのだ。しかし、その事実はひた隠しにされ、休日には高い入漁料を払って釣り人が竿を出す。
月の中旬に小型の台風は来たが鮎を落とすほどとも思えない。
秋も深まったある日曜日の朝、いつもの日課通りに散策していた輝夫は、神島橋上流に三人の釣り人を見かけた。一人は上流対岸の大仁で釣り人宿を営みながら釣場のガイドやコーチをしたり、釣り具メーカーの新製品試用などを仕事にしている江本という教え子の青年で、後の二人には見覚えがない。
輝夫は土手を降り、生い茂った草を分けて水際に出て、魚を怯えさせないように下駄を手に持ち河原の石を素足で踏みながら、二十メートルほどの間隔で並んで竿を出している三人の背後にまわり、距離をおいて大石に腰を下ろした。
下流にいた江本が輝夫に気付き帽子をとって挨拶をした。
それに気付いて、上に入った二人も振り向き軽く会釈をした。
三人三様かなりの手練れであることは一目で分かるが、オトリ鮎の泳ぎを竿の操作で、石から石へと探りを入れているようだが、かなりの時間当たりがない。
やがて、二人に挟まれて竿を出している細身でオシャレヒゲの釣り人に当たりが来た。十メートルの長竿が円相を描いて絞り込まれるが、竿を立てたまま一歩も移動せずゆるぎもない姿勢で、野鮎がオトリに続いて水面に背を見せるのを待つ。さして、時間もかからずに根負けした鮎がオトリ共々、待ち構えた手網めがけて宙をとん
だ。手慣れた見事な竿さばきだった。
が、受けた手網を流れに浸けながら、男がギョッとした表情で掛けた鮎を凝視し、いたわるように水中で優しくカケバリを外すと掛けた鮎を川に戻し、素手網にオトリ鮎を入れたまま水中をゆっくり歩き、上流で竿を出す男の引き舟に鮎を移して岸辺に上がった。
「どうしたのヤマトモさん、珍しくギブアップ?」
江本が驚いて声をかける。
「ああ、食み跡から見て数も出ないからな。オレは上がるけど、のんびりやってや」
ヤマトモと呼ばれた男は、河原に上がり、無言で仕掛けを巻き竿をたたみ篭脇に置くと、胸のポケットからポリ袋に包んだタバコを取り出し、輝夫に近ずいて「どうぞ」と挨拶し、一本差し出すと自分も口にくわえ、ライターで輝夫のタバコから先に火を点けた。
江本にも来た。二尾の鮎が飛ぶ。
「なんだ!」と、江本が不機嫌に叫んだ。
「どうしたんだね?」
素朴な疑問が輝夫の口から自然にこぼれた。
「見てきたらどうです?」
ヤマトモが手を上げ、掛けた鮎を流れに放そうとする江本に声をかける。
「エモちゃん。このオッサンに鮎を見せてやってくれ」
輝夫をうながし、自分も一緒に平瀬の水際に歩み寄る。
江本もオトリを外して曳き舟に移し、竿を担いで「ギブアップだよ」と、言いながら水際に近寄る。
「飯島先生、こいつですよ……」
江本がゆっくりと岸に寄り、手網に入れた野鮎を水に浸け、輝夫の目の下に出した。
「新種かね?」
鼻の先のトガリがない。頭と口先までが偏平で、今まで見たこともない妙な魚だった。まるで人面魚だ。
「よく見てください。これでも鮎なんですよ。今年は背曲がりなどの奇形も珍しくないんです。稚魚に混じってたんでしょうかね。でも、あちらの越塚さんは、湖産じゃないって言い張るし……」
江本が張りがない声で、まだ上流で竿を出している恰幅のいい男を見てアゴをしゃくった。それに気づいたのか、その男も竿を上げ、オトリを手網に飛ばした。
話しには聞いていたが、ついにこの狩野川にも奇形鮎が……。
狩野川は、天然鮎の看板が色あせ、衰退の坂道を転げ落ちていたのか。輝夫の絶望的な気持ちを見透かしたのか、ヤマトモが気に触ることを平然と口にする。
「もうこの川の鮎は終わりだね」
冗談じゃない。輝夫の第二の人生はどうなる?
「あんたら釣り人が、何とか出来なかったのかね?」
輝夫には珍しく、つい愚痴まじりの不機嫌な口調になる。
だが、それを聞いた途端、おだやかに見えたヤマトモの表情が険しくなり、道具を仕舞いかけている江本に怒りのホコ先を向けた。
こっちも冗談じゃないのは、ヒゲの震えで分かる。
「オレは頭に来たぞ。エモさん、オレに喋らせないで、この変なオッサンに納得いくように説明してくれ。オレは金払ってるんだ。お客さんだぞ!」
輝夫が唖然とした顔で、ヤマトモの怒り顔に困惑してうつむく江本を見た。
「江本君、この人、なんで急に怒ったんだね?」
仕方ないという口調で、江本が説明する。
「川の管理が悪いからですよ。この人は、東京下町の釣り具屋で、恐怖のヤマトモといわれる鮎狂いの名手でして、わたし達テスターとか鮎名人で名のある人は、猛毒のハブにでも出会ったように萎縮するか敵意を剥き出しにするかの存在なんです。
でも、ヤマトモさんは、昔からこの川の熱烈なフアンで、それだけに、この狩野川の目を覆うような凋落が耐えられないんですね。
工事ばかりで川は濁るし、鮎はひどくなるし。見ますか?」
ふて腐れた顔で江本青年が、上がって来て黙って石に座りタバコをふかしている越塚という男に声を掛け、水中に沈めてあったその男の生け簀缶を持ち上げ、恩師の目の前で蓋を開いた。数少ない鮎が、それでも驚いてか勢いよく暴れている。
ヤマトモと輝夫も歩み寄る。
「いい型じゃないか、なにを見るんだね?」
「いいですか? こちらの越塚さんは琵琶湖で種鮎を扱っている大手の養殖業者です。組合と取引もないのに今日わざわざ来ていただいたのは狩野川の実態を知ってもらい、急激に増えた奇形がどこから産まれたのか、対策はあるのか、わたしも組合員の端くれですからこうして恐怖の名人殺しのヤマトモさんにも来て貰ってるんです。今、狩野川の危機にみんなで立ち向かおうとしてるんです。それより、もっとよく鮎を見てください。こちらには奇形もいます」
輝夫が、青白い鮎をつかんだ。
「なんでこいつの背に傷があるんだね?」
「なぜって、背掛かりだからですよ」
「こいつは養殖だろ?」
江本が開き直った。
「そうです。こいつは養殖です。だから、どうしたっていうんです? 川に鮎がいなくても、週末にはまだまだ鮎を釣る人が来るんですよ。大会の前などに、高い日釣券だけ売って鮎はいませんじゃ詐欺になります。だから、、つじつま合わせに成魚放流するんです。
これは多分、その残り鮎です。こんなことどこだってやってますよ。どこが悪いんですか?」
二人の会話の腰を折るように、ヤマトモが立ち上がった。
「毎日のように支流で工事があるのか、工場排水が流れこむのか知らんが、水が淀むところなんぞ泡が巻いてるんだ。上流で、一年中川浚いしてるって噂もあるし、下水道が完備したっていうのに排水の垂れ流しもあるらしい。河川改修護岸工事でそのうち天城から駿河湾までストレートの人口河川の鮎釣り堀ができるぞ」
ヤマトモが、怒りと寂しさを捨てせりふに残して荷を担ぎ、慣れた足取りで石の上を歩き出した。
その背に向かって、これも珍しい教育者の罵声がとんだ。
「この川を勝手にさせてたまるか。必ず生き返らせる。見てろ!」
第二の人生をこの川でと、耐えに耐えて来た思いが無惨に踏みにじられていく。
「よろしければ一度、遊びに来てください」
哀れむような目で輝夫を見て名刺を渡した越塚という男も、礼儀正しく挨拶をした江本青年と連れ立って去った。
秋の風が土手下の雑草に揺らいでいる。
この川は、このままゆっくりと堕落し続けるのか、それとも何らかの方策で、昔のように、端から端までの石と魚群が見通せる清い川に生き返らせることが出来るものなのだろうか。
やがて、冬が来て雪一面の銀世界が狩野川の河原をおおう。
そしてまた、若鮎が遡上する春が来る。
川は回復するのだろうか。
六 狩野川再生
狩野川漁協は、狩野川再生に立ち上がった。
しかし、一方では異なった意見もあるのも事実である。
「狩野川は一部の釣りマニアだけのものではない」
この意見の急先鋒がイノケンと呼ばれる中伊豆建築土木の社長、猪瀬健吉だった。
近く県議に出馬するとかいわれている男で、この業界に有りがちな暴力団関係との交流や、建設省や県の土木課との癒着など黒い噂の絶えない男で、その風貌は凶暴な土佐犬を彷彿させる。
二代にわたって橋梁・道路・護岸・河川等不要と思われる工事まで請け負い狩野川をわがもの顔に変えんとするこの男を毛嫌いする地元民も多い。
この男が、昔のよしみと称して「飯島輝夫氏・第二の人生激励会」に顔を出したのは、選挙対策とみて間違いないがこの場違いな男の出現で、夜桜が風に舞う神島橋近い公民館で近隣の知人友人各界有識者を集めて盛大に開かれた祝いの宴は支離滅裂となった。
イノケンを天敵と見て、先に仕掛けた漁協の遠藤という男もガラがわるく大人げない。いまだに狩野川台風で母を失ったのは、イノケンも工事に加担した堰の恒久化工事のせいだと信じている。
「おい、イノケン! この席はな、てめえみてえな川浚い人殺しの来るところじゃねえんだぞ」
「なんだと! 祝いの金持参で文句言われてたまるか。川工事じゃ漁協組合にも補償金が出てる。礼の一つも言ったらどうだ」
「いい加減なこというな! 聞いた人が本気にするじゃねえか」
「金はな、いつだってそっちから持ちかけて来るんだぞ」
二人とも酒のせいもあり赤黒い顔で罵り合い、つい腹にあることが口を衝く。
「おまえ達親子は、役人と結託して江間堰のコンクリート化工事で儲け大水の原因をつくってな、大勢の人を殺した挙げく堰の解体工事でも大儲け、河川改悪工事でボロ儲けを企み護岸工事だ川底平滑化工事だと、とうとう鮎まで追い払っちゃったじゃないか。豪邸を建て、外車をのりまわしメカケ狂いをしてる暇あったらな、川をきれいに戻すぐらいのこと考えてみたらどうだ」
イノケンが鼻の先でフンと笑った。
「あんたら、大の大人が寄ってたかって鮎だのウナギだのって喚いてるから、台風がくりゃあ大水が出て家が流され人が死ぬようなことになるんだ。
奥の山は、根に保水力のあるブナなどの伐採で、雨が降ると一気に水が出る。こいつはワシらのせいじゃあねえ。そこでだ、ますます川は直線化して最短時間で流れを海に落とさねばならん。
そのためにはな、まだまだ川が大化けするほどの工事をせにゃならんだろ。水なんか流れてりゃきれいに見えるもんだ。
パリのセーヌ川だって濁ってても誰も文句は言わんぞ」
「セーヌ川じゃねえ、狩野川の話だ」
「伊豆でも、とくにこの辺りの長岡、大仁、修善寺は都心から近いこともあって、温泉と観光でこれからも充分繁盛し発展するぞ。
鮎だってな、放流さえしとけば下手な釣り師がわんさと来る。
どうせ、狩野川の名にあぐらをかいてやらずぶったくりで稼いできた漁協じゃないか。ま、わしが県議にでたら、一緒に手を組んで一稼ぎしようじゃないか……」
「だれがドロボー野良犬みたいなイノケンを県議に選ぶ?」
と、遠藤が絡む。
「なんだと! ドロボーとはなんだ。この野郎!」
「やるか!」
茶碗が飛び膳が倒され、取っ組み合いが始まる。酔っぱらいのケンカだから始末が悪い、全員が入り乱れて殴り合いになり、輝夫も五発ほどかなり効くパンチを食らった。
輝夫の激励会は、救急車到着という派手な幕切れで終わった。
その話題は、たちまち町中に広まった。
「大変だったそうですねえ…」
行き交う人々が輝夫の顔を見ると、同情の言葉を投げかける。
せまい土地だけに、話しに尾ひれ背びれが付いて、定年を迎えた校長先生が、あの夜の乱闘騒ぎで殴り倒されて重傷を負ったという風聞になって、輝夫の家には見舞いの果物や菓子が届いた。
それだけに、元気で歩いている輝夫を見てけげんな顔をする。
そんなある朝、買い換えて数年になる愛車の燃料補給に寄った地元のガソリンスタンドで、旧知の間柄でもある村田という経理士に出会った。村田は輝夫より十歳ほど若いだけに元気がいい。
「先生、重傷だそうですが訴えますか? 親しい友人の弁護士を紹介しますよ」
余計なお世話だ。噂は一人歩きし、輝夫が狩野川のために職漁師になるという説もあるとか。
車をスタンドに預けたまま二人は、並びの喫茶店で語らいの時を持った。前理事長から引き継いで、狩野川漁協を引き受けることになった村田計理士は、琵琶湖の養殖業者の経営する「とうしゅう」という川魚料理の店で、郡上鮎など各地の鮎の食べ比べに招かれ今から片道三百キロ近い距離を走ると言う。
「いやあ、漁協の理事長なんて、とんでもない仕事を引き受けちゃってねえ。まだ一ヵ月だけど、本業は休業ですよ」
「期待してますよ。みんなでやりましょう」
「狩野川再生の十字架を背負って漁業組合長を引き受けた以上、遠慮はしませんよ。お互い、日本一の旨い鮎を食いたいですなあ」
と、屈託なく笑い、輝夫にも協力を求めた。
「今年は、飯島先生も第二の人生を鮎に賭けるって評判ですが、ぜひ漁協の事務局長を引き受けて頂けませんか? みんなで川を甦らそうじゃあないですか」
「なにから手をつけるつもりかね?」
「飯島先生の祖父も川漁師。先生もセドのジサマにも鮎掛けを教わったそうですな?」
「とんでもない。毎日、潜って鮎を見るのと川掃除だけで、ほんの少ししか釣らせて貰えなかった。あんたのオヤジさんも名のある鮎漁師だったね」
「おかげで私も散々川掃除をさせられました。漁師は石洗いがしんどくなると弟子をつくるんだそうですな」
そこで、村田計理士は、いい珪藻を付着させるために組合員総出で川の石を洗おうと言い出した。河原に火を焚き暖をとり飲み食いをしながら楽しく川掃除をするという。
「これから会う越塚のオヤジさんってえのも川漁師の家に育って、根っからの鮎狂いなんですよ。そうそう、エモさんが、名人殺しのヤマトモさんと、その越塚ダンナを案内した時、先生にドヤされて小学生時代に叱られたのを思い出したって言ってましたな。そういえば、琵琶湖の稚鮎漁は、解禁の十一月二十一日からわずか一ヵ月
の十二月十日には資源保護のために決められた六十トンをクリヤーしたそうです。姉川の上り鮎の梁漁も三月には無事終えて、この狩野川にも久しぶりにいい湖産鮎を放すことが出来ました。
先月末に海産2・湖産4・人工産4の割合で約二百万尾、五グラムの稚鮎が、きれいに洗っていいアカの付いた石を巡って争いながら解禁時六十グラムに成長。どうです? いいシーズンになりますよ。天然鮎の遡上を邪魔するシラス漁、ヤナ漁、排水の流れ込みにも手を打ってますからね。ただ……」
「なんです?」
「イノケンの河川工事だけが気がかりで。上流で、片っぱしからブルを入れて川底浚いの工事をしてるんです」
「なんで?」
「公共投資ですよ。もう、川をいじるしかネタがないんですよ」
時計を見て、計理士休業の新組合長が立ち上がった。
往復一万六千円以上の高速運賃を自腹で払っても、各地ライバルの川が育てた同じ琵琶湖産鮎の味の違いを確かめたいという。その意気込みは高く買える。
「ひょっとすると、狩野川は生き返りますかな……」
二人は笑顔で別れた。
七 幻夢の淵
この年の狩野川は鮎を追う釣り人を裏切らなかった。
水底の石という石に鮎が群がっている。
磨かれた大石には鮎の好む鮮度のいい珪藻が付き、刃物で削いだような笹の葉状の食み跡が無数に交差している。
教職を退いた第二の人生を、他河川に先駆けて五月の最終日曜日に解禁した鮎釣りを、生まれ故郷の川で迎えた感慨は例えようもなく深い喜びに包まれたものだった。
竿と竿が触れ合うような超過密な狩野川で掛けた若鮎のしっとりとした感触を味わっただけで至福の思いが溢れ、生きている喜びがひしひしと胸を打つ。
(敬一、新吾、一緒に釣ろうな…) 心の中で呟くと、無性に青春の日々が懐かしく思われた。初日は型を見ただけで満足し竿をたたんだ。これから、毎日川に入れるのだ。
その日から輝夫の生活のリズムは一変した。人生そのものが変わったと言っても過言ではない。
家の敷地裏を走る細流の一部を堀り、石油缶を加工して作ったオトリ罐を五つ並べてイケスにし、石も入れて鮎を飼った。
朝起きると食事前に必ず、庭の池に泳ぐ狩野川で釣った大鯉に餌を蒔き、イケスの鮎を眺め、その足で川に行き、水量、水温、アカの付き具合、食み跡などを見てまわり、その日の釣り場を思い描き朝食を済ますと川に走った。それは、濁りが入らないかぎり雨の日でも続く。これが彼の望んでいた人生だったことは間違いない。
狩野川をホームグランドとして活躍する若手の名手たちの話しも聞き、喜んで一緒に釣りもし歓談もした。
各地の鮎大会で華々しい活躍を見せるチビ錘り釣法の上野歯科医やチャラ瀬を釣らせたら日本一という若杉名人などの積極的な協力で、狩野川の鮎の生態とその攻め方についての研究会を開いたりもした。
新組合長として内外に多忙な村田計理士の提唱する、鮎の里狩野川の復活は実現しつつあったかに見えた。
輝夫の呼びかけで各地区学童総出での河原掃除ボランテイ アも、地域の人々の目を引いた。
河口でのシラス漁と称する稚鮎の乱獲も、湾内漁協の理解で最低限にとどまり、天然遡上の鮎も近年になく豊かに育っていた。
湖産も人工産も奇形のない良型の鮎ばかりで何よりも、「味がいい」という評判が地元漁協にとっての励みにもなっていた。
しかし、そんなに世の中甘くない。この状態を苦々しく思う天敵の存在を無視することは出来なかった。
組合の陳情で水資源保護公団の自粛案を受け入れていたかに見えたイノケンが、まだ自然そのままの上流山岳部の支流にブルトーザーを乗り入れ、川底の石を均し、苔むした岩や蔓草の生い茂る自然のままの沢岸にコンクリートブロックを積む意味のない護岸工事を再開したのだ。どさくさに紛れて予算消化の常套手段である砂防ダムも何ケ所かコソコソと手掛けているという。
朝から雑草混じりの濁り水が狩野川を埋めて流れ、根草が糸に絡んで掛け鮎ともどもオトリごと一荷で浚われるという腹立たしい被害が続出し、折角名誉を挽回したばかりの漁協事務所には遠来の釣り人からの苦情が殺到し、対応に疲れた事務局の女性の一人がストレス性頭痛でダウンで欠勤となる。
ついに、頼まれても固辞していた輝夫も、手不足の事務所を手伝わねばならない羽目に追い込まれてしまった。
大仁橋西側下流土手際にある事務所に行くと、数台の電話はひっきりなしに鳴り苦情が続く、流れ草に糸を切られたの竿を折られたファッションだけ一人前のビギナーが怒鳴り込みあるいは泣き言をいいに立ち寄り、タバコを喫う暇もない。
当然、輝夫の竿は事務所の片隅で朝から夕方まで立たされているだけで、その持ち主のイライラは続く。
それがわずか四日続いただけで、輝夫のストレスと怒りは頂点に達していた。これでは、会社勤めなどとても勤まらない。たちまちノイローゼでとびこみ自殺だ。
無理もない。充実すべき第二の人生の初年度、雨上がりの二日目からのカンカン照りで新アカが石を包んだ四日間、最高の鮎釣り日が空しく消えている。
しかも、息抜きに事務所を出て土手に立つと、川には見慣れた釣り人の姿が見えたりする。流れ草を巧みに避けながら弓なりの竿をはね上げて良型の鮎をつぎつぎに引き抜いている患者無視の歯科医や、いつぞやの口うるさい名人殺しなどの姿が、否応なく目に入り、彼の脳細胞を刺激しアドレナリンを噴出させている。この状態で
平然としていられる釣り人がいたら、精神科に行く必要がある。
ともあれ、元校長先生が怒ったのは事実だ。このままでは折角の鮎が釣れない。
「何回電話させるんだ。猪瀬社長は携帯電話ぐらい持ってるんだろ。なに? 山で通じない? そんな場所まで掘り返すなって言いなさい。私が出向いてもいいから……」
イノケンこと猪瀬健吉から電話が入ったのは、それから二日も過ぎていた。シャアシャアと「工事が一段落したから、午後一番で出向く」と、いう。
上流からの浮遊物や濁りが消え、クレームも途絶えた。拍子抜けする以上に身体が疼いて川に誘われる。
留守仕事を、たまたま頭痛癒えて顔を出した女子事務員に任せて、「イノケンが来たら川に来るように」と、いい残して漁協前の川に沈めたオトリ缶を手に、一目散に橋の上流に急ぎ、水晶山を正面に見る松下の瀬下の深みのある流心に狙いを絞って竿を出した。
晴天が続きアカ腐れが始まっていて浅瀬の鮎がいい石を求めて流心の荒瀬に集まっていた。平日ということと昨日までの工事水に嫌気がさしたのか、釣り人の姿は珍しく疎らで貸し切りと言ってもいい状態だった。
五分ほど泳がせて一発目の激しい当たりが来た。
胸が高鳴り腕が軋み足元がぐらつき下流に引きずられるが耐えきると鮎が浮いた。輝夫は空中輸送はしないから慎重に水面下を滑らしてゆっくりと引き寄せ、長く伸ばした水中糸を手繰り、二体の鮎を引き抜き手網に無事納める。なかなかの良型で背掛かりだから元気がいい。
オトリを野鮎に代えて放すと斜め上に走ろうとする。糸を張ってオバセ加減に鼻先を押さえると、それがフェイントになって追い気を誘ったのか、四つ付けた目印が一気に水中に没し豪快な当たりが来た。何メートルか下ってようやく鼻環上の仕掛け糸を手繰って暴れる大鮎を取り込んだ。オトリも良型なのに小さく見える。丸々と
太っている狩野川特有の艶やかな雌鮎でめったに出ない二十八センチ、手にズッシリと重い。二百五十グラムというところか。
これだけで心の臓が割れそうに高鳴る。大型が出るときは数は出ない。
ところが、型は小さくなったがこの日に限って入れ掛かりになり、もう世の中のことは頭から全部抜けきっていた。多分、こんなことは一生のうちでも滅多に無い。もう無我夢中だった。
「先生、大分釣れるじゃないですか」
河原に腰を下ろしたギャラリーが先程からブツブツと小うるさいし邪魔になる。
「うるさいな。黙っててくれないか…」
振り向くと、空色にオレンジ色の大きな水玉模様の入った派手なシャツを着たイノケンが、不機嫌な顔でタバコをふかし煙を吐いている。
「イノ、いや猪瀬。そこで何をして……」
言いかけてハッとする。呼んだのは自分なのだ。
気がつくと、先程まで晴れていたはずの空が低い雲に覆われ今にも夕立ちが襲って来そうな空模様に変わっている。天城峠の方角に稲妻が光り数秒おいて雷鳴が轟いた。
上流が雨なのか、流れが速くなり知らぬ間に水量が増え濁りが混じりはじめている。
大粒の雨が落ちて来た。あたりが急に暗くなる。
水が増え流れが強くなり、オトリ缶の上に置いた重しの石が揺らいでいる。
それを見て輝夫があわてた。引き舟は持たないから獲物は全部缶の中だ。
「おーい、イノケン。ちょっと竿を持っててくれ!」
「さお? なんだ。ワシに鮎を釣らせてくれるのか?」
「なんでもいいから、早く、来てくれ!」
イノケンが嬉しそうにタバコを捨て、靴を脱いで素足になり、立ち上がって水の中に入って来た。
「よし、よこせ。なんだか知らんがわしが大物を掛けてやる」
竿を手渡した輝夫は、上の石が傾いて転げ落ちたために流れ出した缶を追い水辺を走った。ようやく手綱に手が届く。そのとき、イノケンのわめき声が耳に入った。
「来たぞ来たぞ。わしだって鮎ぐらいは……ちくしょう!」
見ると、イノケンの持つ竿が立っているはずなのに穂先が水中に没している。膝までの深さで竿を出していたのが腰まで漬かっていて、ずるずると下流の流心に引きずり込まれている。底石が動いて足場が安定しないのか、素足で滑るのか大きくよろめいた。
異変に気づき、鮎を詰め込んだ缶をあきらめた輝夫が、イノケンの下流側に立ち込んだ。
「だめだ。あぶない! イノケン。竿を放せ!」
「バカいうな。ずーっと鮎を釣りたかったんだ。やったぞ、放すもんか!」
「早く竿を! その下の荒瀬に引き込まれるぞ」
加速度がついてイノケンが水を切って走ってゆく。水しぶきが肩から顔をかくす。
輝夫はイノケン目掛けて飛び込み、思いっきりウエイダーを着けたままバタ足で水面を叩いた。あと十メートルで手が届く。
「やったぞ! 鮎を掛けたぞ……」
歓喜の叫びを残して流心に身を踊らせたイノケンが、まるでサーフィンでも楽しんでいるかのように水を裂いて竿を握ったまま流れより早く大石の間を縫って、下流に落ちてゆく。
それを追った輝夫も流されていた。
水面が烈しい雨で目をあけていられないほど視界が効かないのに、水面下は多少の濁りも気にならない。足元方向に走り去る川底の大石小石の間に川魚が群れ遊んでいる。魚影はかなり濃い。
「おや?」と驚き、ふと疑問を感じた。これは、いつか見た景色ではないか。心のどこかに秘め続けていた懐かしい青春の日々が、一瞬にして甦っていた。
狩野川育ちの輝夫は、岸に泳ぎ着こうとすれば容易に辿りつけるのを知っていながら悠々と流れに乗って泳いでいた。
目の下に広がる水族館のようなパノラマ風景は、まさしくセドのジサマに命じられて観察した狩野川そのもの、起伏に富んだ自然の川が戻っている。しかも、大仁橋下のトロ場を抜け平瀬になるあたりから、水面にしぶくどしゃ降りの強い雨で水も濁り、視界もあまり利かないはずなのに、刻々と移り変わる川底の景色は一層鮮明さ
を増し、アカを削り取った無数の鮎の食み跡はまるで熊笹の葉を型取りしたように大きい。悠然と大石裏の巻きを遊泳している大鮎が反転して輝夫を見た。それも一瞬、輝夫は流され、大鮎は縄張りに戻った。
しかし、それを見た輝夫は愕然として恐怖に襲われていた。大鮎の鋭い歯に派手な色の布がからんでいたのを見た。イノケンの着ていたスポ−ツシャツのオレンジ色の水玉模様が見えたのだ。
(まさか……?)
見慣れた神島橋の橋脚の脇をすり抜けるのに、腕をかき足を振ると、水の中で加速が付いた。水泳は得意だったがこれほどスイスイと泳げるとは思えない。しかも、途中から水面ではなく水中を流れ泳いで、一度も空気を吸っていないことに輝夫は気づいた。
輝夫は意識を失ってゆくのを感じた。
「そんなバカな!」
元教育者として、理論上あり得ないこの状況は納得しかねるものだった。呼吸をしないで泳ぐなど、かつて肺活量日本一と言われた水泳の山中選手でも無理な話だ。これでは窒息死してしまう。
遠のく意識の中で、危険覚悟で水を飲み手足を動かしてみる。
すると、片手を意識して強く動かしたせいか進路が狂い、田京側のへちに寄って下流に流れた。なんと、空気を吸ってない自分が水中を泳いだのだ。それは、気絶後の幻覚だったかも知れないが。
剥き出しの岩盤がえぐれて大小の川魚が石間に揺らぐ川藻を彩りにして重なり合うように群泳している。
ショートカットして直線化したはずの白山堂地区の川筋が大きく湾曲し、石を詰め込んだ蛇篭が幾重にも重なり崩れ水勢がそこで弱められている。危うくその「出し」に激突しそうになりあわてて手足を動かすと、まるで川魚に変身したかのようにスイと身をかわすことが出来、我ながら気分がいい。
その岩盤の裏側に、大きな淵が川岸の底を深くえぐって広がり、そこだけ水流が渦巻いている。これでは、上からは見えない。そこで凄惨な光景を見た。
ピラニアのように群れ狂った魚群に包まれて、イノケンの傷ついた遺体が揺れ、かすかに肌につけた空色とオレンジ色の水玉の布が千切れ、朱色の血が薄められて幾条にも筋を引いて流れていた。
イノケンの両手には、滑らなく熱くならないように輝夫が手作業で巻いた蔓皮の竿尻がしっかりと握られていた。凄まじい執念だった。彼もまた、大鮎に思いを寄せていたのか……。
すでに、大物を意識して用いた0・3のメタ線は岩擦れでか切れている。その切れた糸の端がかすかに見え、その先は淵の奥の光の届かない洞窟に続いている。
そこに、何かがいる。泳ぎ近寄って見ると、暗くて定かではないがそこに倒れているのはセドのジサマで、介抱しているのは台風で死んだ村人達に違いない。その周囲や奥にも無数の人影がうごめいている。洞窟の中の一人が手招きをする。顔に見覚えがある。
輝夫は愕然とした。なんと、狩野川に死んだ村人がそこにいた。
多分、懐かしい顔見知りの人も居るに違いない。
どこかで声がする。
「早く行け。お前だけは生きろ!」
振り向くと、そこには二つの顔があり、敬一と新吾の懐かしくも悲しげな目が輝夫を見て語りかけ、輝夫の体を押した。
「敬一! 新吾!」
叫びながら、輝夫はしたたかに水を飲んでそのまま意識をうしなった。いや、意識はとうに失せていて全ては幻覚だったのか?
雨は止んでいた。
八 それからの狩野川
通り雨がやんで、輝夫とイノケンの姿が川原にないことから、漁協の女子事務員が騒ぎだし、警察と消防が出動し、漁協の組合員にも招集がかけられ大がかりな捜索が始まった。
輝夫の生還はほぼ絶望と見られていたが、一キロほど流されて岸に倒れていたのを救われ、奇跡的に一命を取り留め大仁の病院に担ぎ込まれたときには、病院前に集まった人達から歓声が沸いた。
危篤を知らせられ駆けつけた妻の加代の呼びかけに、かすかに反応したのを見て、医師は助かる可能性がある、と言った。
だが、意識が戻った輝夫は、「イノケン……」と、猪瀬の通称を呼び続け、それが警察の疑念を生んだ。
漁協の女子事務員の証言によると、輝夫に呼び出された猪瀬健吉は、かなり殺気だった表情で、輝夫のいる大仁橋上流に向かったことが判明している。
警察では、二人が乱闘になり川に入り込んで流されたものと見たが、署長自身も、自分の恩師でもある輝夫を、猪瀬健吉殺害容疑で調べなければならない状況に困惑しきっていた。
しかも、数日を経て下流の岩場で発見されたその猪瀬の死骸が、白骨剥き出しの酷い様にも係わらず、折れた鮎竿の竿の太い部分だけをしっかりと握っていたことから、輝夫が用いた鮎竿を逆に猪瀬が奪って闘ったのではないかとも推測され、輝夫が柔道の有段者であることも不利に働いた。
危篤状態を脱した輝夫の回復を待って、臨床尋問が行われた。
輝夫から、竿を預かったイノケンが慣れない大鮎を掛け、足場を崩されて溺れ、それを救おうとした輝夫も溺れた、と、いう証言について、警察内部でもその真偽のほどが問題になった。
しかし、輝夫の教え子でもある大仁警察署の署長が、恩師の人柄からみて偽証はないと断定、殺人の疑いは辛うじて晴れた。
輝夫は、その奇異な体験についての真相を黙して語らない。本人自身が幻覚である可能性を否定できなかったからだ。
猪瀬の死は、単なる水難事故として処理されたが、謎は多い。
だが、猪瀬の司法解剖に立ち会った医師と静岡県私立水産試験所職員の証言から、傷痕の殆どが大型の鮎に噛み千切られていることが判明、鮎の持つ本来の凶暴性がなぜ誘発されたのかという疑問がまた論議を生んだ。
鮎竿が鮎の群れに恨みを買ったのか、シャツの模様のオレンジ色が縄張り鮎の金マ−クと誤認されたのか、それとも鮎そのものが鮎の棲む川を破壊するイノケンを天敵として認識していたのか……、
水産試験所の職員、警察内部の鑑識班では結論が出ず、水棲動物の権威といわれる水産大学の名誉教授まで討議に参加したが、ついに科学的根拠もないままに終わった。
ただ、この事件を知った県警本部科学警察研究所の犯罪色彩学専門の鑑識主任が、鮎は黄金色系に反応するという説を大仁署長に寄せたため、ある教訓が、一週間ほど狩野川に残った。
この事件の後で、狩野川漁業組合事務所の入り口左のコンクリ−ト壁に、踊るような下手な油性ペンで書かれた、釣り人向きの張り紙を記憶している人も多いと思う。
「川に入る人は橙色系シャツの着用を避けて下さい。鮎に襲われる危険性があります。この件で当組合は責任を負いません」
だが、折角の張り紙も、口うるさい狩野川常連の名人殺しヤマトモの一喝で破棄された。
「こんな根拠のないヨタをとばすと、狩野川はダメになるぞ!」
確かにその直後、釣り人の姿は川から消えていた。
ヤマトモは、狩野川を愛するが故にいつも苦言を呈している。
狩野川は、往年の面影を少しづつ取り戻しつつあるが、川を地元漁協の私有物と錯覚を起こしている漁協員や、食べ残しのゴミやハリ付きの糸などを捨てて帰る心ない釣り人が存在する限り、一度失った「天然鮎の宝庫・狩野川」の復活は、絶望となる。
これは、どの河川でも共通の悩みではあるが、漁協と釣り人のモラルによっては復活も可能なはずなのだ。
落ち鮎の季節になり、上流から落ちた鮎が大仁地区の神島橋あたりに群れている。
その神島橋の上部西岸では、心身癒えた輝夫が大鮎を掛けていた。竿を絞るその嬉々とした立ち姿には青春が戻っている。
孫を連れて弁当を持参した妻の加代が、孫と声を合わせて「お昼ご飯ですよう」と、水際から叫ぶが、こんなときの輝夫には聞こえるはずもない。
いま、天城山中に源を発して、伊豆の山々の緑を写して流れる清冽な狩野川の水は、永遠の謎を秘めて流れて行く……。
終
